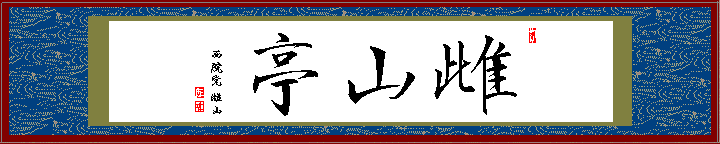

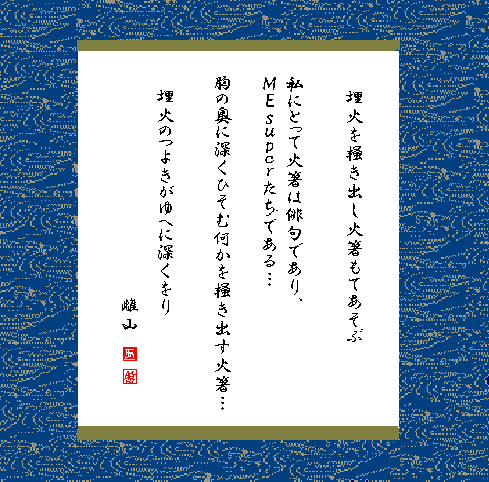
履歴・雑感など 一年目はここ 二年目はここ 三年目はここ 四年目はここ 五年目はここ 六年目はここ 七年目はここ
八年目はここ 九年目はここ 十年目はここ 十一年目はここ 十二年目はここ 十三年目はここ 十四年目はここ
十五年目はここ 十六年目はここ 十七年目はここ 十八年目はここ 十九年目および二十年目はここ
|
四季を色に分けることは、唐土の思想である四神信仰から来ているもので、わが国でも高松塚古墳などの玄室壁画に見られるように、飛鳥・天平以前に渡来した考え方である。 季節は青春、朱夏、白秋、玄冬と色を付けて呼ばれるが、それぞれ青龍、朱雀、白虎、玄武の四神を配する。
俳句は写生の具にあらず。心象の表現手法なり… 俳を忘れず、喜怒哀楽を形に残す… 俳とは「人」に「非」ずと表す。ゆえに、人がましくては俳にあらざるなり…
|
|
亭主は憶良好きである。万葉集は 、古今和歌集など後の時代の歌集より人間のなまの感情を飾り気も少なく、直裁に歌ったものが多いが、そんな中でも、無比にして異彩を放つ歌が山上憶良の歌である。 柿本人麻呂、山部赤人など他の称揚される歌人の歌からは、詠み人の実像を想像することは難しいが、憶良の歌からは、そのひとの人間としての本質のみならず、風貌骨柄のすべてまでが浮かび上がってくるようだ…
|
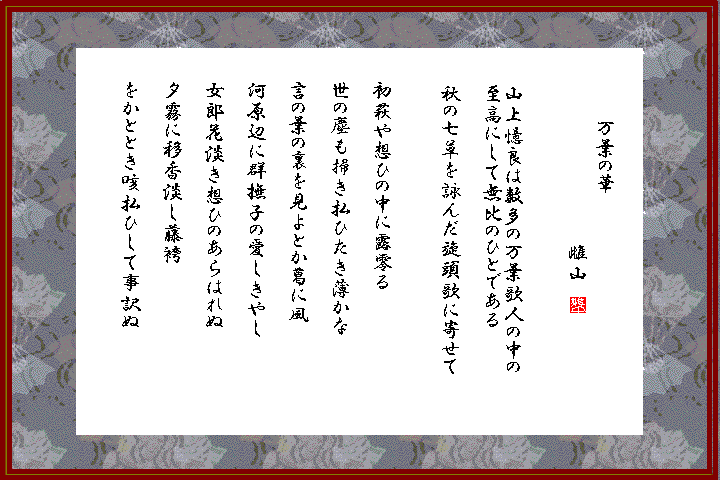
|
山上憶良が筑紫守のときに、 時として敵意を向け合うことも多い大陸・半島に対峙する前線基地九州各国の束ねである大宰府帥として赴任した大伴旅人と出会い、二人は水魚の交わりを為した。 「あをによし…」の小野老などとともに 、世に言う「筑紫歌壇」を形成する中で、互いにまったく異質な歌人である二人は、山上憶良の「日本挽歌」に見られるように、身分の上下をこえた、ひととしての絆によって深く結ばれていたように思われる。 旅人の子、家持も少年期に父に従って筑紫にいたが、憶良の薫陶を受けたことは、防人歌のことを思えば想像に難くない。憶良が著したと万葉集に繁出する「類聚歌林」自体は今に伝わっていないが、亭主は、家持の編んだ「万葉集」の底本となっているのでは、と推定している。
山上憶良は、氏姓家柄で世に出た貴族ではない。テクノクラートととして頭角を現した人物である。そもそも、出自は明らかではないし、その末裔の消息もつまびらかではない。大陸か半島からの渡来人の可能性も高い。名からすれば 、類似例を見る百済人を強く思わせる… しかしながら、続日本紀に記された断片的な経歴や、万葉集に残されたその珠玉作品を見れば、当時の第一級の教養人であることは疑う余地が無い。漢詩の素養、宗教的な知識の深甚さ、その精神世界の奥深さ、どれ一つとっても 、鳥肌が立つほどに傑出した人物と見えてくる。
万葉集は家持が編んだというより、家持の私的な学習ノート、備忘録、記録帳そのものであったのだと亭主は確信している。その中での山上憶良の取り上げ方を見れば、家持が憶良に対していかに敬意を抱いていたかが感じ取れる。決して平坦ではない生涯を過ごさざるをえなかった家持の人格を築き上げた主たる要素として、憶良の強い影響が窺い知れるのである。
2019年4月1日、新元号が「令和」と決まった。その典拠となったのが万葉集巻の五、「815」から「846」までの32首の歌の前に置かれた「序文」ということである。 この「序文」は、天平二年正月13日に大宰府帥大伴旅人の屋敷において大宰府の主な役人や北九州各地の国司などが集まって観梅の宴を開いた時に詠まれた歌を集めている32首の序文として置かれているものだ。 そこで、この「序文」を書いたのは誰かということになるが、それは「山上憶良」であろうというのが亭主の推定である。 その根拠は、「巻の五」の巻頭の歌である挽歌およびその序文のうち、その序文に流れる技巧、思考が新元号の典拠となった「序文」のそれと同等であると見えるからである。観梅の宴の歌には「憶良」の歌も含まれているし、いわゆる筑紫歌壇の主要なメンバーであった唐帰りの漢詩が巧みな「憶良」がそれを作ったと考えるのは自然なことだと思う。 それに、この前後に置かれている歌は「憶良」のものばかりである。「家持」は「憶良」を偲ぶためにこれらをまとめているとしか思えない。 「序文」の構成も、宴の主催者ではなく、客であるその参集者が作ったものであることは読み取れる。参集者の中で身分が高く、最も漢文の素養が高そうなのは「憶良」を置いていない。 そもそも、この時の歌々を記録保管したのは「憶良」その人であったのだろう。そしてそれが「類聚歌林」なのだろう。 藤原氏の血が濃く入っている今の皇室であるが、その藤原氏と幾多の確執を持って、ついには逆賊とされた大伴氏の著作物を史上初の国書典拠とする新年号ということは、万葉集の本質を知らぬ者が選んだのではあろうが、長い時の流れたことを思わせるものだ。
|
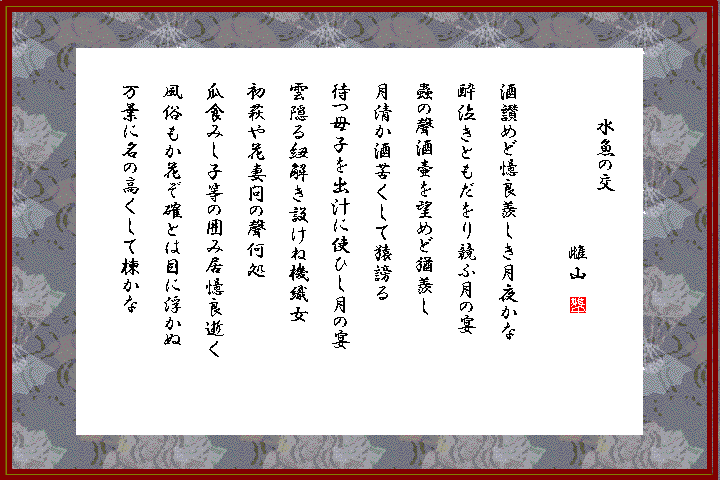
|
正岡子規没後百年を迎えたが、子規の提唱した俳句は、「俳諧の発句」からの解脱を目指したものとされている。あえて芭蕉を批判し、蕪村を評価したその主張を、自己の句作によって示そうとしたようである。 今日代表作、というより子規の俳句として一般人の知っているものといえば、
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
という句しかないのではと思われるが、この句の何がかくまで人口に膾炙させるのか、名句とされるのか、写生文という概念を推し進めた子規のこの句に込めた思いが何なのか、子規という人間をまったく知らない場合に、この句を詠んだ状況を承知していないとした場合に、つまり、浅学の亭主がまさにその状況なのだが、単に俳句として鑑賞した場合にどのような感銘を得られるのか、共感を得られるのか、虚心になって凝視してみた。
まず、この句から読み取れる情報を列挙してみる。 「柿くへば」とあることから、季節は中秋を過ぎた頃から晩秋のころというのが妥当であろう。詠者子規が柿好きだったかどうかで句の解釈は変化するのであろうが、嫌いな人があえて柿を食うという状態を句にする必然性は少ないし、子規は柿が好きだったと解釈するのが自然であろう。 「鐘が鳴る」というのは、時刻を表していると解釈できる。その「時刻」としては、何の説明も無い以上は、晩鐘の鳴る時刻が柿の色や晩秋という季節と「響き合って」相応しく思われる。何の共感や感銘なくして句作するというのは、いかに「写生」といっても無理があろう。 「法隆寺」とあるからには、場所は大和盆地奈良郊外の斑鳩の地、山近くの田園風景の広がる秋景ということになる。 また、「柿」という詞から夕焼け空も連想され、山の端に茜に染まった雲のかかる情景も目に浮かび、帰巣する鴉の鳴き声も耳に届いてくる。これは季語の持つ力でもある。 「鐘が鳴る」という詞から聞こえてくるものは遠い響きであり、乾いた空気であり、付近の静寂であり、このことからも、晴れた夕暮れの落ち着いた情景であると見えてくる。 柿を好む人間がその舌で味わっている喜びと眼前に広がる景色から得る感慨と、耳に届く遠い鐘の響きと、さらには皮膚にも秋を感じ、五感のすべてが古都の秋の中にいる自分を写生した、というのがこの句のありよう なのだと解釈することができて、これが読み取ろうとする人の感性と共鳴するときに名句との評価が生まれたのだと推量するのである。
この句を鑑賞して得る限りにおいて、芭蕉と、蕪村と、一茶と、その他数多の世に知られた俳人の句と等質であり、ことさら革新的とも言えず、単に俳句の本質を把握したに過ぎない。この句は詞によって「写生」したものではないが、心象に写生させた句であると結論することができる。 しかしながら、この句には心情がこもっているとは見えず、それが物足りないと感じさせる原因だと思う。芭蕉の句にはそれがある。その分、凄みの質に差があるのである。
|
|
変な例えであるが、俳句というのは 、日本料理と共通するものがあると思う。旬の素材を生かして調理し、吟味した器に感性を尽くして盛る、この日本料理における器が、俳句の季語だと思うのである。 素材のために器を選ぶように、使いたい言葉に合った季語を選ぶ、吟味する、この愉しみが 、俳句の醍醐味の一つだと感じている。 その反対に、器を生かすための料理というものがあるように、季語を選び出し、その季語にあった俳句を作る、テーマを選び 、ことばを選ぶ、という愉しみもまた捨てることが出来ない。そうして積み上げた詞の中からある感情が滲み出してくれば、それを感じることができれば、それは 、美味しい料理と等質と言えるのであろう…
技法は様々、巧稚は問はず、月並みの謗りは甘受すべきもの、ことばという素材を調理して 、季語の器に盛り付けて、季節を身近に引き寄せて、人の世を眺め暮らすことにいたそうぞ…
|
|
俳句と写真には多くの共通点がある。正岡子規の提唱した「写生」という点もそうであるが、写し切り取ったものが人に語りかける点も 、俳句と写真は等質である。また、切り取り方で実際とは異なった世界を演出する点も類似している。十七文字というフレームの中で、近・中・遠景の奥行きを持ち、超望遠にも魚眼にも変化するズームレンズのような俳句を詠む、これが亭主の目指すものであり、至高不達の存在でもあるのだ。
|
|
俳句 という言葉を創設敷衍したのは子規であるが、その弟子の高浜虚子が唱えた俳句のあるべき姿としての「客観写生」と「花鳥諷詠」という概念は、提唱者である虚子がそれを理論として明示しなかったことから、その本質が何なのか、いまひとつ分からないところがある。 虚子は、「私は客覿の景色でも主観の感情でも、単純なる叙写の内部に広ごつてゐるものでなければならぬと思ふのである。即ち句の表面は簡単な叙景叙事であるが、味へば味ふ程内部に複雑な光景なり感情なりが寓されてゐるといふやうな句がいゝと思ふのである。」(「ホトトギス」大正13年3月号)と述べている。これが虚子の言う「客観写生」なのだろう。そうだとすると、これはまったくの独学である亭主の句作において志向する 今の踏み位置とほぼ等質である。 また、「客観写生とは自然を尊重して具象的に表現すること。まず観察することが基本ですが、それを繰り返していると、対象が自分の心の中に溶け込んできて心と一つになる。そうなると心が自由になり、最も心が動くようになる。」 とも述べている。虚子はこの場合の「自然」の中に己を含む人間を当然のこととして含めていると考えるのが妥当であろう。 後に唱えた「花鳥諷詠」に関しては、「春夏秋冬四時の移り変りに依って起る自然界の現象、並にそれに伴ふ人事界の現象を諷詠するの謂(いい)であります」(『虚子句集』)と述べている。この場合における「諷詠」の定義が虚子の中でどのようなものであったのかが不明なので、分からないという気分が残るのである。 「諷詠」が単に詩歌を詠むという意味だけだとするのは、「客観写生」というときの「写生」の意味の広がりから類推すれば無理がある。虚子は「諷詠」という言葉に虚子なりの概念を持たせていたのだと考えるほうが無理が無い。亭主は 、虚子の「諷詠」は、即ち「客観写生」であると理解している。
明易や花鳥諷詠南無阿弥陀 虚子
この句は、晩年に近い文化勲章受賞の年の虚子の句である。花鳥諷詠とお題目は等質、かつ明快にして平易である、と主張するものであったと解するのは、亭主の読み過ぎであろうか…
|
|
松尾芭蕉は俳諧の巨人である。貞門から入って談林へ転じ、蕉風を確立した遍歴を持つ。その蕉風を確立する過程で成したのが奥の細道であるが、その旅程における冒頭句の解釈をする上で、芭蕉の遍歴は大きな意味を持つと考える。
行く春や鳥啼き魚の目は泪 はせを
この句を解釈するならば、 「行く春」が実際の旅立ちの季節と旅立ちを掛けているのはもちろんであるが、行春、すなわち晩春を今の芭蕉自身の立ち位置であると主張し、そこから離れるとの宣言である。 貞門の常套である古典からの引用として、孟浩然の五言絶句「春暁」から起こした「鳥啼き」は、「魚の目は泪」を起こすための対句であり、しかも啼くは誇り主張するの意であるから、貞門からの旅立ちを示すものとしている。 また、「とりなき」は実際に足にある「魚の目」が取れなくて痛くて悩んでいるとの諧を込め、また、魚の目はなかなか離れ克服することが出来ない貞門や談林を暗喩していて、「泪」がその直前の文中に記述した「涙」でないのは魚の「目」に水であって、「魚の目」すなわち貞門や談林は水に流し去って「戻」るつもりが無いという決意の表明である。 さらに全体として表現しているのは、旅立ちの別離の悲しみはあるが、決して泣くのではなく、涙するのではない、未知に(道に)向かう歓びが本意であり、別れの涙には見えても 、実は単に目に水が浮いているだけなのだよと…
こんな解釈は穿ち過ぎであろうが、奥の細道を読めば、芭蕉の諧謔な心底は透けて見える。畢竟、芭蕉の本質は高尚な貞門ではなく、卑俗な談林であるのは自明なるべし…
|
|
芭蕉の弟子のうちの有力な俳人を指す言葉として「芭蕉十哲」というものがある。それでは、その10人は誰かというと、色々な説があって定まった10人ではないのであるが、そんな中に選ばれる有力弟子の一人に、美濃国関の広瀬惟然という人がいる。芭蕉の臨終を看取ったぐらい 、いつも晩年の芭蕉の身近にいた弟子の一人なのだが、この人の句は、他の弟子とは随分作風が異なっている。芭蕉がその晩年期に提唱した「軽み」ということを最も理解実践した人なのかもしれない。軽過ぎると 、嫌い詰った兄弟弟子も多かったのだが… しかし、後世の俳人小林一茶は、この惟然を、その句作の師と位置付けていたようだ。
おもたさの雪はらへどもはらへども 惟然
この句は、家族を捨てて出家しさすらう惟然に会いに来た娘に会うことをせず、放浪の旅に出てしまったときに書き残したものとのことだ。その娘は 、この句を見て惟然の心を悟り、みずからもまた出家したとか…その背景があることで、おもたさの意味が深くなる…
水鳥やむかふの岸へつういつい 惟然
水鳥の句、同じものを見ているのだと思うのだが、亭主の作に比べて抜群に軽い。その軽さは、水の底に沈む重さを対置している上でのことなのかもしれない。 亭主が広瀬惟然とその作品を知ったのはつい最近のことで、下の拙句は、それより随分前に作ったものである。なので、比較して自己批判の対象とするに適当であろう。
旅の鳥か寄りかく寄る冬汀 雌山 来し方は鴨の水掻き行く末も 雌山
|
|
俳諧というものは、連歌を起源とすることから「座」の文芸であった。まさに、知的な「座興」を目的としていたのだ。それゆえに、古典の素養を必要とし、それを縦横駆使することを貴ぶ貞門、卑俗を厭わず諧謔の心を豊かに遊ばせることを求める談林の隆盛があったのだ。それを「個」の文芸へと変容させたのは、芭蕉の「奥の細道」で代表されるように、旅という当時多くの辛苦を伴った非日常性の記録である紀行文としての俳文の一要素として置かれたからであろう。俳文と句の融合体が文芸としての姿だったのであるが、それを「俳句」として単に17文字だけで独立させたのが正岡子規の主張だったのかもしれない。それは、その句の背景を一切示さなくとも成立する文芸ということだが、そのときの詠み手の心情を切り取り残すという点において、季語などの約束事を数多く含む定型詩の窮屈さが、より本質を求める純粋さを必要とするのかもしれない。これは 、仏教における悟りの境地、禅の本質と類似、または等価なのではとすら思える。 亭主は看破するが、俳句は観賞の文芸ではない。共感の文芸である。句作者にとっては、己の過去を回顧するよすがとなる心の有りようを切り取った記録である。よって、共感の元となる体験少なき者 、あるいは心の豊かな働き少なき者には、無価値に近い文芸である。 畢竟、作られ在る俳句を客観視した場合に、それとどれくらい共感出来るかで、作者および己の心の有り様を測る物差しとすることができるのかもしれない。 |
| 2008年 | ||
|
|
迫り来る足音高し冬土用 炬燵から腕伸ばして豆拾ひ 東風吹かば律儀に生きよ白き梅 早春の月満ちていていざその日 春風や孫の寝顔に見入りけり 股引を脱捨て春は吾がものに 春風や嚏嚏で佳ゐ噂 拘りを洗ひ流して春の雨 夜明け待つ肌の湿りて春の雨 芽を出して赤子のお指金木犀 満開の櫻の下は何埋める 大根の右往左往やにはか雨 老の坂見晴るかしけり秋隣 桃の実の媚を尻目に思案かな 残り物余り物でも残暑かな 夜具恋し夜半の目覚めや秋腐し お指折り残り確かむ秋彼岸 初めての月の瞳に満ちてをり 青空を目に張りてをり赤蜻蛉 いとけなきお指の指せり曼珠沙華 抱かれて小首傾げて蜆蝶 赤蜻蛉見据ゑをりたり吾が姿 幾人の想ひ嗤ふや吾亦紅 未だとは成す励みなり後の月 言訳の積もり積もって後の月 色づゐて在るを悟れり柿大樹 盛りより名残り愛でたし後の月 名残り惜し別れ近付く十三夜 身を守る術を持たずや栗の月 渋皮の爪に刺さりて月仰ぐ 二つ三つ目のほころんで栗御飯 秋故に心沈みて愁ふめり 胸張って空を抱けよ鱗雲 櫻木の葉の赭くなり冬隣 春の日の来るを願へり今朝の冬 育みの糧を勤めり熟柿 苔覆ふもみじ葉愛し三千院 もみじ伝ふ音羽の滝の時雨かな 錦着て晴々しけり嵐山 遣り残す心地ぞ募る冬紅葉 老ゆれども活計に追はる師走かな 乳呑児の母を追ふ目の圓かな 肘笠で凌ぐ風流や葉の嵐 絵心の無きを悲しめ落葉掃 舌鼓打ちつ打ちつの冬の旅 覗き込む己の内に炎立つ 埋火の炎となりて焦しけり 散る時を愛しと叫ぶ山燃る 赤き実よ流離ふ魂の糧となれ
|
せまりくる あしをとたかし ふゆどよう こたつから かひなのばして まめひろひ こちふかば りちぎにいきよ しろきうめ そうしゅんの つきみちていて いざそのひ はるかぜや まごのねがをに みゐりけり ももひきを ぬぎすてはるは わがものに はるかぜや くさめくさめで よゐうわさ こだはりを あらひながして はるのあめ よあけまつ はだのしめりて はるのあめ めをだして あかごのおよび きんもくせい まんかいの さくらのしたは なにうめる だいこんの うをふさほふや にはかあめ おひのさか みはるかしけり あきどなり もものみの こびをしりめに しあんかな のこりもの あまりものでも ざんしょかな やぐこひし よはのめざめや あきくたし およびをり のこりたしかむ あきひがん はじめての つきのひとみに みちてをり あおぞらを めにはりてをり あかとんぼ いとけなき およびのさせり まんじゅしゃげ いだかれて こくびかしげて しじみちゃう あかとんぼ みすゑをりたり わがすがた いくたりの をもひわらふや われもこふ いまだとは なすはげみなり のちのつき いひわけの つもりつもって のちのつき いろづゐて あるをさとれり かきたいじゅ さかりより なごりめでたし のちのつき なごりをし わかれちかづく じゅうさんや みをまもる すべをもたずや くりのつき しぶかはの つめにささりて つきあほぐ ふたつみつ めのほころんで くりごはん あきゆゑに こころしずみて ふれふめり むねはって そらをいだけよ うろこぐも さくらぎの はのあかくなり ふゆどなり はるのひの くるをねがへり けさのふゆ はぐくみの かてをつとめり じゅくしがき こけおおふ もみじばかなし さんぜんいん もみじつとふ おとわのたきの しぐれかな にしききて はればれしけり あらしやま やりのこす ここちぞつのる ふゆもみじ おゆれども たつきにおはる しはすかな ちのみごの ははをおふめの つぶらかな ひじかさで しのぐふりゅうや はのあらし ゑごころの なきをかなしめ おちばはき したつづみ うちつうちつの ふゆのたび のぞきこむ おのれのうちに ほむらたつ うづみびの ほのほとなりて こがしけり ちるときを かなしとさけぶ やまもゆる あかきみよ さすらふたまの かてとなれ |
| 2009年 | ||
|
|
初春やレンズの向ふに明るさを 苔の庭突き崩しけり霜柱 ひよどりの冬越へ支ふ夏蜜柑 春暁や寝静まれかし咲耶姫 空耳に夜泣声聞く北の冬 春隣夕餉の支度遅れけり 空舞ふは灰か花粉か今朝の春 縮かまり空見上げれば春の雪 居心地の悪しき古巣や初燕 ささがにのいと絡みけり紅の濃き 乳離れの母と子の間秋袷 銀を金に紛ふ芒原 蟲啼き望む月の出でけり 憶良らの家路を辿る夕闇を 照らして明かし望月の出で 瓜栗のめごひ子等寝て月夜かな 有明の月の隠れて末の松 食言の蔓延る国や冬隣 月満ちて明日は欠くらむ冬隣 家持の縁を梯に冬の旅 幾秋霜澄み沈みけり塗師の技 朝市や蟹の甲羅の犇めけり 塩竈の守人技を誇りけり 白米を幾把得たるや千枚田 古の家格に繁し萱の雨 狼煙絶ゆ禄剛崎に時雨かな 南無遍照能登金剛の濤の華 七五三祝ふ気の充つ気多社 千里浜や濤の華舞ふ砂の飛ぶ 五箇山の屋根拝みをり神の留守 デフレ憂ひ夜具引き被る霜夜かな 蟻の如暮し来たりて霜夜かな 清水の舞台の端に佇みて 其を跳ぶ夢の未だ醒めざる 衒ひ無く最敬礼する孫厚着 冬晴れや北の空見る渡り鳥 家々の電飾の垣見回れる をさなご伴に流れ行く日々 北国の天気図気になる師走かな 雪国の民の苦想ふ晴れの日々
|
はつはるや れんずのむこふに あかるさを こけのには つきくずしけり しもばしら ひよどりの ふゆごへささふ なつみかん しゅんぎゃうや ねしずまれかし さくやひめ そらみみに よなきごえきく きたのふゆ はるどなり ゆふげのしたく をくれけり そらまふは はいかかふんか けさのはる ちじかまり そらみあげれば はるのゆき いごこちの あしきふるすや はつつばめ ささがにの いとからみけり べにのこき ちばなれの ははとこのあひ あきあわせ しろがねをくがねにまごふすすきはら むしなきのぞむつきのいでけり おくららのいえじをたどるゆうやみを てらしてあかしもちづきのいで うりくりの めごひこらねて つくよかな ありあけの つきのかくれて すえのまつ しょくげんの はびこるくにや ふゆどなり つきみちて あすはかくらむ ふゆどなり やかもちの えにしをはしに ふゆのたび いくせひそう すみしづみけり ぬしのわざ あさいちや かにのこふらの ひしめけり しほがまの もりふどわざを ほこりけり しらよねを いくはえたるや せんまいだ いにしへの かかくにしげし かやのあめ のろしたゆ ろっこうざきに しぐれかな なむへんじゃう のとこんごうの なみのはな しちごさん いはふきのみつ けたやしろ ちりはまや なみのはなまふ すなのとぶ ごかやまの やねをがみをり かみのるす でふれうひ やぐひきかぶる しもよかな ありのごと くらしきたりて しもよかな きよみずのぶたいのはしにたたづみて そをとぶゆめのいまださめざる てらひなく さいけいれいする まごあつぎ ふゆばれや きたのそらみる わたりどり いへいへのでんしょくのかきみまわれる をさなごともにながれゆくひび きたぐにの てんきづきになる しはすかな ゆきぐにの たみのくをもふ はれのひび
|