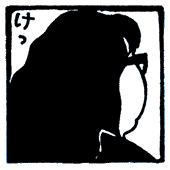
| ナンシー関 〜そのツッコミ魂忘れまじ〜 |
<著名人などのコメント>
これも著作権侵害ですが…
順序に特に意味はありません
彼女の死は「思想的事件」〜ナンシー関さんを悼む〜 民俗学者・大月隆寛(産経新聞6月13日)
「オレ、ナンシーの葬式には出そうな気がするなあ」そんなことを本人によく言っていました。朝、彼女の担当編集者から訃報を聞かされて、まずそのことを思い出しました。今から6、7年前、某女性月刊誌連載の対談で毎月顔を合わしていた頃のことです。
「ナンシーに顔を彫られると不幸になる」などというありがたくない噂が立ったのも、その頃です。実際、当時はあたしも公私共に荒れ模様で、「なんか、あたしと仕事すると大月さんロクなことないっすねえ」と、あきれられていました。時事問題をネタにした対談でしたが、彼女のあの調子で毎回やりこめられながらも、彼女の健康状態はずっと気になっていました。実際、あのガタイ、あの風体でしたから、こりゃ心配するなというほうがムリです。
訃報は常に大文字です。彼女もまた「ユニークな消しゴム版画家」「辛口のテレビコラムニスト」、といったもの言いで語られ、追悼されるのでしょう。もちろん、それは間違いではない。世間にとってのナンシー関とは、おおむねそういう書き手ではありました。
でも今、ナンシー関がいなくなった、ということは、単に雑誌界隈が面白くなくなる、といったこと以上に、実はかなり大きな思想的事件だということを、心ある人たちはそれぞれしっかりと感じているはずです。それは例えば、三島由紀夫が割腹自殺し、連合赤軍があさま山荘で篭城し、オウム真理教が無差別テロをを展開した、それらとある意味匹敵するくらいの大きな時代の転換期を象徴するできごと、になるはずです。
彼女が斃(たお)れた、ということは、80年代出自の価値相対主義思想の、その最良の部分が失われた、ということに他なりません。笑わないで下さい。これは本気です。その意味を、これからあたしたちは深く思い知ることになるはずです。
(記事にはこの他に消しゴム版画として、「週間朝日」6月14日号の石原慎太郎都知事が掲載されていた)
今日のヒトコト 岡田斗司夫(2002.06.12付
HP「OTAKING」より転載)
コラムニストのナンシー関さんが亡くなりました。
ショックで悲しいです。
単行本は全て持っていました。
でも、いま悲しいのは「新作が読めない」というのとは、違う気がします。
ああ、僕はナンシー関が好きだったんだなぁ。
東奥日報 「天地人」 (朝日新聞でいうところの天声人語か) 2002年6月14日(金)
「週刊朝日」の連載コラム「ナンシー関の小耳にはさもう」。六月二十一日号は、作家の辻仁成さんと女優の中山美穂さんの入籍の話だった。時々このコラムを読んで、思いがけない視角からの発言に「ウーン」と感じることがあっただけに、突然の訃報(ふほう)に驚いた。関さんは青森出身。まだ三十九歳の多彩な才能が惜しまれる。
ユニークな消しゴム版画や辛口のテレビ批評などで知られる。著書の「顔面手帖」(シンコー・ミュージック)に自画像がある。「カッターと生きる」とあり、消しゴム版画に関心を抱いたころのことも書いている。高校生の時に彫った喜びと、それをあちこちに押しまくる「ある種の征服感」と。
肩に力を入れずに、しかもハチの一刺しのような鋭さも。そんな文章を書く人だった。雑誌で連続対談をした民俗学者の大月隆寛さんは、その視線に触れて「ビシッと反応する感度と解像度」と。一九八○年代に仕事を始めた関さんらの、新しい感性を言ったのだと思う。
半面、こんな文章もある。「ちゃんとした生活、それはものを腐らせない暮らしだ」(「何の因果で」世界文化社)。青森から上京し、暑さでものがどんどん腐っていくことに驚く。で、生活をやりこなせていない自分を恥じ、古里の母の難なく暮らしを切り回している姿を思う。
こういうところが多分、関さんの素顔なのだろう。外への敏感なまなざしと、内に秘めたまっとうな生活感覚。そんな文章を、もっと読みたかった。
元記事へのリンク
ナンシー関急逝に寄せて (小田嶋隆 公式HP「おだじまん」内「偉愚庵亭日乗」より)
今日の昼頃、Asahi.comだかを眺めていて訃報に気づいた。
何と言って良いのやら。
取り替えのきかない人だったと思う。
テレビを観ている人はたくさんいる。
批評眼を持った人間がまるでいないわけでもない。
しかしながら、もののわかった人で、なおかつきちんとテレビを観ている人間はほとんどいない。
ものがわかってくる年頃になると、人は、ふつうテレビなんか観なくなるからだ。
そういう意味で、ワンアンドオンリーな人だったと思う。
スタンドアローンな、唯一の、かけがえの無い、稀有にして再生不能な才能だったと思う。
合掌。
たしか、最初の単行本の書評をどこかの雑誌に書いた。
以来、著書が出るたびに送ってくれていた。
義理堅い人だったのだと思う。単に事務所がしっかりしていたのかもしれないが。
4年ほど前に、一度、月刊誌の対談で同席した。
目のやり場に困る巨体だったが、ひとたび挨拶を終えると、十年来の知己に対するように自然に話をすることができた。
こういうことはとても珍しい。
つまり、私のような偏屈な者が初対面の人間に対して素直にふるまうことができたのは、ひとえに、相手が立派な人間だったからなのだと思う。
訃報に触れて、呆然としている。
長い間、離れて住んでいる知り合いみたいな気分で暮らしてきたが、実際には、一度しか会ったことがないわけで、こうなってみると、もっと会う機会を作っておけばよかったと、残念でならない。
同業者としても、指標を失った感じだ。
彼女に対して感じていた尊敬とシンパシーは、そのまま、喪失感として私の中に残るだろう。
冥福を祈りたい。
彼女が彼女にふさわしい神様のもとにたどり着けるように。
……って、最後の一行はクサかったか?
ナンシーよ。
「けっ」 と、笑ってくれ。
02/06/13/木 01:55
元のページへ
ナンシー関、急逝。 (人気サイト「日記猿人」BOWWOW氏 6/11〜12付)
今回は、
あるんだか無いんだか分からない予定
を変更して、ナンシー関さんのご冥福をお祈りする
短い文章を掲載いたします。
アサヒコム(朝日新聞)6月12日(水)13時24分から
(急死を知らせるニュースが引用されているがこれは略します)
ここ2週間ほどの「週刊朝日」と「週刊文春」の連載コラムでは、
いつものスタイルの
「テレビ番組から直接引用したタレントの発言」をネタにせず、
活字媒体などからのタレント発言の引用をネタにしていたので、
彼女は好きなテレビが見られない状態なのかな?と
不思議に思っていたワシである。
やみくもに消費され消えていく「テレビ」(番組とかタレントとか人気とかブームとか成功企画とか失敗企画とか)
に対して、
番組やタレントなどの、意味の固定(あるいは、無意味さの固定)は
彼女の批評によってなされていたと言える。
ふわふわととめどなく動き回り、やがてすぐ消えてしまうシャボン玉が、
彼女の言葉で、誰の目にもはっきりと、永遠に観察し認識することが可能になる。
彼女の言葉は、だから、魔法のようなものであったのだ。
今後、誰が、シャボン玉を固定して見せてくれるというのか。
彼女がいなくなった穴は、あまりにも大きい。
テレビ批評の世界の、大きな穴。
彼女がものすごい肥満体であることの比喩ではなく。
ご冥福をお祈りいたします。
ナンシー関は全力で投げ続けた (朝日新聞6月14日夕刊「マガジンウオッチ」 亀和田武)
ナンシー関の批評センスは最後まで冴えていた。「週間朝日」の連載「小耳にはさもう」(6月21日号)のネタは中山美穂と辻仁成の入籍。
「中山美穂はどんな速球にも逃げることなくバッターボックスに立ってきた」「美人といえば中山美穂」という重い大看板を背負わされても、それにこたえるべく頑張ってきたに違いない」。この畳みかける語り口が圧巻だ。対象へ一気に肉薄するスピードと角度は誰もマネできない。「豪速球にも振り遅れず、荒れ球を見極め、クセ球には技術で対抗してきた中山美穂だが、今回の辻仁成政って全く新しい変化球だったのでは。いや(中略)デッドボールか。危険球かも」
ナンシー関はその消しゴム版画も含め、生涯コラムニストを通した。コラムを書きつづけるのは至難の技だ。経済基盤の危うさにくわえ、生モノを扱う商売だから、時代とズレれば一巻の終わりだ。コラムニストの旬の時期は短い。切れ味鋭いコラムも半年つづくと、鮮度が落ちる。
大半の書き手はそうして消えていく。達者な書き手が活躍の場を広げるケースも稀(まれ)にある。泉麻人、リリー・フランキー、中野翠。しかし彼らの関心は、ある時期を境にうつろいやすい事象から、もっと確個とした自己の内面に向かった。コラムニストは作家へと転身していく。
コラムは下世話な一過性の出来事しか扱わない。そんなはかない刹那(せつな)的な仕事にナンシー関は全力投球した。アイドルより賞味期限の短い過酷なジャンルで10年トップを走った奇跡。こんなコラムニスト、もう二度と現れない。
(新聞から直接入力6/15)
テレビの冥界に旅立ったナンシー関 (朝日新聞6月14日夕刊文化欄 コラムニスト・中森明夫)
鋭い批評もはや名人芸
ナンシー関さんが亡くなられた。と書いて覚えるこの奇妙な感じはどうだろう。著名人が死ぬと親しくもない人々が急に「さん」づけで呼び出すような風潮にこそ、彼女はもっとも違和感を訴えるといった人だったので、ここは慎んで<敬称略>といきたい。
ナンシー関の名前を知ったのは消しゴム版画家としてだった。有名人の似顔絵版画の隅に絶妙なひと言が添えられている(藤井フミヤの顔の脇に「おれ、セクシー?」とか。やがてテレビ評や人物評の書き手として、またたく間に売れっ子となっていった。
当初、辛口女性コラムニストブームの一人として彼女が現れた時、感想を求められた私は「景気が悪いからでしょう」と応じたものだ。おそらくナンシー関の躍進と日本経済の退潮には相関関係がある。バブル崩壊この方女性週刊誌を中心として著名人のバッシング報道が過熱化した。その根底にあったのは大衆のツッコミ衝動だと思う。テレビに出るような有名人はもはや憧れや称賛の対象ではなくなり、公然と視聴者にツッコミを入れられる存在に成り下がった。バブル景気の頃にはうまい目を見ていて転落した人々が「なんでこの不況期にアンタはテレビに出て楽しくやってるワケ?」というような。そのツッコミ先導役として辛口女性コラムニストらが大量動員されたのだ。
しかしナンシー関は明らかに彼女らと一線を画していた。まず文体に女性性のかけらもない。世代性にも縛られない。ツッコミの肝は違和感の指摘だが、ナンシーのそれは名人芸の域に達していた(例えば大橋巨泉のセミリタイアを「一年中、閉店セールをやってる家具屋」というような)。むしろ彼女の同時代のライバルはダウンタウンなどだろう。
ナンシー関とは一面識もなかったが「中森明夫は”おなべバーのママ”みたいだ」と斬(き)られて大笑いした。いつか応戦しようと「ナンシー関はヌイグルミで実は中に誰か入ってる。こないだ背中のチャックの開いたナンシーの古い皮が捨てられていた」というネタを考えていたのに、遂に御本人に披露する機会を失って残念である。
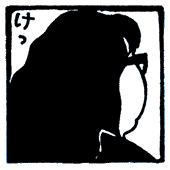 |
| 「ボン研究所」プロフィールより拝借 |
あれほどテレビにテレビについて書き続け、しかし不当にテレビに無視されつづけていたナンシーが、死ぬと(封印が解かれたように)いっせいにワイドショーで「いい人」として処理されていたのは皮肉な光景だ。私は近い将来、”ナンシー関内蔵型テレビ”が発明されるのでは?と思っている。ナンシーのお腹の部分がモニター画面でヘソの部分を押すと自動的に番組にツッコんでくれるというスグレモノだ。するとその機械は先のナンシー追悼報道をどんなに鋭くテレビ評することだろう。
テレビ局の放送終了時の告知を見ていると、この世の終わりを想う。ナンシー関は死んだのではない。日本テレビの放送終了時にコマ落としで飛んでくるモノクロの鳩に連れ去られ、テレビへの冥界(めいかい)へと旅立ったのである。何だそれ(とナンシーならツッコむところだ)。
いつも心にナンシーを 高度情報社会の「常備薬」に(毎日新聞
6月20日夕刊 文化欄 民俗学者・大月隆寛)
あのグローブみたいな、分厚いクリームパンのようなまるっこい手が、すごく器用に動くんですよ。あの消しゴム彫るのも彼女、主にカッターナイフだったはずで、それは自慢だったみたいです。「これできるの、あたしぐらいだと思いますよ、へっへっへ」と、珍しく自慢してましたもん。彫刻刀とかで彫るよりずっと難しいんだ、って。
その彼女、ナンシー関の死について、語ります。
80年代出自の価値相対主義思想の、その最良の部分が死にました。その限りでこれは、思想的事件です。ひと昔前ならば、たとえばサルトルが死に、三島が割腹し、中上健次が早世した、いずれそういう大文字の固有名詞と結びつけられて語られるべき、あるひとつの「時代」とその精神を象徴するできごとになっていたはずです。ナンシー関の死、というのは、岡崎京子の”遭難”と並んで、実にそれくらい、同時代を生きる者にとって大きな意味をはらんでいます。
テレビにもの言う、というのは、これまでも評論家達のお家芸でした。古くは、大宅壮一に始まり、藤原弘達や細川隆元など、彼ら「オヤジ」評論家が何か「もの申す」時にはテレビは常に悪玉で、「衆愚」の権化として扱われてきました。テレビはバカであり、通俗だった。ゆえに、知性や、教養の側からは当たり前に批判されるもの、でもあった。今でもそれは基本的に変わっていません。
けれども、彼女はそんなテレビを、そのバカで通俗なありようのまま、世間の多くが抱える日常の感覚の内側から眺めて語る、という離れ業をやってのけました。テレビを高みから見下ろすのでなく、バカで通俗なそのテレビと同じ空気を吸い、同じ場に生きている自分も共にひっくるめて眺める――そこに旧来の知性や教養を超えた「批評」が宿りました。
それを可能にしたのが自己相対化――つまり「ツッコミ」です。バカで通俗なテレビに敏感に反応しながら、でもそんなテレビと共に生きるワタシって何、という自己相対化も必ずしている。月並みなニヒリズムに足とられがちな価値相対主義を一歩突き抜けて、彼女のそのスタンスは、「ツッコミ」がある種透明な自己抑制に昇華し得る可能性を見せてくれていました。そしてそれこそが、この高度情報社会における最も信頼すべき「主体」のありようを示していました。だからこそ、単なる売れっ子雑誌コラムニストの死にとどまらない衝撃が各方面に深く、静かに走っているのだと思います。
ナンシー関に寄せるこの絶大な、しかしそのままで絶対に世の安定多数にはなり得ない無告の「信頼」というものを、もはや役立たずになってしまった活字出自の知性や教養ってやつは、さて、どれだけ謙虚に受け止められるか。それは正しく「政治」の問題であり、ごく普通の日本人、いまどきの「常民」に即した、気分のフォークポリティクス、とでも言うべき領域と関わってくるはずです。
「いつも心にひとりのナンシーを」――けたたましくもとりとめなく流れるばかりの、この情報化社会の真っただ中で、うっかりと舞い上がらず、不用意に自意識を肥大させてしまわず、身の丈の「自分」の立ち位置を確認し制御してゆくために、ナンシー関の残した仕事はこれからもなお、あたしたちがこの国でまっとうに生きてゆく上で欠かせない、言わば常備薬のようなものであり続けるに違いありません。
(記事にはナンシー関さんの顔写真あり(『対談するナンシー関さん』という言葉とともに 1994年=中村琢磨写す)
ナンシー関さん、薄化粧の忘れえぬ夜…青森の生んだ平成の偉人(ZAKZAK
2002/06/19)
夕刊フジ紙上で「新性紀・女優改造論」を連載中の“毛の商人”高須基仁氏。彼の交友範囲は広く、あの故・ナンシー関さん(享年39)=写真(元記事には拡大写真も)=との思い出をつづった。
 |
過日、夭折した消しゴム版画家でありコラムニストのナンシー関さんは、サッチーに肩入れする私に、「高須さん、サッチーって女性はね、“血中外国人度”の高さが、とってもすごいの。アメリカ人だと思って付き合えばいいんだよ」と、常々、伝授してくれました。以来、私は「サッチーってアメリカ人、アメリカ人…」って念じながらおつきあいを続けたんです。
だから今、サッチーの二男、ケニー野村氏が、お世話になったはずの阪神球団に“外国人選手紹介手数料の金を支払え”と、民事裁判を起こしたり、私がその夫人から出版物をめぐる民事訴求を起こされても、妙に納得しちゃうところがある。サッチーファミリーって、アメリカ的な訴訟合戦には、なりふりかまわないんだなって。
5月初旬、赤坂の中華料理店で、ナンシーと、ウオツカのオンザロックを傾けました。突然、「アナタの新妻って、芸能リポーターの横田砂選でしょう。呼んだから…」と言われ、横田は、あわててお店にかけつけて来たんです。
「横田さん、芸能界に数多く存在する“○○ファミリー”に群がる有象無象の末端構成員のようなリポーターになり下ったらダメよ!!」と、他局の高名なリポーターの実名を挙げながら、的確なアドバイスを私の妻へ送っていました。
まさしくナンシー的独立独歩、自力更生の生き方のススメでした。
そして、「悪も転じて善と成す−って言葉を知ってる?」と言いながら、ウオツカをグビリ。当たり前の「正義」をふりかざし“善”を語る人間をとても嫌う女性で、権威を嫌がった。
一方で、「運転免許を取って、新車をついに買ったの」とポツリと語る顔は、とても普通だった。その夜、薄化粧に、軽く引いたピンクの口紅が忘れられないのです。当然のことですが、新車は地味な国産車でした。
コツコツとゴム版画を削ったナンシー関の人生は、毒舌コラムとは対照的に、地味そのもの。青森の生んだ平成の偉人でした…。
(元記事へのリンク)
ナンシー関に書かれて、人は初めてテレビの住人になれたのだった
(TV Bros7/6→7/19号追悼記事内 文・豊崎由美)
新聞でテレビ評を連載しているライターの文章を読んでいて、改めてナンシー関(あえて敬称略)の偉大さについて思い知らされた。フジ系の昼メロ『真珠夫人』について書かれたそれは、スタッフの「ベタを狙ったベタ」を称賛しており、その論旨は納得のいくものだったのだが、問題は最後の一文。「横山だけでなく、ここに出演している役者は、こぞって新境地に踏み出した。面白いけど、ひとつ聞きたい。どこへ行く。」――そう、これはナンシーのエピゴーネンなのだ。
独りでツッコんで、独りでボケる。褒めているかのように見せかけて、すぐさま茶化して落とす。この文体を確立したのがナンシー関だった。私も含めて、ほとんどの凡庸なライターがそれを真似せずにはいられなかった。それほど、ナンシー関の文体は魅力的だった。
ナンシー関は見立ての達人でもあった。川島なお美主演ドラマ「失楽園」がかもす間抜けで不潔な猥雑感を、あえて落ち目気味の古谷一行にスポットを当てることで看破してみせた文章には、笑うと同時に舌を巻いたものだ。”川島なお美の乳を揉む装置”、古谷一行のこのドラマにおける立場を示して絶妙な見立てなんである。フードバトルのいやらしいパクリを指摘し、元祖の大食い選手権を擁護したのはナンシー関が一番最初だった。壊れた人間の壊れっぷりを味わうという「ヤバいもの見ちゃった」感が魅力だった大食い番組が、小林尊の出現によって、その質を変容させてしまった気配を真っ先に嗅ぎつけたのもナンシー関だった。
これからはナンシー関なしでテレビを観なくてはならない。その途方にくれてる感たるや……。訃報を伝える際、「自分について間違ったことばかり書いた」と恨みがましいことをほざいていた小倉智昭よ、ナンシー関に書かれてなんぼにすぎない己の卑小さを、彼女を失った世界で思い知れ。人は、ナンシー関に書かれて初めてテレビの住人になれる。そんなことにも気づけなかったタレントだけが、多分ナンシー関の死を言祝(ことほ)いでいる。
彫った。書いた。歌った。――ナンシー関を追悼する
(TV Bros7/6→7/19号 p20 エディター・川勝正幸)
●7月7日はナンシーさんの40回目の誕生日である。どう過ごせばいいのだろう。
●ワールドカップではしゃぎすぎな日本に機嫌が悪い。そんな噂を聞いた矢先だった。ナンシー関が急死した。早すぎる。即この言葉が浮かんだが、こんな調子の追悼では天国のナンシーからツッコミが入るだろう。ゆるいと。あり得ぬことだが、彼女が自分で墓碑銘を彫ったら、と想像してみる。「彫った。書いた。歌った」だろうか。
●ナンシーさんが筆者の消しゴム版画を彫ったことが一回だけある。’90年前後、ゴンチチの演奏会のフライヤーに原稿を書いた際、彼らのマネージャーがなぜか僕を彫るように依頼したのだ。はんこをもらい受けた時、注意書きを添えてくれた。「厚さがないので押しにくいかもしれませんが、コツは押捺面にまず置いてズレないように手の平で圧力をかけることです。手を離す時にズレないように気をつけてください。でも、ズレたりカスれたりしているのもまたはんこということですんで」最後の一行――たかがハンコ的な物言いが彼女らしい。しかし、当時からナンシー関の版画のスキルに関して僕らは巧くて当たり前と慣れっこになっていたが、この紙の前半を読んで彼女が他人に見せなかったされどはんこサイドを知り、ドキッとした。共通の友人で同病(狂剣患者=CKB
CRAZY)のO嬢によれば、「横山剣さんの顔は昔の二枚目ぽいから彫りやすいと思う」と言っていたそうだ。<いいね!はんこ>、見たかったニャー。
●筆者の遅筆が世の中に役立ったことが1度だけある。彼女と高橋洋二君と僕とで<記憶の底の有名人辞典>的な本を書く企画があったが流れ、初単行本『ナンシー関の顔面手帳』(’91)が生まれた。エクスキューズの一切ないTV/世相評論。<芸能界人>など言い得て妙な造語の連発。6歳下の彼女の目を頼りにして生きていた自分は、これから自立しなくてはならない。
●ナンシーさんからのカラオケの誘いを3回続けて断ったら、「私達と遊ぶのが嫌いなのか、カラオケが駄目なのか」と訊かれ、後者だと答えたら、「だったらいい」と許してくれた。以後会うのは、彼女が招待されていながらチケットを買って観に行くムーンライダーズのライヴ会場ぐらいとなった。
●6月16日。初青森は快晴で、常光寺には150を超える供花が風に揺れていた。ビートたけしとリリー・フランキーがカタカナ繋がりで漫才の相方のように並んでいた。黒柳徹子、楠田枝里子、水野晴郎……と<彫られても好きな人>からも多数。ナンシー関の器の大きさを改めて感じた瞬間、彼女の不在のでかさに目の前が曇った。
(注:他に文中にある川勝氏の消しゴム版画あり。「おそれいります」の言葉が添えられている。下にコメントとして「メールが普及する前は必ず原稿にこのはんこを押しファックスしていた」とある。実際の文章は改行もなく詰められていたが、適度に行を空けてタイプしました。)
ものすごいショックで落ち込んだ!フテ寝した!
(TV Bros7/6→7/19号 「私のテレビ日記」タレント・清水ミチコ)
―前略―
○月×日
「ナンシー関さんが亡くなっちゃった。」と、ある朝、水道橋博士から電話があった。ものすごいショックで、(あれ、自分はこんなに好きだったか?)と思うくらい泣けて落ち込んだ。フテ寝した。最近は年に1、2回会うって程度だったんだけど、会えばいつも話に味わいがあり、品格さえ漂わせる口調で言う冗談は、本当におもしろかった。というか、うまかったのだ。
「さ、おもしろいことを言いましょ!」というニヤニヤがなくって、淡々と、かつムダがない。って、芸人じゃあるまいし、こんな事ほめられても嬉しくないだろうけど。ま、そういう部分にほのかに尊敬もしてたんだ。ベッドから起き出して、(そういえば最後にメールのやりとりしたヤツはどんな内容だったっけ……)と思ってパソコンを開いてみたら、水野真紀さんについて、だった。な、な、泣きにくい。
ブレない人 (サンデー毎日6月30日号 「満月雑記帳」
中野翠)
―前略―
この原稿を書いている間に、知り合いの編集者から電話でナンシー関さんが亡くなったということを知らされた。
何ということだ!ただただ驚く。胸がドキドキしてしまい、しばらく仕事に戻れなかった。
ナンシー関さんとは一度だけ対談したことがあったけれど、私には苦手なジャンルのテーマだったので(皇太子と雅子さまのロイヤル・ウエディングについて、だった)、ナンシーさんに会えたのはよかったけれど、あんまりうまくしゃべれなくて、我ながらもどかしかった記憶がある。
ライターとしてのナンシー関さんの凄いところは、何と言っても動かない(文中は傍点)ところだ。世の中何が起ころうと、「私はここからここまで」と自分の世界を限定して、そこから決して動かない。動揺しない。価値基準にもブレがない。
それはみごとなものだった。根本がお調子者で、確信に欠け、何かにつけてブレがちな私とは大違い。ずうっと年下の人なのに、おうおうにして年長の賢者のように感じられた。
まぶしく、こわいライターを失ってしまった。
学生時代から才能が認められ、メディアで活躍していたとはいえ、三十九歳の急性はいかにも早すぎる。こんなことが現実にあっていいんだろうか。
ダメだ。まだ気持ちが混乱している。
「ナンシー」 (朝日文庫「秘宝耳」内解説 いとうせいこう)
ナンシーと出会ったのは80年代の前半だった。えのきどいちろうの紹介で池袋まで行き、ソファが柄入りのべっちんで覆われているようなうさんくさい喫茶店の中で、私は彼女の消しゴム版画を見た。題材は”丁稚”や桂歌丸だったようにも思うが、はっきりとは覚えていない。
むしろ、その喫茶店の感じばかりが記憶されているから、初対面の我々はどちらともなく店の作りに軽いツッコミを入れたのではないだろうか。なぜなら、その日のうちに私は仕事の依頼を決めたからで、その判断の奥には”この人のセンスは信頼できる”という確固たる第一印象が存在していたのである。
ひょっとすると、その喫茶店の名前はボンだったかもしれないと今、急に思った。のちにナンシーはボンという名の喫茶店が多いことにこだわり、自分のホームページに「ボン研究所」という名前をつけるからだし、珍しくその由来を私に熱っぽく語ったことがあるからだ。もし本当にそうならナンシーらしいとも思う。
それはともかく、当時、私は『ホットドッグプレス』に配属されたばかりの新人編集者で、「パックン・プレス」という読者投稿ページを担当していた。したがって、イラストレーターとしてのナンシーの輝かしいキャリアはそのページの小さなカットから始まったことになる。
おそらく最初の仕事の時ではないかと思うのだが、私はナンシーから「なぜか伊藤正幸」という文字が刻まれた消しゴムをもらった。横には逆立ちしている私の絵が彫ってあった。この時点で、すでにナンシーは版画の横に字を入れる例のスタイルを確立していたわけだ。以後ナンシーは依頼された仕事を編集部の中でこなした。ファックスさえないような時代だったから、少なくともライターはみな編集部に通って書いていたものだが、イラストレーターとしては異例のことだった。
原稿を見せるとナンシーは編集部の大きなテーブルに陣取り、カッターで版画を彫り始める。やがて出来上がるとスタンプ台に乗せてインクをつけ、紙にぎゅっと押しつける。つまり目の前で画伯の仕事のすべてが見られるわけで、今から思えばなんとも贅沢な入稿だった。暇な編集者はいつでもナンシーの後ろから彼女の作業を見学していたもので、
ちなみにナンシーの去った後にはいつでも少しだけ消しゴムカスが残っていた。
そのうち、同じページの小さなコラムに原稿を書いてもらうことにもなった。ライターが原稿を仕上げるのを待っていてもらうくらいなら、ナンシーがすべて受け持つ方がいいと思ったからなのだが、果たしてそれが彼女の物書きとしてのデビューかどうかは定かではない。ライター稼業の先輩、押切伸一に導かれて、早くも他の雑誌に何か書き始めていたということもあり得る。
なんにせよ私が思い出すのは、最初にナンシーから受け取った手書き原稿のことだ。中に改行は皆無だった。二百字詰めのいわゆる”ペラ”数枚にびっしりと文字が詰まっていて、読者投稿を紹介するには内容が濃すぎるほどだった。
たぶん私は、”ナンシー、少しは改行してくれよ”というようなことを笑いながら言ったのではないかと思う。のちに彼女からその時の思い出を聞いたような気もする。
ナンシーには書きたいことが山ほどあり、また改行で字数を稼ぐような書き方への激しい嫌悪もあったのだと思う。それがひしひしと伝わったからこそ私は笑いながら改行を要求したはずで、技術的な改行なんかよりナンシーの姿勢の方が圧倒的に正しいんだけど、と私は私で伝えたかったわけだ。
原稿に重心がよく乗っているという印象も鮮やかだった。短いコラムでも不器用なくらい考え抜き、やがて厳選された複数のテーマを見つけ出して書ききれなくなるのだ。
だから、ナンシーは自然と切れ味よく書いていく以外になかった。修飾語とゆるい印象の表明だけでダラダラと文を綴ることはあり得ず、凝縮したフレーズを次々とつなぎ合わせるようなやり方で原稿を作り上げたのである。
ナンシーの文体の底にある、配管工がボルトで管をつないでいくような重々しい感触は、初期の頃からすでに存在していたのだった。
そのナンシーが本格的にテレビ批評を始めたのは、デビューから数年後の87年。『スダジオボイス』誌上での「テレビの泉」という連載であった。サブタイトルには”どんな番組でもおもしろくする”と銘打たれており、初回の宣言にはこうある。
「我々はすべての番組を楽しめる!クズなプログラムを24時間流されても楽しんでみせよう!我々はテレビ鑑賞に革命を起こす黒船団なのだ!」
”我々”とは、ナンシーと押切伸一、そしてやはり「パックン・プレス」で原稿を書いていた放送作家の高橋洋二の三人である。また、宮沢章夫と私が中にコラムを持ち、しりあがり寿のイラストなども入っていた。このにぎやかな四ページ連載が、のちのナンシーの仕事を決定づける。
その後の歴史については、いつか誰かが詳細に書くだろう。私は自分が知っている、デビュー時から数年間のナンシーのことだけをここに書き記しておいた。
そしてその最期。ナンシーは眠っているとしか思えなかった。私は長い付きあいの中でナンシーの寝顔を初めて見たと思ったし、今でもそうとしか考えられない。
涙は出なかった。けれど、何日か経ってこうして彼女にまつわる文章を書いていると、急に発作のように涙が出る。書くことで少しずつ事実を受け入れているような状態で、だから本当はこんな文章を書いていたくない。今は”それ”を絶対に認めたくないのだ。
もしも本当に彼女がいなくなってしまったとするなら、我々は社会から正論を失ったということになる。無理解で愚鈍な連中は彼女を”斜め読みの名手”として誉め称えもする。だがむしろ、彼女の意見こそがいつも正論だった。それが斜め読みに見えるのは、読むほうの視線が曲っているからである。
彼女は常に現在だけを力強く斬り、ほとんど決して過去や未来に逃げることをしなかった。現在という瞬間をとらえて、その最深部を正確に把握し、例の”配管工”スタイルで濃密に書き記した。
考えてみるがいい。彼女以外の人物が書くテレビ評論はことごとくクズではないか。好き嫌いのレベルでそれこそ斜め読みをしていれば、そこそこの仕事にはなる。それだけの話だ。最初からうさんくさい人物をうさんくさいと指摘するだけで、人気者のうさんくささを摘出するような力などない。ましてや、その人がなぜ怪しいのかを全力で考え抜くような営為は皆無である。
もしも本当に彼女がいなくなってしまったとするなら、テレビ界は緩むだろう。人気者界はことごとく緩む。マスコミが祭り上げた人間が、ユルいイメージだけで我々を支配しようとする。ナンシーだけがそういうイメージと正対し、本質を言い当て続けていた。彼女は世界を映す小さな真実の鏡みたいな存在だった。我々はその鏡を失ってしまった。
当然、言論界も緩む。誰一人、ナンシーのような影響力を保ってはいないし、あの洞察力と速度を持つことがないからだ。
圧力に屈せず、自らの身辺もきれいでユーモラスで、意地悪のようでいながら大らかに優しい人が一人いなくなった。
いや、そんな人はもともとナンシーの他にはいなかった。
よくぞ言ってくれたと思うような文章に、あるいはいつでもそう思わせてくれる人物に、我々は果たしてこれから出会うことがあるだろうか。なければ世界は退屈で真っ暗闇ではないか。
ナンシーの身の上に起こった”それ”を、私はこの世界のためにも認めることが出来ない。彼女の本に触れた誰かが、やがてその粘り強い意志を引き継ぐまで、私は事態を完全には認めないだろう。
いつか池袋のあの喫茶店みたいな場所から、再びナンシーのような人が現れないとも限らない。私はそういう奇跡があり得ることの証人として、これからを生きていく。
(長文なので、本文の改行部分は行を空けました。…ナンシーさんだったら行空けすぎ!というところか。)
「ナンちゃんのこと」 (NAVI 2002年9月号「是々非々ジドウシャ巷談」
文・えのきどいちろう)
こういう原稿は書き直そうと思うと百ぺん書き直しても納得がいかないものだから、一切、書き直さない。ナンシー関が死んだんである。もう半月も経つけれど、やってられない気分になる。こんな、原稿書きたくない。何でそんな馬鹿なことが起きるのか。俺はナンちゃんに二度と逢えないのか。
ナンちゃんとは、もう数年、疎遠になっていた。最後に逢ったのは相撲の敷島の断髪式か、しりあがり寿さんのパーティか、どちらにしても言葉は交わさなかった。最近のナンちゃんは、いつ逢ってもまわりに取り巻きの女友達が何人もいて、ちょっと入ってく気持ちになれなかった。それから5、6年前に大ゲンカをしたのだ。『通販生活』の座談会の後だった。新宿のホテルだ。
当時、僕は文化放送の朝ワイドを始める直前だった。その時間枠は落語家の立川志の輔がやっていたところで、ナンちゃんはその仕事に大反対だった。
「何でえのきどさんが志の輔の後がまをやるの?」
単刀直入にそう訊かれた。
「何か狙いがあるわけ?狙いがあるんだったら、いっそ助かるんだけど、理由がわからないよ」
「いや、別に何年かラジオをやって国会議員に立候補するつもりはないよ」
「そんなこと言ってねーよ」
ナンちゃんは物凄くムキになっていた。こちらも折れるつもりはなかった。折れるも何も半年くらい準備期間をおいて、確かあと半月でスタートするくらいの時期だ。僕はラジオの現場へ飛び込んでいって、ひと暴れしてやるつもりだった。どうせやるんだから気持ちよく送り出してくれりゃいいじゃねぇかと思った。
話は平行線に終わり、僕らは別れた。後日、うちの奥さんとナンちゃんが電話でずいぶん話し込んでいたようだ。色んなとこに書いたことだが、ナンシー関の才能についてはうちの奥さんが「第一発見者」ということになっている。まだ法政大学に籍をおいて、何もしていない頃、ナンちゃんはヒマにまかせて消しゴムのハンコを彫り、それがうちの奥さん(はまだうちの奥さんになってない頃だが)の手帳に押してあった。ひと目見てこの人はプロになれると思ったもんだから、集英社でイラストレーターの決まってない仕事があったとき逢わせてもらった。逢ってみたらとんでもなく面白い人だったので、消しゴムハンコ(当時は「版画」という言いかたはしていなかった)のサンプル見本みたいなものを作り、あちこちに営業をかけてみた。同じ事務所だった押切伸一が講談社にサンプルを持ち込んで、まだ編集者だった、いとうせいこうが興味を持ってくれた。いとう君はメキメキ頭角をあらわした時期で、売り込み側としては是非、名付け親になってもらいたかった。まだ僕がいとう君と全然親しくなかった時期である。講談社に電話してペンネームについてかけ合った記憶がある。
「なにかイラストレーターっぽい名前がつけられないかなと思うんですよ」
「あぁ、そうですか」
「スージー甘金みたいなかんじでどうですかねぇ」
「ナンシーとか、そういうのですか」
あ、それ行きましょうと電話を切り上げたのだった。ナンちゃんに電話して「君はナンシー関に決った」と一方的に告げた。それから売り出す為に僕はどの連載にもナンちゃんをイラストレーターに指名し、ある程度、定着したなと思ったところで手を離した。仕掛人としての僕の最大のヒットはこの手を離したところだと思っている。自分で文章が書ける人だし、イメージが固定されると大きくなれない。
文化放送の朝ワイドに関する話は結局、うちの奥さんとも平行線に終わったようだった。ナンちゃんの言い分はこういうことのようだった。えのきどいちろうは新しい笑いを作れ。そんな落ちぶれた仕事をせずに才能を創造的に使え。主婦相手に愛想をふりまくのは60過ぎてからで沢山だ。私はえのきどにそういう人間になって欲しくない。
たぶんナンちゃんの目には僕が大層ふがいなく映っていたのだろう。僕は僕で物凄いラジオ番組を作ってやろうと燃えていたから、簡単に言うとふざけんなと思った。文化放送の仕事にはなにか予感があったのだ。ナンシー関の特徴であり凄味は軸がぶれないことだった。無名でも有名でも、金がなくても金が入っても、気力充溢でも疲れていても、構えが崩れない。アートの方向にも文学の方向にも一切、色気を出さなかった。天安門事件にも湾岸戦争にも、特別なことはしなかった。
まぁ、僕はふがいないことこの上ないとは思う。色気や欲心でふらふらしてばかりいて、構えなんていったら崩れっぱなしだ。だけど仕事に総動員で打ち込んで、そのなかで何かつかみとることがある。事実、ナンちゃんに猛反対された朝ワイドで、僕は色んな意味で成長したように思う。
すっかり疎遠になっていたけれど、僕はナンシーの仕事をずっと見ていたし、彼女のことは相当なところわかっているつもりでいた。いつか何かの連載で、もう一度、イラストをお願いするのを楽しみにしていた。
今、彼女がいなくなって、骨身にしみているのは、あいつが僕の為にムキになってくれたことである。これは感情だ。僕もナンシー関のことになるとムキになる。ふざけたことを言う奴は絶対に許せない。生涯にひとり逢うか逢わないかという、ずば抜けた才能だ。
絶望的な気分になる。
もう逢えないのかよ。
この原稿の写真ページのために引き出しを探したら、ナンちゃんが彫ってくれた「妙にえのきど」のハンコが出てきた。『ミュージックマガジン』や『DIME』で使ってたやつだ。それからうちの奥さんがオリジナルの絵ハガキセットに添えられていた走り書きを見つけた。
「つかってください。
えのきどさんによろしく。
じゃあ、またね。
せき」
すっかり疎遠になっていた頃のものだ。
悲しくて、もうこれ以上、書く気がしない。
(写真は「妙にえのきど」のハンコと上記の走り書きの一部が。脇には原版と思われる消しゴムが写っている。 写真=大石環)
車色のナンシー (NAVI 2002年9月号
「Forza! Macchina」NAVI編集長・鈴木真人 )
80年代初頭、ニューアカデミズム・ブームに随伴してアイドル批評がもてはやされたことがある。一団の若手文筆家が、”高級な”フランス現代思想を”低級な”アイドルに適用する冒険を敢行したのだ。
そのほかにも、サブカルチャーというジャンルを逆用する形で、さまざまな試みが仕掛けられた。もちろん、”高級”と”低級”を前提とした枠組みに疑念を抱かなかった思考に、実りが生まれることはなかった。今となれば、スノッブな意識が透けて見える。
それでも、どんな現象にもなんらかの収穫はあるものだ。少し後れて現れたナンシー関は、ジャンルへの差別的意識をもとから持ちあわせていなかった。サブカルチャーを扱いながら、”高級”に”低級”を対置させる発想がなかった。だから、ナンシー関の批評活動だけは、21世紀になっても輝きを失わなかった。時代の産物ではなかったのだ。彼女の思考は。
ナンシー関の人となりについては、師匠であるえのきどいちろうさんが今月号のコラムで書いてくれたはずだ。一面識もない僕があえてここで彼女のことに触れるのは、彼女の対象に対するスタンスが、僕が自動車に向かう時の道標になると思うからだ。
ナンシー関がジャーナリズムにとっていかに重要な存在だったかについて、すでに多くの人が語っている。もともとたくさんの物書きがナンシーのエッセイのスタイルを賞賛し、それどころか、才能の乏しいライターたちが真似し、剽窃した。そんな扱いを受けたのは、ナンシーのほかには東海林さだおだけだ。彼女は、新たしい文体を作った。要するにそれは、新しい思想を作ったということだ。
彼女は、少数の優れた番組と大半のくだらない番組からなるテレビを毎日のように観察し、批評し続けた。テレビが”低級”なジャンルだから高みから説教したのではない。
僕たちの住んでいる世界は本当にひどいもので、のべつ戦争は起きているし、人は飢えて死ぬ。汚職で私腹を肥やす政治家はいるし、官僚は国民の利益なんて考えちゃいない。だけど、僕たちは革命を起すでもなく、毎日をそれなりに楽しく過ごしている。
アイドル、テレビと同様に、自動車だって腐った資本主義の消費社会から生まれたものだ。正義のアイテムというわけではない。ただ、僕たちはそれを受け入れ、享受している。それを無視した言説は、力を持ち得ない。
批評の対象がどんなにどうしようもないものでも、それによって自分が支えられていることを認め、だけど手放しに肯定するのではなくて、でも無残に否定するわけでもなくて、自分にツッコミを入れる。ミーハーで、快楽主義で、機会主義で、行き当りばったりだと知っても自分を許して、でも、それはダメなんだと、わかっていて直せないんだと。情けないだらしない自分をわかって謝って、そういう過程を経なければ批評なんてあり得ない。
ナンシー関がそんなことを言ったのではないけれど、雑誌で彼女のコラムを読むたびに、僕はそんなふうに感じていた。それは、僕が自動車について文章を書くときに、戒めとして作用していた。
したり顔に、自動車の権威のように振る舞い、多くの自動車を並べて序列をつけて何かをなしたように思いこむことを、心して拒絶しなくてはならない。それは、自動車に対して最も礼を欠いた接し方だ。そこには、自動車への愛はない。打算、ないしは自己愛があるだけだ。
自動車を手放しで肯定することも、無残に否定することも、やめよう。軽やかに謹厳に、くだらなくも魅惑的なものに向き合ったナンシーの姿勢を、僕は忘れない。
(この他にテレビのリモコンらしきを持った自動車のイラストあり。イラスト=阿部真理子)
「雨の降る夜」 (CREA 8月号 リリー・フランキー)
雨の降る夜でした
六月十二日。その日は夜が明けたら、夕方にはいつものように、ナンシーさんと僕
は、このクレアの連載のために、会って対談する予定の日でした。
このナンシーさんの連載は十年前、大月隆寛さんをお相手に始まり、町山広美さん、
そして僕と続いていたものでした。
最初にこのお話をいただいた時、ナンシーさんが僕を指名してくださったと聞いて、
本当にうれしかった。それと同時に、僕でいいのだろうかと恐縮もしました。
それは、先輩方の後に名前を連ねることもそうでしたし、なにより、文筆家として、絵
描きとして、尊敬していたナンシー関さんと一緒の連載ができる、ナンシーさんに少
しでも認めてもらえたのだなという喜びでした。
それは今でもそうなのだけど、僕は文章を書いても、絵を描いても、他の仕事に手を
染めても、どこか自分はニセモノだなと自身を嫌悪しておりましたから、ナンシーさ
んにお誘いを受けて、初めて、なにか誇らしい気持ちになったのです。
以前、ナンシーさんにそんな話をしたこともありました。
僕が本を出し始めた頃、いくつかの書評で「男・ナンシー関」「ナンシー関以来」と
いうようなほめ方をしてもらったことがありました。僕は素直な性格ではないので、ほ
められることも、人に例えられることも気持ちのいいことではないのだけれど、その
ときだけはとてもうれしかったのですとナンシーさんに言うと、ナンシーさんは「そ
んなんじゃしょーがないねぇ」と笑っていました。
それからずっと、この連載を一緒にさせていただいた二年とちょっと、僕はずっとナ
ンシーさんから、この言葉を言われていた気がします。
「しょーがないねえ、リリーさんは」
いつもいつも、時間に遅刻してくる僕に、苦笑しながら言いました。
免許が取り消しになったとき、酒ばっかり飲んでて、原稿が書けないと言ったとき、
ナンシーさんの嫌いないやらしい話ばかり僕がする時、取り返しのつかないことで僕
がグズグズいう時、
「しょーがないねぇ、この人は」
笑いながら、優しい顔で言ってくれました。
カラオケの好きだったナンシーさんとカラオケに行ったとき、昔、変な別れ方をした
彼女にもう一度会いたいとか、また、バカなことをいいながら「逢いたくてしかたな
い」を絶唱していた僕に「しょーがないねぇ、この人は」と言いながら、続けて「で
も、郷ひろみよりも気持ちが入ってた。もう一回歌っていいよ」とリピートしてくれ
たり。いつも、過剰なことは言わないのだけれど、ひと言、人の楽しくなるようなこ
とを察してくれる人でした。
歌がすごく上手だったナンシーさんと「ロンリー・チャップリン」を何度も歌いまし
た。出版社の新年会とかで披露しようといいながら。でも、仕事も何事も完璧を目指
すナンシーさんでしたから「ちょっとハモリ違うんだよね。CD買って練習しよう
よ」ってナンシーさんらしいなと思いました。
ナンシーさんはよく「辛口」と評されるけれど、僕はそう思ったことはありません。
繊細な人でしたから、他人を無意味にほめることはしなかったし、また、単なる悪口
を書くような文章も読んだことがない。気の強い人ではなかったから、書かれる対象
以上の重圧を自分で受け止めて、きめ細やかに文章を綴り、消しゴムを彫っているの
だと僕は感じていました。
批評や評論とは違う、ナンシーさんだけがかたちにできる文章がありました。
それは、TVを観ている人や僕らがそれを観てモヤモヤ感じていること、なんだろう
この人は?と思っていること。
僕らが頭や心の中で、言葉や文字にできずにしていることを手に取って並べかえて,
それは、こういうことなんじゃないの?と教えてくれることでした。
あのきれいな文章で。あの版画で。
雨の降る夜。
その日、気が動転して、何が起きたのかも判断できないまま病院に駆けつけ、目を閉
じたままのナンシーさんを見た時、足が震えて涙が止まりませんでした。
そして、先月号の一番最後にナンシーさんが言ったひと言を思い出しました。
前回は占いの話をしていて、僕が来月、タロットカードを持ってきて、ナンシーさん
のことを占うと言っていたのです。それに対するナンシーさんの最後のひと言がこう
でした。
「私のことは、絶対当てさせないよ」
当たるわけないですよ、こんなこと……と思いました。
結局、ナンシーさんにはお世話になったまま、いつも良くしてもらって、何のお返し
もできずに甘えたままのかたちになってしまったことが悔やまれてなりません。
また、今月もいつものように二人で対談するはずのものが、僕ひとりで追悼文を書く
ことになるなんて思いもよらず、その現実を完全に受け止められぬまま、あの美文家
に贈る追悼文を書くということ、ナンシーさんに読まれるのだというプレッシャー
で、筆の進みも、内容も上手にいかないまま、また、ナンシーさんに「しょうがない
ねぇ」と言われそうです。
こういう風に書くと、ナンシーさんは照れて嫌がると思いますけど、尊敬していまし
た。頭が良くて、繊細で、女らしくて、本当にやさしい人でした。
ナンシーさんと一緒仕事ができたことは僕の一生の誇りです。
ナンシーさん、お疲れさまでした。
(このHPを見て頂いた、みみさんからのメールをそのまま貼りつける形で掲載しました。漢字・平仮名における若干の変換間違いがあるそうですが、全文です。
以下にこの文章以外で追悼ページにあったことをみみさん自身の文章で紹介します。
『この文章が載ったのは、3ページに渡って、で、
トップページにはリリーがナンシーに
「しょうがないねぇ、この人は・・」って怒られているイラスト
開いて2ページ分に、
傑作消しゴム版画&名言集として
12個のはんこと8個の名言が載っていて
それ以外に一番大きく載っていた名言が
2002年1月号の中の
「私は、ナンシー関で10年後も消しゴム彫ってるのかな。
ま、間違いなく彫ってるんだろうな」ってひと言。
私が好きな名言は
「車の運転中は何かけても私の勝手だから。でも車を買ったばかりの頃、
CDチェンジャーにシブがき隊を入れてあってさ(笑)勝手っつっても限度はあるね。
別に正解もないんだけど、とりあえず不正解だった。」
(2002年2月号)
です。』
みみさん、長文のタイプありがとうございました。)