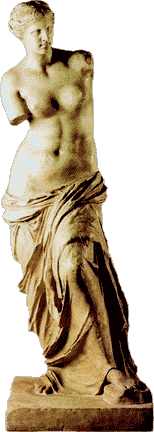| わたしとヴィーナス | |
|
私は、ミロのヴィーナスの美しさはその《欠落》部分にあると思う。腕がないからこそ、人を越えた《美》を感じる。誰であったか、本当に《美》を感じるとは「未完」を自分の心の眼によって「完成」させることが出来る感性だとか言っていた人が居た。私は自分の中で無い腕を補い完成させているわけではないが、「未完の美」というものに惹かれるのは、そこに空白の部分、遊んでいる部分があるからだと思う。だから私は《欠落》した部分を持つ彫刻に倒錯的な憧れがある。手がどうであったか考える楽しみのためではない。「無い」という非日常がそこで手招きしているからだ。 ヴィーナスは人の手を越え、神の領域に浸食する。その美しかった両手と引き換えに。 ある女流詩人はミロのヴィーナスに関して嫉妬しながらも 「汝の玉座は虹のよう 永遠のアフロディーテよ………」 と憧憬を抱かずにはいられなかったという。そのエロチシズムと理知的な健康美との融合。完璧でないからこその魅力。その「欠陥」への憧憬という複雑な問題をミロのヴィーナスは静かに提議しているといえる。いま、故意に作り出したとして、このような特殊な作品が作れようか。この「作品」は明らかに「偶然」というなの神の手によって飛翔させられているのだから。 同様のことが、サモトラケのニケについても言える。あの彫像は首までないのだから、さらに顕著に私を誘惑する。彼女は頭部が無く、両腕もない。しかし、日常では知り得ない《美》の世界へと羽ばたく翼を彼女は持っている。 余談。ヴィレンドルフのヴィーナスにも惹かれる。ミロのヴィーナスとは対照的な美しさかも知れないが、すごく愛らしいし、それでいて俗っぽくなくて素晴らしい。これこそ女体美の極致。(でも、後期のルノワールの描く、肉のたるんだ女体は苦手………。)このような作品、今の人は作れそうで作れない。 |
| ←前へ・展示館へ | |
周子の森へ |
|