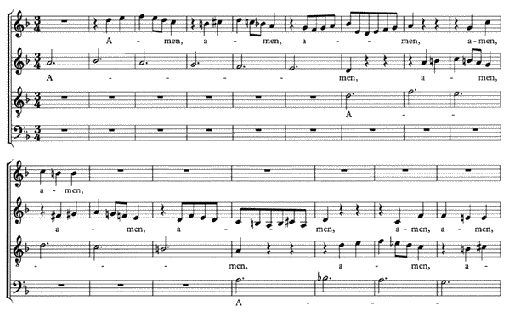| 譜例7
〈ラクリモサ〉第5-8小節の上昇、そして残る音 また、6小節と7小節では長調から短調への繊細な変容が起こっていることにも言及しておく。特に8小節目はforteとなって膨らみ、"reus"(罪ある)のテクスト的語義を強調しつつ、クラリーノとティンパニが2回(バイヤー版では3回)黄金の時を刻んで、終局をいったん迎えさせる。ぽつんと残るのは第一ヴァイオリンのオクターブ落下A音だが、荘厳から静寂の中この音だけが終局を受けて次に持続させる。終局の別の意味ではモーツァルトの筆はここで途切れているというのもある。私は、多くの伝記のように死に行くモーツァルトがコンスタンツェや弟子たち友人たちと小さなリハーサルをやって、この〈ラクリモサ〉の8小節目でモーツァルトは涙が止まらなくなり、演奏が中断されたという細やかな事実があったかないかは実際のところわからないが、やはりこれも『レクイエム』神話のひとつに数えられるものである。(註8)いわば、この8小節目で起こるのがモーツァルトの死であるから、なおいっそう聴くものは感慨深い。9小節以降の声楽と低音、(況やオーケストレーションをや)もすべてモーツァルトのものではない。この曲がたった8小節までだというのに、美しすぎるからこそ、後世のモーツァルト研究家などは、ジュスマイヤーの手に委ねたくなかった。この曲とモーツァルトへの愛情があり余るからこそ、エディションとして両方自分のものにしてしまおうと考えた。(註9)少し話がそれたが、9小節目以降を見ていこう。一旦終わったものの、第一ヴァイオリンの持続を受けて、優しく控えめに冒頭の歌詞を繰り返す。(テノールの旋律の優美さよ!)11小節目ではforteとなり歌詞は前2小節の続きなのだが、旋律が異なり、膨らみ大きくさらに優美に歌い上げるのだが、バス声部とオルガンのメロディが落下を挟んだ上昇を表しそれがなんとも言えない暗鬱な緊迫感をあらわすから、全体的に壮絶である。この旋律もまた第8小節と同じように、クラリーノとティンパニの出現によって下降し幕を引かれるが、ここでも第一ヴァイオリンのD音は残る。15小節からは"Huic
ergo parce Deus. Pie Jesu Domine,"(だからそのとき、咎あるものを憐れんで下さい、神よ。慈しみ深い主、イエスさま)ささやくように絶対神へ祈り、受肉したイエスには一層の共感を持って、情けを乞う。そこで出現してくるのは、バセットホルンとファゴットの落ち着いたメロディである。金管と違って、音色は優しく、穏やかさと慈しみに満ち、すべてを暖かく包むようだ。それを引き裂くのは、トロンボーンの音色であり、主題へとまた引き戻すのだが、冒頭ではpianoで歌われた部分が、ここではforteで"dona
eis requiem"(彼らに安息をお与え下さい)と「私」と言う表現から、また「彼ら」という確固とした客観が戻りつつある。ティンパニとクラリーノも鳴り続け、第24小節からは崩れるようにもろくはがれ落ちてゆき、ティンパニとクラリーノがひっきりなしに流れを細かく刻み、28小節で全体が上昇してゆき頂点に達する。(註10)ティンパニがトレモロを叩き出すと、声楽は渾身の力で大切に"Amen."と歌い出すが、この語の中に短調から長調への転調(解決)が鮮やかにも表れていて、そこの転調に〈ラクリモサ〉全体、いや、もはや存在しない、かつてモーツァルトだった存在の美しさすべてが投影されているようで、実に素晴らしいの一言に尽きる終結である。
ここで少しだけ、〈アーメン・フーガ〉に触れようと思う。1961年ヴォルフガング・プラートによって発見された、恐らく『レクイエム』の為に作られたであろう、16小節からなるスケッチの発見を経て、モーンダー版をはじめとして、レヴィン版、ドゥルース版がこの〈アーメン・フーガ〉を起用している。曲としては、モーンダー版を聴く限り、"Amen"という言葉が入り乱れ、確かに至上とはいわないまでも清らかで美しい。(私の不確かな直感では、モーツァルト固有の美とは言えないものの)しかし、これをモーツァルトがどのように使うつもりだったのかはわからないし、なぜジュスマイヤーがこれを使わなかったのかも謎のままである。
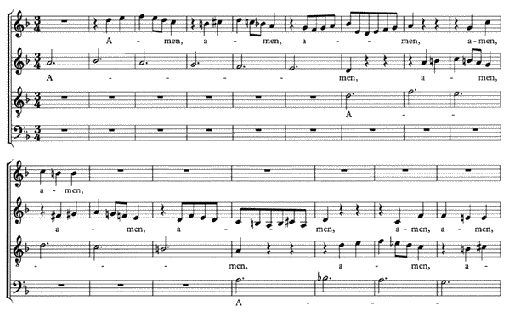
譜例8
モーンダー版〈アーメン・フーガ〉
(註8)「死の前日、午後二時のことだった。彼の周囲には、義兄フランツ・ホーファー、(私註『魔笛』での)ザラストロ役のフランツ・ゲルル、タミーノを演じたベネディクト・シャックが彼の病状を気づかって集まった。彼は身を起こして、指揮をとった。ベッドに拡げられた『レクイエム』のスコアには「ラクリモサ」の出だしが彼の手によって書き込まれてあった。彼は書きつづける前にぜひとも歌を聴きたいと望んだ。そのテーマの冒頭はあまりにも美しいので終わりまで続けずにはいられなかった。彼自身はアルトの声部を受け持った。その弱々しい声が他の声に溶け合った。
Lacrimosa dies illa………
Qua resurget ex favilla………(灰より甦える
その日こそ涙の日なり)

『the Mozart Project』より図版をお借りしました。
「だが、すでに彼は口をつぐんでいた。彼は泣いていた。いや!そうではない!彼は裁きを受けるため罪びと《homo
reus》が甦える《その涙ながらの日》をおそれはしなかった。彼は求めずして受けた天賦の才に栄誉をあたえようと、力の限り、最後のときまで努力を続けた。それを悪用したことがあったろうか?少なくとも彼は、神の定めたこのとてつもなく危険な地上において、人間に可能なかぎり純粋で、つつましく、勤勉で、誠実だったではないか?最後の諦めの瞬間に、彼は音楽に涙することを許されたのである。音楽に生まれついたように、彼は音楽に死んでゆくのだ。」(『モーツァルトとの散歩』アンリ・ゲオン著、高橋英郎訳、白水社1964 370頁)
(註9)ドゥルース版の〈ラクリモサ〉は典型的で、全く原型をとどめていないが、一聴するだけで、作曲者のこの曲への思い入れ、その人なりの美学が窺える。モーンダー版も、敢えてモーツァルト真筆の8小節分を生かすために、残りのジュスマイヤーの補筆を取り去って、モーツァルトの筆が輝くようにした。その際、〈アーメン・フーガ〉につながるまでの部分をモーンダーは〈イントロイトゥス〉再現部とみなし"te
decet hymnus,"の旋律を再現している。
(註10)28小節目の第一バイオリンの最後の重要な旋律は、ジュスマイヤー版がD‐Cであるのに対し、バイヤー版は♯C‐Dとなっていて興味深い。バイヤー版は上り詰める感じであるが、旋律的にちょっと異色でどぎつい感じもする。多くのエディションが実際ジュスマイヤー版を再評価させているという海老沢敏氏の意見は頷けるものでもある。(『モーツァルト全集9』著 海老沢敏他 小学館、1992 63頁)
|