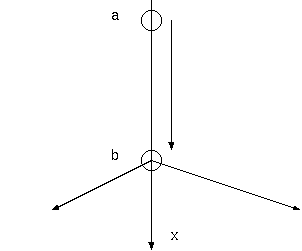
目次
1. 回転系
1.0 ニュートン力学での回転系
1.1 回転をさせるのではなく、すでに回転している
1.2 回転系の時空
1.3 Sagnac 効果
2. 加速系
2.1 一様重力系と加速系とは、原理的に区別できない
2.2 加速系の光速は、より正確に解くことができる
2.3 特殊相対論を使って空間短縮を導く
2.4 議論
2.5 光速一定の放棄は何によるのか
ニュートン力学では回転系は、遠心力とコリオリの力で説明される。その系の中で回転は知ることができる。静止物体は、軸からの距離 による遠心力をうけ、速度をもった運動物体は、その点の速度と系の回転との外積のコリオリの力を受ける。遠心力は、半径と角速度の 2 乗に比例する加速度 rw^2 であり、コリオリの力は、速度と角速度の外積 v x w に比例する加速度、両者の式が違うからその特性は、 一見違うようにみえる。しかしよくみると、両者は、同じ力を分解しているだけである。 遠心力とコリオリの力 また、太陽地球系のような地球軌道に同期する回転系での平衡点に ラグランジュ点と言われるものがある。
特殊相対論では、回転系では円周方向の速度が光速になる距離の宇宙の半径ができ、それに近づけば宇宙の周囲は、無限に延びる必要がある。 回転系は、アインシュタインが一般相対論へ進むのに重要なステップをなす思考実験であった。回転系では、周辺空間の幾何学が違ってくる。 回転系の各点は、半径方向には速度をもたず、円周方向に速度をもつ。そのため円周方向にローレンツ短縮があり、回転系の上の円周方向に おいた物差しは慣性系からみて短縮し、半径方向には短縮しない。外(慣性系)から見た円形の形が保存するので、円周は半径の円周率倍でなく、 それより長い。回転系の半径と周囲の比率は、よく間違われる。これは、コズミックストリングの線状の質量の重力による円周の削減とは逆である。
アインシュタインの"The Meaning of Relativity"(英語版) では "The General Theory of Relativity" の章の始めの方に円周と直径の関係を U/D>π と明記しているのに、その矢野健太郎の訳、"相対論の意味" (岩波書店)では、U/D≠π と改ざんされている。アインシュタインの 最高に良い本なのに残念である。また、後藤憲一の"相対論"(共立全書)では、その29章"一様に回転する座標系"では、 "円周と半径の比は、 2π/√(1-r^2w^2/c^2)<2πとなり、2πより小さくなる。"と誤っている。立派な内容の本なのにこの部分は台無しである。また、今枝国之助、 今枝真理の"ブラックホール物理学" ブルーバックス(講談社)も同じ誤りをしている。一般向けの本でも、M・ボルンの本や、 ランダウ・ジューコフの本では、もちろん間違っていない。
物理とは、時代による変化のない対象をあつかう分野である。それゆえに後生に誤りが分かりやすく、指摘を受けやすい分野である。 気を付けなければならない。流行や風俗や技術の分野では少々の誤りも何十年も経って後の世から指摘されることは決してないだろう。 物理は、時代が変わっても同じことを繰り返し考え尽くす。自らの思考形成に大いに役立ち、有り難かった本に対してさえ、余計な批判を してしまうのはそのためである。
考え方を変え、これから円盤を回転させるのではなくて、すでに円盤は回転しているとする。それより良いのは、回転している台の上で 円を描くことである。コンパスか紐かで、回転台の上で円を描く。この円は、回転系の外の静止系から見ても、やはり円形である。 しかし、回転台の上で円周にそって置かれた物差しは短縮し、半径方向に置いた物差しは短縮しない。こうすれば回転系では円周直径比 が円周率より大きいと理解できる。
座標系が回転するとは、(x,y,z)と(x',y',z')とが座標軸の z と z' を共通にして、x'軸とy'軸が、x,y 平面上を回転するだけである。 そこには、硬い床でなく変形可能な軟らかい床を考え、さらに床さえないほうがよい。z' 軸からの距離と回転の角速度とによって存在する、 その点の接線速度がある限界、光速に近付くと、円周方向のローレンツ短縮は、どこまでも短縮の度合を進める。限界距離では、 回転と逆方向に移動する物体は存在を許されるが、静止物体が存在できない。そのように、回転系は、有限半径 (r< c/w) のその果てに 無限の周囲を抱える世界である。そこは、球状の星ぼしが薄い円盤となって放射状のフロッピーケースにように詰め込まれた世界である。
速度をもった系の物差しが他の系からどう見えるかという特殊相対論によって考えると、(中心が静止した)回転系を静止系からみた幾何学は、 半径 r の場所にある微小な 3 方向の物差し (dr, dl, dz) は、r に垂直な円周方向の速度 v= w x r によって 1/γ= √(1-r^2w^2) 倍のローレンツ短縮とγ倍の時計の遅れを受ける。(γ= 1/√(1- v^2) ≧ 1) 角速度 w をもつ回転系の半径 r の場所の時空は、 円周方向に短縮し時計の遅れがある。
ds^2 = g_rr dr^2 + g_ll dl^2 + g_zz dz^2 + g_tt dt^2
において、g_ll と g_tt とが短縮や時計の係数を表す必要から影響を受ける。半径(r)方向と軸(z)方向とは回転による影響がなく、 g_rr = g_zz = 1 であるが、l 方向の係数 g_ll がγ^2 になる。時計の遅れは、時間係数 g_tt が -1 から変化しその絶対値が (1/γ)^2 倍に小さくなる。
ds^2 = dr^2 + 1/(1 - r^2 w^2) dl^2 + dz^2 - (1 - r^2 w^2) dt^2
特殊相対論では、動く系は、その前方の同時刻を未来にするので、回転系では静止点同士の時計の合わせ方に問題がでる。 光をやりとりし、系内の点どうしが同時刻を使って、任意の閉曲線で時計合わせをすると、一順すると同じ場所の違う時刻になる。 同時刻は、螺旋を描いて閉じない。そのため、円周上で同時刻に止まろうしても、無限の過去から合意しないとできない。
同じ半径の円周上の点の時間経過は等しいから、a 点から光を送り、b 点で反射して a 点に戻す、b 点で反射した時刻と同時刻なのは、 a 点の送受の中央の時刻として時計合わせをする。同じ半径の円周上進行方向に a から b とすると、a と同時刻は、b の(静止系から みた) 未来である。これは進行方向に a, b, c, d ...と並んでいても、その方向に未来が同時刻になる。ところがこれは、円周上で一巡 できる。...の後に a がもう一度出てくるとき a 点の同時刻は a 点自身の未来になる。これは、同時刻という意味の破壊であり、局所 因果性を壊して時間が周期的になるわけではないが、同時刻=空間が大局的に何かまずいことになっているのである。
回転の存在は普遍的で、地球、太陽系、銀河系も全て回転物体であるが、宇宙自体の回転は、星ぼしの見え方が異様になるはずであり、 現実の宇宙は、全体として回転をしていないとされる。回転円盤のどの点もその点での回転が等しく存在するから、回転宇宙は、 どの場所も回転の中心とする一様性をもつが、軸方向が特別であるから等方ではないのか。いや、軸の位置からの距離によるから 一様でもないだろう。
アインシュタインのいたプリンストン高等研究所にともにいた数学者、論理学の完全性と自然数を含む命題の不完全性定理で有名な ゲーデルによる、一般相対論のゲーデルの回転宇宙解(1949)があり、一順する時間軸ができてしまうという。マッハの原理からは、 宇宙全体の物質がすべてある軸のもとに回転している宇宙というのは、静止宇宙と同じである必要があるのではないか。そうでないなら マッハの原理は、一般相対論に保たれていないことになる。
一様な重力が、加速度系と原理的に区別できないとする。高いところの光源からの光は、低いところに達するまでに系が速度を増しているため エネルギーを獲得する。そのため、上方からの光は青方偏移する。連続的にこれが起こるためには、ばかげたことに重力場では時間の経過速度 が場所によって異なるという必要がある。局所点の時間の経過速度は、その点の光速と同一視できる。場所による光速の違いは、屈折率の違い のように、重力による光の湾曲をもたらすと予想した。そして太陽の側の光線の折れ曲がりを計算し、その後の一般相対論のもたらす、 重力による光の折れ曲がりの 1/2 の折れ曲がりを導びいた。時間経過は、実に物体の存在する場所の物体にエネルギーを与える場、 重力のポテンシャルに直接に関係するものであった。
重力のポテンシャルが、時間の経過と、光速というスカラーによって表されるこの単純な理論は、どこで失敗したのか、どうして重力理論は、 一般座標変換というとんでもない数学を持ち出さなくてはならなかったのか、このことは、ほとんど説明されない。そして理解が難しい。 この初期の論文は、ナイーブな物理的な思考方法のお手本と考えられるほどに、物理的な常識を壊して行く。時間経過の速さが場所の関数である。
重力でなく重力ポテンシャルがその時空点の時間経過の速さを決める。重力は、より実在的な重力ポテンシャルの勾配でしかない。地球の中に 穴を掘れば、穴の中では次第に重力は減少していくが、ポテンシャルは低下し続け、地球の中心では重力がなく、ポテンシャルでは最低点、 時間経過の最遅点である。未来の超高密度物質で作った球殻内には重力がないが、低い重力ポテンシャルが時間経過を遅らせる。 SF の時間停滞場(ステイシスフィールド)というのは重力ポテンシャルだけによって可能なのである。
もし重力が時空のテンソル理論でなく、より理解の容易な電磁気のような 3 次元ベクトル解析で表されるものであったら、どれだけ楽だった ことかと考える。一様等方の解が宇宙論であり、球対称場の解がブラックホール解である。そういう最も容易な条件における数種類の解しか 存在していない一般相対論は、十分にこなされた理論とは、私には思われない。電磁気での遅延ポテンシャルを扱うようなニュートン力学と 一般相対論の橋渡しの近似的解が欲しい。この初期の論文は、その問いに答えているかもしれない。
重力はすべての物体、物質に等しい加速度を与える。ニュートン力学は、重力を加速度で表現する。z のマイナス方向に g の 重力加速度をもつ静止系と z 方向に加速度 g をもつ加速系とは、ニュートン力学的に同一である。アインシュタインは、これ を一歩押し進め、一様な重力の静止系 K が重力のない加速系 K' と "原理的に" 区別できないと仮定する。この同一性の厳密 な要求は、時空間の考え方の枠組を壊す結論をも辞さない。その仮定は、絶対速度を否定した特殊相対論と同様に、絶対加速度 を否定する理論になるという。
高所からの光は、低地に達するまでに系が速度を増してエネルギーを獲得するため、上方からの光は青方偏移する。高さ h だけ違う 上の a 点から下の b 点に光を投げるとき、これを加速系に置き換えると、a 点から b 点まで光が飛ぶ間に、b 点が光が来る z 方向 に速度をもつため、ドップラー効果によって b で受ける光は、青方偏移する。逆に b 点から a 点に光が飛ぶときその間に a 点が 光から逃げる方向に速度をもつため a 点で受ける光は、赤方偏移する。
持続的にこれが起こるためには、"表面的には、ばかげたことだが"、重力場では時間の経過速度が場所によって異なる必要がある。 時間経過の速度の差は、重力加速度 g と高さ h の積 gh 重力ポテンシャル差によって生ずる。局所の時間の経過速度の遅れは、 光速の低下をもたらす。光速の違いは、屈折率の違いのように重力による光の弯曲をもたらす。太陽の側を通る光の重力弯曲を計算し、 0.83 秒角を出す。それは、その後の一般相対論の導いた、重力による光の折れ曲がりの 1/2 であった。
時間経過は、実に重力ポテンシャルに直接に関係するものであった。重力は、より実在的な重力ポテンシャルの勾配でしかなかった。 重力でなく重力ポテンシャルがその時空点の時間経過を決める。直接測定できる物理量でないとされてきた重力ポテンシャルに 時間経過が比例するという結論には驚きを禁じ得ない。
ニュートン力学では重力ポテンシャルφは、全体としてある一定値シフトしても物理的にはなんら影響を受けない仮想的な量であった。 ポテンシャルはその差にしか意味がなかった。ところが、時間経過が (1 + φ/c^2) に比例するという結論は、φの大きさを直接使う。 例えば、φに -c^2 以下を与えると、時間経過が 0 以下になり、物理的に許されないようにみえるが、それはいま、ブラックホールの 事象の地平面を表すと解釈できる。彼は、その考察を 1 次近似と明言している。その式は、ポテンシャルの微少変化の範囲の式であるが、 以下の考察は、彼がより精密な結果を考察して、そのままこの理論から一般相対論まで発展させてもよかったように思えるのである。
普通にはこのスカラーのポテンシャル理論は、失敗した理論であるとされ 10次元の計量 g_ik に置き換えた理論にしない限り、解決し 得なかったと理解されているが、この理論で彼が行った考え方の変化は、(1)時間経過が時空の関数である、そして(2)光速が時空の関数 であることを明確に示したことである。その両者ともに、一般相対論の原理として採用されてきた考え方である。この理論は、 一様な重力をもつ系を加速系に置き換えることで、ニュートン力学の道具だけから上の 2 つの結論を導いたのであるが、 この重力系=加速系という原理に対して特殊相対論を導入することで、さらにもう一歩、先に進むことができるのである。
ν/ν0= 1 + v/c = 1 + gh/c^2 (1)
光速 c は、時間経過に合わせて、場所によって異なる。φ= gh とすると、
c= c0 ( 1 + φ/c^2 ) (2)
アインシュタインの論文では式(3)としてある、この(2)式は、一種異様である。ひとつの式の中に 4 つの光速がある。φを割る分母に光速が 2 つあり、ab 間の通過時間 h/c の分母の光速とドプラーシフトの比率 v/c の分母の光速とである。c0 という不明な光速と、最後に計算結果 の光速 c がある。分母の 2 個の c は、結果の c と一致しない。(φ= 0 か c = ∞でないと c = c0 ではない。) ポテンシャルは質量当たり のエネルギーであるから、右辺の分母側の c^2 は、ポテンシャルの次元合わせのためかもしれない。
しかし、光速がその場所のポテンシャルの関数であることをこの (2) 式ほど明確に示すものはない。特殊相対論の光源の速度に依らない光速、 座標系によらない光速から、光速に対する考え方が大きく変わったのである。(2) 式によれば、光速は、場所によるポテンシャル φ(x) に比例 して低下し、ある低さ φ(x)= -c^2 になると光速が 0 になる。それを超すと光速が負になる。
この式につけたアインシュタインのコメントは、"光速一定の原理は、この理論に従っても、通常の相対論の基礎をなす形式とは異なる形式でよく 保たれているのである。" という不思議なものであった。そのことは、とても文章どうり受け取ることはできない。特殊相対論の最も不変な 時空の特性であった光速が場所 (と時間)の関数でしかないとき、光速一定の原理は、徹底的に解消されたというべきことである。この式の基本的 な重要性から次の考察を行った。1 次近似でなく、a 点から b 点まで光が到達する間の光速も、結果の光速と一致させて微分方程式によって 解くことができる。すなわち、
最初から高さによって光速が違うという考え方による計算をすれば、一様な重力下の光速は、(2) 式よりも正確に解くことができるのである。 下方向を x の正として a から b への到達時間 T は、1/c(x) を a から b まで空間で積分(線積分)した T= ∫_a ^b dx/c(x)、である。 b 点での速度を v= gT とすると、ドップラー効果は、v/c0= g/c0∫dx/c(x) であり、光速を c(x)= c0 - v = c0 - g∫dx/c(x) とすると、 この両辺を微分した微分方程式 c'(x)= -g/c(x) は、変数分離し c(x)c'(x)= -g、c(0)= c0 として、
c^2(x)= c0^2 - 2gx
φ= -gh とすると、
c(x)= c0√(1 + 2φ/c^2) (3)
式 (3) は、ドップラー効果には 1 次近似が使われているが、途中の光速の変化に対応したことによって (2)よりも精度の高い式である。 (2) は、(3) の φ≪ c^2 における 1 次近似である。(3) によると、一様な重力の下の光速は、x により、その 2 乗がポテンシャルに比例して低下し、 ある低さφ(x)= -c^2/2 で光速が 0 になる。それを超すと光速が虚数になる。特異になる低さが式 (2) とは異なってその 1/2 であること、 特異な面より下では光速が負ではなく虚数であることが異なっている。しかし、どこまでも続く一様な重力というのは物理的にありえないから、 この結果も不思議ではないだけでなく、加速系=一様重力系では、下方のある距離に地平面ができ、光速が 0 とか虚数になる事象の地平面より 下の現象は、永遠にこの場所に影響することがないことと解釈できる。上方の時間経過と光速は (その 2 乗が距離に比例してだが)、 どこまでも大きくなる。加速系の描写は、特殊相対論の双子のパラドックスの弟が遠方でロケットを反転するとき、地球時間が急速に経過する 情景と類似している。双子のパラドックスでは、加速度と距離に比例した時間経過速度だったので、少し違うが。
c(r)= c0 - v = c0 - GM/r^2∫dr/c(r)
a 〜 b の積分範囲は r の向きと逆だから微分方程式、
c(r)'= GM/(r^2 c(r)) - (GM/r^2)'∫dr/c(r)
を得る。第 2 項を小さいとして無視するなら、(3) の導出と同様に変数分離し c(r)c(r)'dc = GMdr/r^2 から c(r)^2= -2GM/r + const、 r→∞で、c→c0 をいれ、c^2(r)= c0^2 - 2GM/r から、
c(r)= c0√(1 - 2GM/rc0^2) (4)
この式は、(3) にニュートンポテンシャル φ(r)= -GM/r をいれたものと一致する。一様重力の場合と同じく光速 c(r) の 2 乗がポテンシャル の 2 倍に関係して低下し、ある半径で光速が 0 になり、それより内側で光速が虚数になる。一般相対論とこの結果とは、地平面の存在とその半径は、 等しいが、光速は、一般相対論のシュワルツシルツ解の光速、
dr/dt= c0(1- 2GM/rc^2) (5)
と比べるとその変化の影響は 1/2 乗である。この論文の考察には、何が欠落していたのか、時間の計量 g_00= (1-2GM/c^2r) は、 この論文で時間経過としてあるが、半径 r 方向の空間計量 g_11= 1/(1-2GM/c^2r) がなかった。光速 (ds=0 を与えたときの dx/dt) は、 √(-時間計量/空間計量) = √(-g_00/g_11) であるから、時間計量だけでは 1/2 乗しか反映しないのである。 この論文の考察に欠落していたものは何か、それは、驚くべきことに特殊相対論である。次項では特殊相対論が正確な重力による空間短縮を 導くことを示す。
アインシュタインのこの論文の以降の計算を簡単に説明を追加しておくと、光速を半径の関数 c(r) として求めたあと、この c(r) で太陽の 側を通過する光線の曲りを計算した。原点を太陽、光経路(y 軸に平行な直線)と太陽との距離を d とし、光線の曲りは、波面中の光速の 傾きの経路上の線積分であるから、光経路上の点の太陽からの距離を r とし光速の r 方向の微分 dc(r)/dr の x 成分を経路にそって積分する。 ∫(dc(r)/dr)cosθds であるが、この論文では、dc/dr = (1/c^2) dφ/dr であり、光速の r 方向の微分は重力と同じ式になり、 その x 方向成分の積分となる。s = r sinθ= d tanθ から ds = d/cos^2θ を使って、距離の2乗に反比例と、 cosθと線分s 方向の 線積分のビオサバールの式と同じ形の定積分になり、∫(kM/r^2) cosθds を sでは -∞〜∞、θでは -π/2〜π/2で定積分する。 ∫(kM/r^2) cosθds = kM∫dθ/r = (kM/d)∫cosθdθ= (kM/d)[sinθ] = 2kM/d
1/γ= √(1 - v^2/c^2)= √(1 - 2GM/rc^2) (5-1)
であり、一般相対論のシュワルツシルト解の無限遠からみた重力による半径方向の短縮比率と一致する。
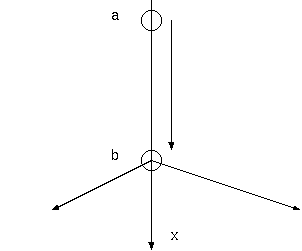
重力場のある静止系を加速系に置き換える。加速系上に静止点 a, b 点があり、a 点を離れた物体が b 点に到達するまで、b 点が加速する。 重力加速度中の落体の加速が系の加速に置き換わり、a 点で離れた物体の慣性系がみる加速系の x 位置の速度 v(x) は、前項の計算と同様に v(x)= gT = g∫_a^b dx/v(x) を x で微分して、v(x)'= g/v(x) の微分方程式を変数分離して、v{x)v(x)'= g、 v{x)^2 = 2gx、 v(x)^2 = v0^2 + 2gx = v0^2 - 2φとなり、ニュートン力学の -PE が KE に加算される式になる。この速度のローレンツ短縮は、v0= 0 とすると、
1/γ= √(1 - (v/c)^2) = √(1 + 2φ/c^2) (6)
であり、光の ab 間通過時間の系の加速による速度のドップラー効果からくる光速の低下 (3) と等しい。それは、なぜか。
重力場の物体の落下を、加速系での物体の放出に置き換え、自由落下物体の慣性系から見て加速系上の静止物体にローレンツ短縮と時計の遅れがある。 特殊相対論の時計の遅れとローレンツ短縮とは逆数で、時計の遅れが γ倍のときローレンツ短縮比率 1/γである。(3) の光速の低下は、 時計の遅れの逆数である。それゆえ、ローレンツ短縮比率と等しい。光の落下のドップラー効果による時計の遅れが、自由落下速度による 特殊相対論の時計の遅れと等しいのは、加速系の時間経過という同一の物理現象だからである。結果が違ってはいけない。
しかしそれは、十分な説明ではない。同じ現象でも違う考え方で解くと違う式をもたらすものである。式が同一となるには理由がある。 重力のある系でも加速系でも、静止した 2 点間で、光と物体とをやりとりするとき、両者の時間経過の比が存在し一致する。その理由は、 c^2 と v^2 がともに上下の ab 間のポテンシャル差 2gx を持つからか。γが速度による質量エネルギーの増加率であることだろうか。
光の落下によるドップラー効果で場所による時計の遅れを説明したことは、物体の自由落下の速度で説明することもできたわけであり、 アインシュタインがこの論文で使わなかった特殊相対論だけを使ってすむ話だった。しかも、特殊相対論では、時計の遅れとローレンツ短縮は、 常にペアで表れる現象であるから、もし、アインシュタインが彼の特殊相対論をこの問題に使う気になっていれば、 当然、もう片方の空間短縮にも着目せざるを得なかったものであろう。
1/γ= √(1 - 2GM/rc^2) (7)
であり、これは、無限遠から見たシュワルツシルト解の半径方向の空間短縮と等しい。時計の遅れは、その逆数 γ= 1/√(1 - 2GM/rc^2) である。光速は空間/時間であり、短縮と時計の遅れの両者から、
c(x)= c0 (1 - 2GM/rc^2) (8)
一様な重力は、加速系と原理的に区別できないとして、加速系上の静止点の速度による特殊相対論のローレンツ短縮と時計の遅れから シュワルツシルト解の空間短縮と時計の遅れそして光速を導くことができたようだ。
空間短縮を物体の慣性系からみて速度を獲得した加速系上点のローレンツ短縮で説明できるのは、重力=加速系仮定を使用した結果であり、 逆に加速系上のその位置からみれば、自由落下物体側のローレンツ短縮も同等に相対的に起きる。互いに相手の短縮をみるのは加速系上点と 落下物体との間の特殊相対性である。上述の (5-1) の偶然にみえた合致、一般相対論の重力短縮が自由落下物体のローレンツ短縮と一致する ことは、重力=加速系仮定と特殊相対性で説明される。
このアインシュタインの初期論文の光速が時計の遅れと同じであるために、光速が一般相対論におけるそれの 1/2 乗であることは、 空間の重力による短縮、空間短縮を考慮しなかったためである。光速はスカラーではなく、空間計量が方向によって異なるような空間異方性 があると方向によって速度が違ってくるのである。例えば、質点の側の計量は、半径方向に大きくなり、それに垂直な方向は変化しないため、 光速は半径方向と球面内の方向とで違ってくる。この論文に問題があるとすれば、空間の異方性を考慮しなかった点にあるのであり、 "一様な重力の静止系と重力のない加速系とが原理的に区別できない" という仮定が間違いだったわけではないと思う。
質点の側の時空の光景を描くことができる。質点近くの観測者は、半径方向の距離が長いと見る。遠方の静止した観測者からは、逆に質点の 側の物体が平坦化、薄膜化してみえる。ブラックホールに物体は落下して最後は凍結して永遠に停止する際に、後から落ちる物体が前の物体に ぶつからない理由がそこにある。薄くなって降り積もり、後からの分を受け入れるのである。自由落下物体と重力に踏ん張る物体とは、等しい 比率で平坦化しているという、一般相対論の質点の側の時空の光景が初等的に再現される。
(1) 加速系でのドップラー効果は、相対速度から発生するものであるが、重力による赤方(青方)変移は、速度差がない。重力を含む系で速度を獲得 するのは、系ではなくその中の物体である。重力系を、加速系に全く区別できないとする仮定は、この間の類似性を原理的合同性に格上げする ことで、重力系の時空記述を試みている。
加速系での速度差のドップラー効果が重力系に置換されたとき、時間経過の違いを系内点に持ち込んだ。時間経過が場所によって異なるならば、 静止点間でドップラー効果と同じ現象が観察される。時間経過比率がドップラー効果比率であることは、静止点間であるから継続的にドップラー 効果を得るため正しい。その比は、 v1 を光が通過する時間の加速による速度として 1 + v1/c である。
それに対し、光でなく物体の自由落下での時計の遅れは、物体の位置する場所のポテンシャルの変化である。その終端速度の特殊相対論的な 時計の遅れが最初のドップラー効果による時計の遅れと一致するのは偶然なのかという疑問がある。後者の時計の遅れは、慣性系からみた 加速系上の物体の時間経過である。式からは、一致する理由がないかにみえる。 v2 を自由落下中の加速による速度として、時計の遅れは、 γ= 1/√(1- (v2/c)^2) であり、v2 は、上記の v1 よりはるかに大きい別の値である(v2 ≫ v1)。
(2)慣性系からみると光速は場所によって変化しないが、加速系では光速が場所に依存するとして、その場所の光速を c(x)= c0 + v(x) とした。 加速系の光速を露わに使った。とくに光速に見る側の速度を加算すること、c(x)= c0 + v(x) は、乱暴である。重力があるとき光速が変化し、 時間の経過も変化すると考えるのに対して、慣性系からみたときは、光速が変化しない代わりに、空間短縮で説明することはよい方法だろうか。
(3)加速系で、場所によって光速が異なることを使うときの光速と、結果の光速が異なっていること。ab 間を光が通過する間にb が速度をもつ。 v= gT = g∫_a^b dx/c(x) を微分した、微分方程式 c'(x)= v'(x)= -g/c(x) が満たすのは、c(x)= c0√(1 + 2φ/c^2) これが加速系の空間短縮 を考慮しない時間経過に比例した光速であり、重力系の遠方から見た光速とは異なっていた。空間短縮と時間短縮の両者を考慮して正しい光速 を出すことができたように見える。しかし、自然が種々の光速を使い分けることはない。さらに式は統一的に扱われるべきである。
加速系を a 点で物体が離れた時点から t 秒後 a 点での並進慣性系 (x',y',z',t') からみると、加速系 (x,y,z,t) の静止点のもつ速度 v= gt による局所ローレンツ変換は、 dx'= γ(dx - v/c dt), dt'= γ(dt - v/c dx), 1/γ = √(1-(v/c)^2) 加速系の物差しの目盛の短縮 dx'/dx は、dt'= 0 をいれて dx'/dx = 1/γ、時計の遅れは、dx= 0 をいれて dt'/dt =γである。 これが、φ= -1/2 c^2 (g_{4,4}+1), g_{4,4}= -1 - 2φ/c^2 にまでどう継るのか不明である。
(4) 最後に完全な否定。重力による計量とローレンツ変換の関係をより明確に扱うべきである。任意の計量は、座標系を選択すれば空間的な 異方性と時間経過になる。一般変換は、速度をもった局所のローレンツ変換に空間異方性を、後から掛けて遠方からみることであるなら、 局所の計量をその局所で知ることはできない。重力による空間圧縮を局所ですれ違う慣性系のローレンツ短縮で説明することは無理ではないか。
(5) 加速系と重力をもつ系は、例えば慣性系からみたとき、加速系が速度を増して動き、重力系は静止しているという違いは明らかである。 1 g の加速系は、1 年もすると宇宙の果てを目指して光速に近い速度で進んでいるのに、1 g の重力系はそうではなく、地上に止まっている。 両者が同一であるはずはない。これは、どこか間違った議論だろう。加速系においても加速系の系内の点は静止している。系内の静止点は、 互いの速度をもたないのに加速の方向に一方的なドップラー効果をもつ。そのことについて、加速系と重力系で同一というのである。
加速系と重力系を同一とするのは系内の現象についてであり、系外の遠方からの光や物体の現象は別ということである。加速系では星々は後方 から横に回り込んで進行方向の前方に集合し、星々の見え方が違ってくる(光行差)が、重力系ではそういうことはない。少なくとも定常である。 両者の同一性は、系内現象に限定されるだろう。また、加速系を側でみる慣性系は存在するが、一様な重力の系が存在し得ないから重力系の側 には微小な局所慣性系しか存在しない。両者の(局所) 慣性系、静止点から離した物体が同じ振舞をすると仮定し、そして、その局所慣性系から みた両者の系も同じと仮定することも問題なさそうである。遠方の星々からみた両者の系は、遠方の星からの光が違って見えるように違うだろう。 局所慣性系と遠方の慣性系の違いである。
加速の方向が x のとき、時刻 0 で a 点から離れた(局所)慣性系からみた加速系の速度は gt であるが、その各点が速度をもつために、ローレンツ 短縮や、時計の遅れがでる。a 点からの距離 x = 1/2 gt^2 の√に速度が比例する。a 点からの時刻 t は、それに比例するからである。
速度の 2 乗は、エネルギーの単位であり、加速系の各点の加速方向の距離とエネルギーが比例する。後方にエネルギー 0 の距離ができ、前方は どこまでもエネルギーが延びるという非対称の構造ができるのは、このエネルギーに関係している。
問題は、加速系の距離がローレンツ短縮を考慮された距離だろうかということである。 a 点を離れてからの時間 T は、慣性系上の時計であり、 相手側の静止した一個の時計は、時計の遅れを起こすが、原点が速度 v= gT ですれ違う相手の場所の累積時間 T' は a 点を離れてから多くの 時間を経過している。 (T'>T) 向かい側の場所の a 点からの累積距離 X' は、ローレンツ短縮のために系内距離は大きい。 (X' > X)
なぜなら、局所ローレンツ変換、
dx'= γ(dx - v dt),
dt'= γ(dt - v dx)
に dx= 0 をいれ、 dx'= -γv dt, dt'= γdt から、
T'= ∫dt'= ∫γv dt、
X'= ∫dx'= ∫γdt。
γ倍を微分時間と微分距離に掛けて、すれ違う加速系の点の距離と時間経過は、その積分である。
上空で、1 m の水平方向の往復に 1 秒かかる光速をストップウオッチで測定しているとする。ストップウオッチの針がある位置に来 たとき光が到着する。地上と上空で時間経過が違い、そのストップウオッチの針の周り方が地上からみて 2 倍速く、その時計は、 0.5 秒でその回転をするとする。そのとき、そのストップウオッチの針がある角度になって光が到着することが地上からみても同じ とすると、0.5 秒で 1 m を往復するように、上空の光速が 2 倍速くないといけない。
もし、光速だけが場所に依らず地上でも上空でも一定とすると、ストップウオッチの針の位置と光の到着が違わなければならない。 そしてそれは、上空の局所事象を変えることになる。つまり、上空での時間計測が 2 秒に変わらなければならないが、それは 1 秒 であった。この局所事象、局所計測は、どう遠方から眺めても、相対論がそれを変えることができないこととするのである。 (1 m の距離が変ればそれは光速に影響するが、一様な重力では水平方向の物差しは変わらない。垂直方向は違って来る。)
つまり、局所の時間経過に局所の光速が比例して初めて局所事象が保存される。地上からみて、上空の出来事はすべて高速化される とみるべきで、上空の光速だけそのままということはあり得ない。ある点の光速は、時間経過と物差しのサイズに比例し物差しが方向 に依存するとき光速も方向によって違うと考えられるのである。
特殊相対論は、他の系の時間と空間(時間経過、物差の長さ)を変化させるが、同じ系の中の物差し時計を変化させない。 その系の中での長さと時間の計測は、固有時、固有長として別の系からみても変わらない不変量である。一般相対論では、 非線形の座標系変換を採り、局所がそれぞれ違って座標変換され、g_ik という係数が掛かった不変量の式をもつ。局所の計測は、 座標変換によらない不変量 ds^2 として保存されるのである。