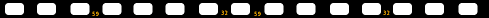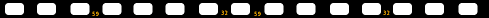|
 |
Wagner: "Siegfried"「ジークフリート」
April 1 (Tuesday), 2003
新国立劇場
Production: Keith Warner
Conductor: Jun Markl
Orchestra: NHK Symphony Orchestra
Cast:
ジークフリート:John Treleaven
ミーメ:Uwe
Eikotter
さすらい人:Donnie Ray Albert
アルベリヒ:島村武男
ファフナー:佐藤康弘
エルダ:黒木香保里 ブリュンヒルデ:緑川まり
森の小鳥:菊地美奈
新国立オペラハウスの、そしてキース・ワーナーによる、奇妙きてれつな「リング」の第三作である。キース・ワーナーの悪趣味ぶりはますます嵩じてきて、ワーグナーの至高の楽劇を、少なくとも視覚的には、冒涜、台無しにしてしまった。
第1幕。ドイツの黒い森の奥深く、人里(そして地底族、天上の神々からも)離れて暮らし世の中のことは何も知らずに育ってきたはずのジークフリートの家が、乱雑なやもめ暮らしのアパート風になっている。ノートゥンク剣の鍛冶がまるでパンケーキを焼くようで、ジークフリート入魂の(はずの)刀鍛冶の歌は力が抜けてまるでさまにならない。加えて、素人田舎歌舞伎の早変わりではあるまいし、ミーメが次々と無意味に衣裳をとりかえたりしていて、見ている我われは音楽に集中できない。ミーメの軽薄な多才多芸ぶりを象徴させようとしているのだろうが、それを歌唱と演技で見せるのが芸(それを引き出す演出)ではないのか。
第2幕。大蛇ならぬお化けトネリコ樹を正面に据え、多数の『奇妙な果実』*(=首吊り人間)をその枝にぶら下げる悪趣味。*1930~50年代のアメリカの黒人女性ブルーズ歌手ビリー・ホリデイの自作自演曲。その中で白人のリンチで殺され樹木に吊り下げられた黒人たちの様子を「奇妙な果実
strange fruits」と描写した。加えて、怪しげな連れ込み宿風モーテルを出したり引っ込めたりして、舞台はなんとも落ち着かない。しかもその表示はドイツ語と英語の混合だ。
第3幕第1場には、いまや廃墟と化した前作「ワルキューレ」の救急病院を持ってきて、さすらい人(ヴォータン)がエルダーととりかわす、苦悩から諦観へ至る重要な歌い合いの間中、消防士風の数人がわけもなく梯子を登ったり降りたりしている。観客はここでも落ち着かない。
第3幕第2場で、「ワルキューレ」の最後、ブリュンヒルデが長い眠りについた場面が再現される。昨年これを見せられたときは不快に近い違和感を抱いたものだが、今回はなんと、ここへ戻ってきてむしろホッとするではないか。
衣裳も、趣味の悪いものが多い。ジークフリートはスーパーマン風のシャツを着ているし(ジークフリートはスーパーマンだったと言いたいのだろうか)、エルダーの衣裳は、そして動きも、スパイダーマン風だ。アルベルヒを車椅子の身障者にする意味は何だろう。森の小鳥にぬいぐるみを着せて舞台に登場させる(声だけだから良いのだと評者は思うのだが)のはまだしも、それが後に裸の女になる。これにはどういう意味があるのだろう。悪趣味以外の何ものでもない。
でも、評者より早く観たオペラ狂の知人が「素晴らしい『ジークフリート』。新国立が初めて世界に誇りうるオペラを創出した」と言っているから、この演出には好き嫌らいが分かれるのだろう。芸術的感性、美的感覚、歴史観などの、起点の置き場の相違だと思う。
かくして歌手たち、オーケストラ、指揮者について語るスペースが無くなってしまった。それほどまでに演出主導の「リング(ジークフリート)」になっているということである。
世界トップクラスのワーグナー歌手をそろえた第一軍のチケットが買えなかったので、評者はこの日を聴くことになった。めっぽう強いが性格は軽薄、そういう狙いならばこの日のジークフリート(トレレーヴェン)は合格、歌唱もまぁまぁで長丁場を無事つとめた。ミーメのアイケッターは上手かったが、極上にはほど遠い。ブリュンヒルデ(緑川まり)、評者は近年ではジェイン・イーグレン(2000年メトロポリタン・オペラ)、デボラ・ポラスキ(2002年ベルリン・ドイツ国立オペラ)と現代最高のブリュンヒルデを聴いたばかりなので、彼女たちと比較するのは酷であろう。
特筆大書すべきはNHK交響楽団。独墺ものを得意とするだけあって、極上のワーグナー音を聴かせてくれた。第3幕冒頭の弦のユニゾン音の美しいこと・・・。重厚な弦楽器群の音の重なり(ワーグナーには不可欠)はこのオペラハウスではじめて聴くものである。その他、たとえば木管楽器群の合奏、掛け合いの妙技妙音等々、随所で「さすがはN響」と思わせた。評者が聴いて来た新国立オペラでは文句なしのナンバー・ワン・パフォーマンス。本評欄でもたびたび触れてきた新国立オペラハウスで聴く薄いオケ音は、ピット内のオーケストラのせいだったと分かる。
ジュン・メルクルの指揮も良い。第3幕の出来はことさらみごとで、休止符を含めたテンポの設定、音量、音のバランスの調合も素晴らしい。演出者の独りよがりの雑駁な舞台を、メルクルとN響の緻密、美麗、雄大な音楽が救ってくれたと言ってよいだろう。この人、ここ数年間で急速に成長、大家への道を順調に疾駆しているようだ。
|
|