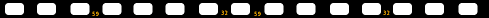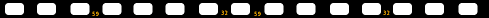|
 |
February 2 (Saturday), 2003
新国立劇場
Production: 鈴木敬介
Conductor: 若杉 弘
Orchestra: Tokyo Symphony Orchestra
Cast:
アラベッラ:Cynthia Makris マンドリカ:小森輝彦
ズデンカ:天羽明恵
マッテオ:経種廉彦 ヴァルトナー伯爵:山口俊彦
アデライデ:白土理香。
舞台を19世紀半ばのウィーンに置いて、斜陽の貴族階級が、その体面と慣れ親しんで来た贅沢な生活様式を守ろうと、なりふりかまわずあがいている、そういう様子を揶揄と憧憬の両方を込めて、R・シュトラウスとホフマンスタール長年の名コンビが、20世紀も1920年代になって、描いた、あるいは描こうとしたオペラもしくはオペレッタである。
シンシア・マークリスのアラベッラが美しい。2年前ここ国立オペラハウスの「サロメ」で、妖艶で、残酷で、かつナイーヴなサロメを見事に演じて見せた彼女の記憶は新しい。そして今回は、同じR・シュトラウスながら「薔薇の騎士」の流れを汲む典雅な貴族社会を具現する。
時代の流れからか、急速に没落の一途を辿りつつある伯爵家、それを経済的に救うには、美貌の娘アラベッラを金満家に嫁がせるしか道は無い。このような一家の緊急事態は重々知りつつも、自らの一生を預けるにふさわしい男と出会いたい。そう願う甘い娘心も持っている。
落ちぶれたりとは言え伯爵家、そこに育った娘ならばそれなりの気品、貴族階級の雰囲気は十分に備わっている。アラベッラはそれを舞台の上で見せなければならない。第3幕、ウィーンの豪華ホテルの階段を、グラス一杯の水を片手に下りて来る。最後の甘く劇的なクライマックス、エンディングの序奏とも言うべき、そしてアラベッラの美しさと気品を示す、俗に「アラベッラの階段場面」と言われている、大事なシーンだ。それをシンシア・マークリスがほぼ満点と言ってよい演技と歌唱で見せ、聴かせてくれた。階段の中ほどやや左寄りに立ち、首を心持右に(彼女の左肩の方に)傾けて階段下のロビーに立つマンドリカにささやくように語りかけるアラベッラ、その優雅な立ち居振る舞いは、一幅の泰西名画を見るようだ。
ここで聴衆を甘い陶酔の境地に誘い込むにはそれなりの仕掛けが必要。というわけで美術担当のパンテリス・デシラスに拍手。最新鋭を誇る新国立劇場の舞台装備を駆使して、第2幕の舞踏会シーンから第3幕の豪華ホテル階段のシーンへと(いずれも豪華なもの)、短い間奏曲のあいだに、音も無く変換してみせた。この装備といい、第2幕で示された舞台の深い奥行きといい、専用のオペラハウスをやっと持つことになった喜びが、満喫できる。
マンドリカの小森輝彦が一段とうまくなった。つい先日、場所も同じここ新国立の「ナクソス島のアリアドネ」で音楽教師を歌う彼を聴いたばかりだが、今度は大役マンドリカである。西欧のオペラとくに喜劇オペラ(オペレッタ?)ではとかく学芸会風の演技になりがちな日本人歌手たちだが、小森輝彦は現在オペラの本場ドイツの第一線歌手として活躍中、歌唱はもとより、演技も堂々としていて、馥郁たる香りを漂わせる演技のマークリスにまったくひけを取らなかったのは見事。
それとは対照的に、歌唱はまあまあながら、ズデンカ(天羽明恵)とマッテオ(経種廉彦)はまさに学芸会風、国際レベルのオペラ歌手を目指すにはもっともっと研鑽が必要だ。
オーケストラがお粗末。R・シュトラウスの音楽の特徴は重厚かつ華麗なオーケストラ音にあるはずなのに、ピットから出てくる音は細く枯渇してくたびれ果てたものでしかない。なかでも金管部門の貧弱さは耳を覆いたくなるほどのものだった。もしかしたら、第一次大戦に敗れて疲弊したオーストリア(初演時)の状況を再現するべく、若杉弘が意図的にそのような音を東京交響楽団から引き出したであろうか。もしそうなら、それはみごとに達成されていた。
|
|