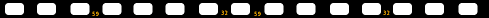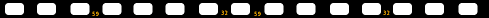|
 |
NHK交響楽団第1479回定期公演
2003年1月15日・サントリーホール
Weber: "Der Freischutz"
Overture op.77
Scumann: Cello Concerto in a,
op.129
Dvorak: Symphony No.9 in e, op.95
"From
the New World"
指揮 イルジ・コウト
チェロ ミクローシュ・ペレーニ
本家のチェコ人に劣らず、日本人はこの「新世界」交響曲が大好きである。私もその例外ではない。長いN響の歴史の中で、演奏回数の多さでは「新世界より」は第3番目だそうである。
そういう、いわばN響が慣れ親しみきった曲なのだが、この夜はそれをまことに新鮮、みずみずしく演奏した。チェコ人コウト(現在はドイツ国籍だそうだが)が母国の英雄的作曲家の最大傑作を振るのだから、熱がはいるのは当たり前だろうが、彼の解釈はやや従来の世間一般のそれとは異なるようだ。
コウトは「ドヴォルザークは、家族がアメリカにやってくると知って大いに喜び、その嬉しさの中でこの曲を書いた。だから世上言われているようにホームシックにかかったドヴォルザークが故郷を懐かしみつつ書いたというメランコリックな曲ではない」と言っている。そうプログラムに書いてある。
聴いてみて、なるほどその通りの解釈そして演奏だと分かる。明瞭快活、やや早めのテンポのもと、胸のすくような快演であった。もとより全曲を通じて良かったのであるが、聴かせどころの第2楽章が秀逸、二重丸。かの「家路」の主題を弦楽四重奏で奏でるあたりでは、聴いていて、その美しさ、嬉しさのあまり、涙がこぼれそうになる。この楽章を頂点として、コウトは同郷の大先輩が「アメリカにいて故郷を想う」あり様を、詩情豊かに、情感を込めて、しかしあくまでも明るく、歌い上げたのだった。
この夜のN響の木管楽器陣に拍手。なかでも「家路」の主題をコウトが求めたであろう「まもなく故郷から家族がやってくる」その嬉しさを、情緒たっぷりにしかし明るく表現するに万全であった、若きイングリッシュ・ホルン(オーボエと併奏)女史には花丸印。
それに引き換え、金管楽器群とくにホルンが粗雑。N響ともあろうものがン十年前ならいざしらず、金管晴れの舞台であるはずの「新世界」交響曲でトチるとは。
シュトゥットガルト放送管弦楽団からの客演ティンパニー奏者(ノルベルト・シュミット=ラウクスマン)にも拍手。パーカッションがひとり替わるだけで、オケ音全体が変わってしまう、そういう印象すら受けた。
ウエーバーの「魔弾の射手」序曲では、コウトの棒が読みにくいのか、出だしの不ぞろいが気になった。ここでも聴かせどころでホルンがトチって興ざめ。ドイツの黒い森の奥からドロドロと響いてくるようなティンパニーの妙音に感服。N響がワーグナーの「ジークフリート」で新国立劇場のオペラ・ピットは入るのだそうだが、ぜひこの人に本場のワーグナー音を叩いて欲しいと思う。
|
|