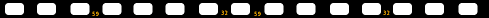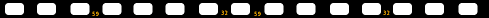|
 |
February 2 (Wed), 2000
Suntory Hall
Philharmonia Orchestra Concert
Chopin : Piano Concerto No.1
in e, Op.11
Tchaikovsky : Symphony No.5 in
e, Op.64
Martha Argerich (piano)
Vladimir Ashkenazy (conducting)
Philharmonia Orchestra
昨年アルゲリッチがもと夫君のデュトワの指揮、NHK交響楽団でこのショパンのホ短調協奏曲を弾いた(1998年12月、NHKホール)。大変な評判で、評者はチケットを買うことが出来なかった。そのアルゲリッチが何とショパン弾きの名手であり近年指揮者としての名声を高めつつあるアシュケナジー、それにフィルハーモニア管弦楽団と組んでもう一度ショパンを日本で弾く。しかもただの一度だけ。そう聞いては聴き逃すわけにはいかない。2000年ミレニアム・イヤー前半の屈指のコンサート、そう目星をつけてチケット入手に文字通り奔走した。やっと手に入れたのはA席27000円也、夫婦ふたりでで聴くと54000円という、近場の海外旅行ならば十分にこれで行けそうな高額チケットである。でもこんな豪華な組合わせのショパンは今後いつ聴けるか分からない、そう思えばこの出費も仕方ないだろう。
「Karajan Gate」と書かれた回転ドアをくぐり抜けて、寒い北風が吹くサントリー・ホール前の中庭広場へたどりつくと、開場時間の6時半はとっくに過ぎているのに、黒山の人だかりである。アルゲリッチが風邪でも引いたのではないか、との危惧が頭の隅をよぎる。やがてハンド・マイクを手にした係りの人があらわれ、 「リハーサルが長引いていて、開演が遅れます。悪しからずご了承下さい。 ただいま第3楽章に入っていますので、まもなく開場できると思います。」とのアナウンスがあった。
ショパンの演奏にかけてはともに第一人者、プロ中のプロであるふたりが顔をあわせる、それも今夜1回かぎり。であれば解釈の相違もあろうし、打ち合わせに時間がかるのは仕方がないだろう。開演の遅れは、それだけ真剣に演奏に取り組む二人の熱意のあらわれ、そう理解することにしよう。 結局30分おくれての開演となる。
評者がアルゲリッチのナマのコンチェルト演奏に接するのは、1970年代はじめのニューヨーク・フィルハーモニーの定期演奏会、小澤征爾のもとでのラヴェルのト長調協奏曲以来である。あれから二十余年の歳月が流れて、熟年の域も過ぎたアルゲリッチが貫禄十分の体つき、表情で、サントリー・ホールのステージに現れた。腰から深くからだを折るラテン式のお辞儀、これはその昔と同じだ。
好演、ではなく熱演。(当然のことながら)満員の聴衆が息を止めるばかりに全身全霊を傾注して聴き惚れたショパン、そう評してよいだろう。技術がどう、解釈がどう、表現、テンポ、アクセントがどう。そういうことに言及する必要は全く無い。それをすれば、アルゲリッチ、アシュケナジーそしてフィルハーモニアの面々に礼を失することになる。
評者はこのコンチェルトが好きで、LP時代から今日に至るまで、数多くのレコードやCDを買い集め、またコンサートにも通って、聴き込んで来ている。そのディスク群の中でいちばん回数多く聴いていて耳に馴染んでいるのが、実はアルゲリッチ/アバード/ロンドン・シンフォニーのDG盤LP、そしてその次ぎはたぶん大御所ルビンシュタインのRCA盤(これもLP)だろう。いまでも「ショパンの第1番」を聴こうと思えば、煩瑣を厭わず、これらのLPに手を伸ばすことが多い。
そのアルゲリッチが目の前で、その「ショパンの第1番」を弾いている。こんなに嬉しいことはない。すでに何十回もアルゲリッチで聴いてきているのだから、その演奏スタイルには何の違和感も無い。あれこれ思いをめぐらせることはやめて、とにかく彼女のショパンに浸りきる、それが今夜のベストの過ごし方であろう。そしてまさに至福の三十数分間であった。
アシュケナジーとの間で見解の相違でもあってリハーサルが長引いたのか、とすればそれは何処だろう、たぶん第3楽章? チラとそういう思いが頭をよぎる。でもふたりのショパンは疾風のごとく、第3楽章を駈け抜けてゆく。ものすごい速さ、これこそがアルゲリッチのテンポである。(ではアシュケナジーならどう弾くのだろう、と思ってみたのだが、アシュケナジーが弾く「ショパンの第1番」のディスクが家のどこを探しても見つからない。出ているのならば当然買っている筈と思うのだが。)
熱狂した聴衆に応えて、ふたたび、三度、からだを腰から深く折ってのラテン式お辞儀。しかしアンコールは無かった。でもこれだけのショパンを聴かせてもらったのだ。満足々々。
チャイコフスキーの第5番交響曲について書くスペースが無くなってしまった。これも評者の大好きな曲で、実はついこの間、マズア/ニューヨーク・フィルで聴いてきたばかり(1999年9月28日、NYフィル定期演奏会)。第2楽章のホルン・ソロの上手さに感嘆し、第4楽章のブラスの咆哮にからだを震わせたのだったが、その同じ第5番をアシュケナジー/フィルハーモニアはどのように演奏するのか。
アシュケナジーは指揮者活動に入った初期(1977年)に、フィルハーモニアでこの曲をデッカに録音していて、それは評者も聴いている。いわば得意中の得意のレパートリーというところであろう。
チャイコフスキーの運命の主題が、あるときは優美に、また厳かに、ときに神秘的に、また脅迫的に、楽器を変えニュアンスを変えて、繰り返し出現する。それを料理するアシュケナジーの指揮棒に敏感に反応するフィルハーモニアはさすがに上手い。
第2楽章のホルン・ソロ、本来ならばその甘美なメロディーにどっぽり身をゆだねるべきなのだが、ナマのコンサートではいつのまにか緊張してここを聴くのが習慣になってしまった。残念ながらこの夜のホルン奏者はいまひとつ冴えなかったようで、ミス音がひとつ出た。第4楽章の大音響部は音量も十分で、体育会系の興奮すらおぼえる、心地よい終幕の盛り上げとなった。
アンコールは一転して弦のメンバーだけでの「アンダンテ・カンタービレ」。楽団員の譜面台にはほかにも楽譜が用意されていたようだが、開演時間が遅れたためであろう、アンコールはこれ1曲のみであった。
お許しを得て余談をひとつ。最近発売されたツィンマーマン弾き振りのショパンの「第1番、第2番協奏曲」(DG盤)を、日本のレコード評論雑誌がベタ褒めしている。ショパン・コンクールを制した直後、まだハイティーンだった頃のツィンマーマン/ジュリーニ/ロサンゼルス響のDG盤(LP)は溌剌とした若さに溢れる好演で、評者の愛聴盤のひとつ。そういうこともあって雑誌の評につられて新録音を買ってみた。ところがこれが大はずれ、まったく評者の好みに合わない。「笈<キュウ>を背負って、これから花のウィーン、パリへ出かける」という若き颯爽としたショパンの面影はそこには無く、年増の厚化粧のような、ひとりよがりの思い入れと過剰なテンポの揺れを聴かされてしまったのだ。いずれグラモフォン誌なりペンギンなりが客観的な評価をくだすだろうが、日本で読むディスク評は、レコード会社が売るために考え出す宣伝コピーの受け売りが多い、どうもそのような気がしてならない(なぜならば、書き手は異なっても評の中身は大同小異ということが多いのだ)。
|
|