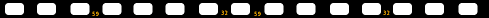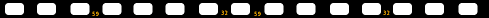|
 |
January 15 (Sat), 2000
Bunkamura-Orchard Hall
Donizetti : "Lucia di
Lammermoor"
Fujiwra Opera Company
Stage Director: Henning Brockhaus
Set Director: Josef Svoboda
Music Director: Stefano Ranzani
Fujiwara Opera Group Chorus
Tokyo Philharmonic Orchestra
<Cast> Lucia: 佐藤美枝子 Edgardo:
佐野成宏 Enrico: 堀内康雄
Raimondo: 矢田部一弘 Arturo:
田代誠 Alisa:
河野めぐみ
Normanno: 有銘哲也
1999年のチャイコフスキー国際コンクール声楽部門で優勝した佐藤美枝子(もちろん日本人では初めて)のルチア、同年のモービル音楽奨励賞を得た佐野成宏のエドガルドという待望の組み合わせは、2000年ミレニアム・イヤーの日本オペラ界幕開けに相応しいものとなった。
藤原オペラでは第1、第3公演日の主要キャストを外国人で固め、中の第2公演日に日本人によるキャストを組むのを常とし、従来は外国人の日からチケットが売れて行くのだが、今回の公演に限って、第2日目の方が先に売りきれとなった。このふたりの歌手の顔合わせに寄せるファンの期待の大きかったことが、ここからも分かる。
結論から言えば、大成功。佐藤、佐野に加えてエンリーコを歌った堀内康雄は、国際的舞台に通用するであろう水準の歌唱を聴かせてくれた。評者が観た(そして聴いた)のは第2日目だけだが、日本でのオペラはまずは全部観るというオペラ・ファンで、3公演を全て見た評者の知人は「2日目がいちばん良かった」と言っていた。
佐藤美枝子はチャイコフスキー・コンクールでも「ルチア狂乱の場」のアリアを歌ったことだし、正月のNHKニューイヤー・オペラ・コンサートでもそのさわりの個所を披露していたように、今まさにこのオペラで売り出して行こうとしているコロラチューア・ソプラノである。コンサートでアリアを1曲歌うのと違って、あの細い小さな身体で全曲の長丁場が持つのかとの危惧を、リサイタル・ステージでの佐藤を観たことのあるファンなら誰しも抱いたであろう。評者もそのひとり。だがそれは全くの杞憂であった。
よく練られたベル・カントは中音から高音超高音域まで安定して、美しくそして十分な声量で響いていたし、音程も正確。聴き手は安心してベル・カント・オペラの陶酔の世界に浸ることが出来た。とくに「狂乱の場」の出来は見事で、歌唱後満員の聴衆は湧きに湧いた。例の聴かせどころのフルートとのデュエットでは、オーケストラ・ピットの奏者(妙齢の女性奏者だった)が立ちあがって、ルチアと目と目を合わせながらフルートを吹き、そこへルチアともどもスポット・ライトを当てるという、洒落た趣向が用意されていて、興を盛り上げた。
昨年3月の新国立オペラハウスでの「ラ・ボエーム」で白熱のロドルフォを聴かせて、日本のベル・カント・テノールに佐野あり、を印象づけた佐野成宏、こちらは恵まれた体躯と舞台映えする容貌で、堂々のエドガルドぶりであった。(前記の友人は「外人組はエドガルドがひどかった」と評していた。どうやらスキンヘッドで出てきたらしい。)そして張りのある美声。いままで日本にはこのようなタイプのテノールはいなかった。
「プリマドンナが死んだあとで、延々とテノールが歌って舞台を独占する。テノール冥利につきるオペラで、やり甲斐があります」。モービル賞の受賞パーティー席上、佐野は評者を含む一群のオペラ・ファンにそう語っていたのを思い出しつつ、終幕のテノールの独壇場を聴いていた。ところどころで地の声がちょっと顔を出すことはあったが、それは克服可能な今後の課題ということ。まずは無難に、というよりは見事に、このテノールにとっては試練とも言える長丁場の難役をこなした。
もうひとつの収穫はエンリーコの堀内康雄、声よしルックスよしで、舞台を盛り上げた。とくに第2幕第1場、エンリーコとエドガルドが激して決闘の約束をする緊迫した場面(演出によってはこれを省略することもあるがもったいないことだ)での佐野とのやりとりは見ごたえがあった。これにくらべて、ライモンドの矢田部一弘が弱く、声量音程ともに上の3人にくらべ、かなり聴き劣りしたのは残念。このオペラのたくさんある聴かせどころのひとつ「ルチアの六重唱」もしっかりとした堂々の出来で、オール日本人キャストでここまで出来る!との喜びを与えてくれた。
では「この『ルチア』を世界第一級の桧舞台へ持っていけるか?」と問われれば、「ウーン、まだもう少し」と答えざるを得ないだろう。評者はメトロポリタン・オペラその他で、古くはスコット、サザーランドから最近ではロストなど、そしてパヴァロッティ、クラウスほかの名唱名演、豪華絢爛の舞台を観、聴いてきているので、採点がどうしても辛くなるのは仕方がない。
ステージ全面に紗とそれに投影する映像、それに木の階段を大胆に使った演出、美術は、それなりの効果は挙げていたとは思うが(ルチアに刺された血だらけの花婿アルトゥーロを、階段の上から下までスタントマンを使って転がすのは、目新しくはあるがやややり過ぎではなかったか)、所詮は三日間だけ使えばよい安直な舞台、日本のオペラ公演の実情から致し方ないとは分かるのだが、時代劇に相応しい重厚な衣裳との対比ではいかにもちぐはぐであった。
スカラ座その他でも振っていて、歌手を気持ちよく歌わせる術を熟知していると思われる、イタリアの指揮者ランザーニ、東京フィルハーモニーも好演。 豪華で優雅なオペラを存分に楽しんだところで席を立つと、オーチャード・ホールのロビーや階段は化学製品タイル張り、そしてその外は渋谷の街の喧騒で、ヤマンバ、ガングロ、厚底ブーツのお姐ェチャンたちが闊歩している。なんともちぐはぐな東京でのオペラ鑑賞であった。
|
|