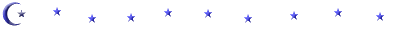
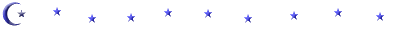
『三月は深き紅の淵を』に言及される本・映画などについてのコメントです。
ちょっとブラックユーモアのきいた短編の名手というイメージが強いですが、児童文学作品でも有名な作家。
『三月は深き紅の淵を』(以下『三月は・・・』と略す)の冒頭に引用されているロアルド・ダールの『チョコレート工場の秘密』は記憶になかったので読んでみました。あらすじは『三月は・・・』p.294-295に詳しくのっているので省きますが、確かにこれは読みだしたら止まらないですね。結構ブラックですが。『おばけ桃の冒険』の作者がロアルド・ダールと知って「ああ、あれもおもしろくてブラックだったなあ」と思い当たりました。(ちなみに『おばけ桃の冒険』は少し前にティム・バートン製作のストップ・モーション・アニメーション映画『ジャイアント・ピーチ』の原作でもあります。)
また、『三月は・・・』の出だし、「じゅうたんの模様の踏んでいいところといけないところを自分で決めていた子供」の話はロアルド・ダールの短編「お願い」(『あなたに似た人』ハヤカワ・ミステリ文庫所収)です。
「ジャングルと言えば、連想する映画がある。」(『三月は・・・』p.286)
ベトナム戦争で戦闘中重症を負った主人公ジェイコブは、帰国後、奇妙な幻覚や夢に悩まされる。何者かに追われ、殺されかけたり、主治医や戦友が爆弾事故にあう。どうやら、軍が秘密裏に開発しベトナム戦争で使用した麻薬に原因があるということを突き止めるが・・・。
ポリティカル・サスペンスの装幀でありながら、よじれた悪夢の深みにはまっていくような雰囲気。レンタルビデオ屋で、「戦争・アクション」ではなく「SF・SFX」のコーナーに置いてあったのも納得です。ジャングルの木々の間から見上げた空、地下鉄の揺れるあかりなど凝ったカメラワークと独特の”間”が特徴的です。とりわけ、最初の方の「わけのわからない」雰囲気がよかったです。テリー・ギリアムに出会う前だったらかなり気に入ったかもしれないと思うのですが、途中で「もしかしたら」とラストが読めてしまい、ちょっと醒めてしまったのはもったいなかった気がします。
以下蛇足。
*麻薬の名前は”バナナ・フィッシュ”ではありません(^^;)。
*タイトル”Jacob's Ladder”の元の意味は『創世記』にでてくる「ヤコブが夢にみた天に至るはしご」。
*知ってる人にはネタバレになるのですが、エイドリアン・ライン監督(他作品『フラッシュ・ダンス』、『危険な情事』など)はアンブロース・ビアスの短編「アウル・クリーク橋の一事件」(『生のさなかにも』創元SF文庫所収)にこの作品の着想を得たらしいです。
「四部作という形式に憧れているのは、ロレンス・ダレルの「アレキサンドリア・カルテット」という素晴らしい四部作のせいだ。」(『三月は・・・』p.247)
こちらも『三月は・・・』で初めて知った作品ですが、読んでみるとこれはすごい。「憧れる」というのもむべなるかな。
三作は空間的な関係のなかで重なりあい、からみあい、第四作のみが(時間的)続編となっています。現実は一つの真実で構成されているわけではなく、各々の見た断片的な出来事が散在しているだけ・・・。第一作で描かれた出来事は、次々と変形し、裏側に隠れていた真相、人の思いなどが示唆に富んだ文章で、重ね塗られていきます。
一行二行のあらすじ紹介は、興をそぐだけという気がするので、具体的なさわりはあえて書きません。読み終えるのに若干時間がかかりましたが、とにもかくにもおもしろいです。読み応えのある本が少ないとお嘆きの本好きの方で未読の方がいらっしゃいましたら、必ずやご満足いただけると思います。
『三月は・・・』第三章(p238-284)で、美沙緒と啓輔が期末試験が終わった後に見に行った映画。
“ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)”を代表するジャン=リュック・ゴダールの代表作。
昔の恋人・マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と再会した主人公・フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモンド)は不可解な殺人事件に巻き込まれ二人で逃飛行を続けるはめとなり、破滅に向かってまっしぐらというお話。啓輔がたちまち眠り込み目を覚ましたらラストのクライマックスだったというのがうなずける退屈さとカルトな魅力をもつ映像詩がまざりあった作品。
ラストのモノローグは言わずもがなですが、ランボーの詩『地獄の季節』の中の一節。
「彼のイメージのすさまじさ、その吸引力に見ている私までもがひきずりこまれそうなほどだった。」(『三月は・・・』第四章 p.280)
ダーガーが人知れず60年にわたって書き続けた小説と絵画『非現実の王国で』。子供たちが虐待される王国で、7人の美少女戦士ヴィヴィアン・ガールズが死闘を繰り広げる物語。
この度『ヘンリー・ダーガー 非現実の王国で』(ジョン・マグレガー著 作品社)が刊行されたようです。詳しくはこちら。このページにはダーガーの生涯や書籍データなども掲載され、リンクページも充実していますので、ダーガーについて知りたい方はぜひどうぞ。
