
10月10日 Oct. 10
01:00 バンベルグ入港。
08:30 市内観光ツアー。ラオホビア試飲
11:45 帰船。
12:00 ビュルツブルグへ向けて出港。
Arrive at Bamberg-city tour-leave for Burtburg

バンベルクはマインツ川の支流レグニッツ川が町の中央を流れている。町は第二次大戦で戦禍を免れているためこの流れに沿って古い家並みが残り「ドイツの小ヴェネチア」と呼ばれるに相応しいたたずまいを見せている。川の中洲に建つ旧市庁舎は橋で両岸と結ばれた変わった作りになっている。外壁にはフレスコ画が描かれ、川に突き出した木骨組の部分と相まって何とも言えない美しさだ。1993年に世界遺産に登録された。
From the 10th century onwards, this town became an important
link with the Slav peoples, especially those of Poland and Pomerania. During
its period of greatest prosperity, from the 12th century onwards, the
architecture of Bamberg strongly influenced northern Germany and Hungary. In
the late 18th century it was the centre of the Enlightenment in southern
Germany, with eminent philosophers and writers such as Hegel and Hoffmann
living there.
The city is registered as World Heritage in 1993.
City Hall on the bridge over the Regnitz river.


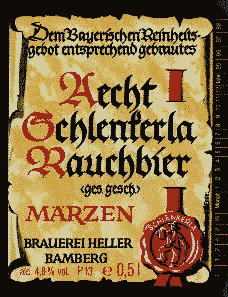
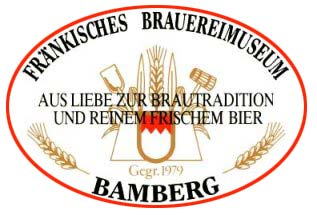
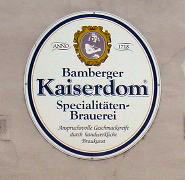


1536年創業のラオホビア醸造所・ビアホール Smoked beer Brewery & Pub since 1536
ドイツでは地方ごとに独自ブランドのビールが数多くある。ビール好きの人のために、ビール醸造所を巡るツアーなんていうのも催されているくらい。 数あるドイツビールのなかでも変り種がラオホビア(Rauchbier)、バンベルクで製造される燻製ビール。 その紹介をすこしばかり。
バンベルクは、世界最古のビール醸造の中心地の一つにも数えられるとともに、モルト(麦芽)製造の中心地としても有名。
さて、『ラオホビール』はどのようにして誕生したのか?
これについては『中世にビールを醸造していた修道院が火事になった。せっかくのモルトが煙で燻り薫製になってしまったが、捨てるのはもったいない。仕方なくそのモルトを使って醸造したら、思いがけない味になっていた。これがラオホビールの始まりだ。』という話が伝わっているそうな。
現在は、製麦の際、発芽を終えた大麦を乾燥させる工程で、3年以上寝かせたブナの木のチップで24時間薫製にし、薫製麦芽(ラオホモルト)を造る。
キメ細かい泡立ち、薄めのカッパ―ブラウン。甘味を含んだ控えめな薫製香。少し時間を置くと香りが引き立つのが特徴。
炭酸ガスの刺激とホップの苦味は、燻した雰囲気を楽しむため極力抑えてある。
一口のどを過ぎるころにスモーキーな風味が鼻からフゥッと抜けていきます。
ラオホビアいろいろ