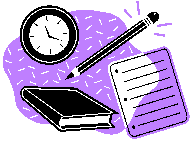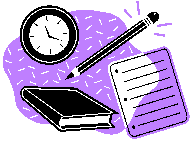もう二十年以上も前、テレビに大量のCMを投入した角川映画のキャッチ・コピーは、「見てから読むか、読んでから見るか」というもの。これは、映画の原作の文庫本と映画そのものの大ヒットを狙って、両方に興味を持ってもらおうという、実に上手い宣伝文句だった。
しかし、実際に先に原作を読んでから映画を観て、登場人物のイメージの違い、作品全体のスケールの小ささにガッカリした事は誰にでもあるだろう。
逆に、映画を先に観て感動し、原作を読んで初めて、「ああ、そういう事だったのか。映画化に際して、随分と省略し、設定も少し変えたんだな」等と思う事も多い。
しかし、一番よく聞くのは、「原作を越えていない」や、「原作のイメージがブチ壊し」という批判だ。何故か?
それは、どんな映像でも人間の頭の中にあるもの、人間の脳の想像力には敵わないからだ。
原作を読んだ人それぞれの頭の中に、読んだ人の数だけの作品世界が存在し、その人自身が作った映画が出来ていると言っても過言ではない。
『よみがえる幻の名作―日本無声映画篇』は、ちょっと信じられない事に挑戦した本だ。戦前、色々な事情で、フィルムが失われ、今はもう観る事が出来ない日本映画の「幻の名作」五十一作品の、あらすじ、解説、スチル写真を収録し、読者に、「恐らくは、かつて一度も観た事がなく、今後も観る機会がないであろう映画」を、《さあ、貴殿の頭の中で再々構築して下され。さてさて、貴殿のドタマの程度はどの程度かいな?》と、約五十回も迫って来る一冊なのだ。
とても歯がゆいが、最高に楽しい。
かつて、淀川長治さんが、「もう一度、何としてでも観たい粋な粋な映画。でも、何処にもフィルムが残ってないの。」と、熱く語っていた『アマチュア倶楽部』は、一九二〇年製作の「現代喜劇」。鎌倉・由比ガ浜での若者の一騒動を描き、当時の映画劇運動の先陣を切ったという映画史的に重要な作品で、俳優として、内田吐夢監督や、井上金太郎監督も出演し、原作者の谷崎潤一郎その人も顔を見せているというから、本当に観たくて観たくてたまらなくなる。
『村の花嫁』(一九二八年/五所平之助監督)の解説はこうだ。
「お静が馬車に轢かれたシーン。カメラ手前から、村人数人が事故現場へ一直線に駆けて行く。普通なら、カメラを馬車のそばへ持って行くが、五所はそのまま右へ緩やかにカメラを移動して、風にそよぐ稲穂をとらえた。静の極致をとらえる事によって、馬車付近の人々のざわめきをひとしお感じさせているのだ。」読んでいて、唸ってしまった。サイレント映画の魅力があふれている。きっと誰かの記憶、何処かの記録を元に再現したに違いないのだが、もう七十五年も前のこの映画を今、観たような気持ちになってしまう。
読み進む内に、大河内伝次郎の殺陣がどんなに速かったか、阪東妻三郎の独立プロ設立がいかに一大事件であったか等、当時の映画界の様子も浮かび上がって来るが、もう一つ強く感じたのは、この時代の日本人が持っていた実直さや、正義感の強さ、シンプルな人の良さだ。人々の多くは、まだ貧困や社会におけるあらゆる差別とも戦わなければならなかった。
現在、すべての社会悪が消え去った訳ではないが、この本の中に出て来る、今は既に死語となってしまった言葉たち《近代女性、桃色の雰囲気、傾向映画、洋行、至誠…》や、素晴らしいタイトルの数々《陸の人魚、からくり娘、足にさわった女、熊の八つ切り事件、摩天楼・争闘篇…》に触れるだけで、我々がこの数十年の間に確実になくした何かを思い出させてくれる気がする。
ここ数年、韓国や中国、イランの映画にこれほど日本の観客が入る理由も、この「我々が失った何か」がそこにあるからではないのか?失われたのは、フィルムだけではなかった。
八十年近く前に想いを馳せながら、ブーメランの様に現代の日本に気持ちが返って来る、実に稀有な一冊だ。
 
『よみがえる幻の名作 日本無声映画篇』
無声映画鑑賞会・編
(株)アーバン・コネクションズ発行
1800円 +税
|