

![]()
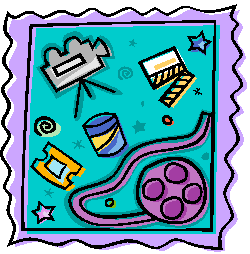
私が観た映画 年間ベスト10 1991年〜1992年
![]()
1989年 1 ペレ
「いいか、デンマークへ行ったらなぁ、パンにな、バターを塗って食べられるんだぞ」と、ささやかな夢を語るペレだが、現実は厳しかった。19世紀のデンマークの小島。スウェーデンからの移民親子の可酷な体験。マックス・フォン・シドー、渾身の演技に震えた。
2 サンドイッチの年
一筋縄ではいかない偏屈者の古物商・マックスを演じたヴォイツェフ・プショニャックの芝居は、「マルサの女」の山崎努に似ている。誰の人生にも、“サンドイッチの年"がある。そこには、美味しいハムやキュウリもあるが、時には辛子に泣く事だってあるのだ。
3 バベットの晩餐会
19世紀後半のデンマークを舞台に、質素な生活を送っている村人たちとフランスからやって来た女性との出逢いと当惑、そしてある晩餐会の一夜を描く。“私たち芸術家は、決して貧しいという事はないのです”というバベットの矜持を生涯、心に刻んでおこうと思う。
4 トーク・レディオ
欧米で議論を呼んでいる“ショック・ラジオ"を舞台に、マス・メディアと聴取者との間の敵意と憎悪を描く。私も同業者なので、思いも寄らないラストには、とても衝撃を受けた。時には、その左翼振りが痛いオリバー・ストーン監督の資質がプラスに作用した一篇。
5 ダイ・ハード
事件に巻き込まれた1人の刑事の活躍と戦いを描くシリーズ第1作。いつもタイミングが悪い場所にいるブルース・ウィリスの、“またかよ。やれやれ…”という表情がサイコーだ。日本企業のビル、ご褒美のロレックス… 大道具小道具が最後の最後まで生きていた。
6 私の中のもうひとりの私
隣室の精神分析医に通う患者の声が、かつての自分の苦悩と二重になり、次第に“もう一つの自己”を見つめ直すようになる女。ジーナ・ローランズ、ジーン・ハックマン、ミア・ファローら名優の共演。スヴェン・ニクヴィストによる映像は、見ているだけで幸せだ。
7 ブラックレイン
“久しぶりだな”“ああ、久しぶりだ”。冒頭、ニューヨークのレストラン。この瞬間、松田優作は世界へ飛び出した。私がこの映画を観た時には、彼はまだ生きていた。M・ダグラスを完全に食っている。役者に大きい小さいはあっても、演じる役に大小などないのだ。
8 ショコラ
1950年代末期、カメルーンのフランス統治の小さな行政区で、使用人の黒人青年と奇妙な友情で結ばれるようになる少女。物語の始めと終わりとで、人は同じではあり得ない。黒人青年を演じるイザアック・ド・バンコレの存在の危うさ、デリケートさ。美しい映画。
9 その男、凶暴につき
公園のホームレスのおっさんのアップで始まる。彼に暴行した少年の部屋に、ほぼ無言で入って行き、殴るたけし刑事の迫力。更に、「フレンチコネクション・2」ばりに徹底的に足で追い掛けグイグイ見せて行く。ラストは若い女の顔のアップ。処女作とは思えぬ快作。
10 殺人に関する短いフィルム
ある殺人事件を通しポーランドの現代社会の歪みを、鋭く厳しく描く。貧しい青年が何の罪もないタクシー運転手を惨殺するのは、明らかに恵まれない自分の人生と社会に対する恨みが原因。故クシシュトフ・キェシロフスキ監督の出世作。彼の「神曲」が観たかった。
1999年 1 ゴースト〜ニューヨークの幻
幽霊となっても愛する人を守ろうとする男の姿を描くファンタジックなラブ・ストーリー。この映画の成功が、後に「シックスセンス」「ブレイブワン」へと繋がって行く。ウーピー・ゴールドバーグが演じる霊媒師が、渋々教会へ巨額の寄付をする所が最高に笑え、ラストは涙、涙。
2 てなもんやコネクション
室田日出男が、香港ロケの最中に役を降りてしまった為、映画の途中で、彼の役・茜が女優・鈴木みち子に変ったり戻ったりする奇天烈振り。しかし、その強引な手法は、この映画のテイストと一致、全体のハチャメチャさ加減を増幅させているから凄い。楽し可笑し。
3 どついたるねん
ボクシングで再起不能となりながらも、カムバツクに賭ける男の姿を描く。主人公・安達は、もちろん演ずる赤井英和にピタリ重なる。大阪・西成のガサツだが、とてつもないパワー。映画全体からビュンビュンとパンチが飛んで来る、阪本順治監督の長編デビュー作。
4 死の棘
別離の危機に瀕した夫婦の絆と家族の再生。夫婦の葛藤がピークに達した時、ノーメイクの松阪慶子が上半身裸になる。それが、まるで少年がダダをこねてシャツを脱いでしまったみたいで、エロスではなく、人間としての可愛らしさを感じた。こんな映画は他にない。
5 サラーム・ボンベイ!
インドのボンベイを舞台に、ストリート・チルドレンたちの苛酷な生活と、逞しい生命力を描く。500ルピーのカタにサーカスに売られた少年・クリシュナに幸あれ。“30日間で36ヶ所のロケ。まだまだやれる!”という、エンド・クレジットの監督の言葉に脱帽!
6 ウディ・アレンの重罪と軽罪
愛と欺瞞を2つの物語から描く。浮気は軽罪だが、殺人は重罪。人を殺しても誰にもバレず、主人公はその後も平穏に暮らして行く…という展開は、後のアレン作品「マッチポイント」にも出て来るが、彼が描きたかったのは、“人生そのものの理不尽さ”に違いない。
7 カミーユ・クローデル
19世紀末、愛と芸術の葛藤の中で生きた彫刻家カミーユ・クローデルの後半生。イザベル・アジャーニは、これで、「アデルの恋の物語」を超えた。2001年春、パリのロダン美術館で、初めてカミーユの作品に接した私は、涙が止まらなかった。この映画のせいだ。
8 幻の女
私の大好きな「アメリカの夜」と同じく、これは“映画の映画”。映画製作に失望を感じている監督のポール(もちろん、アラン・タネール監督の分身と言える)を演じるジャン・ルイ・トランティニャンの少し枯れた様な味わい。物語が進んで行く、そのタッチが良い。
9 ニューシネマ・パラダイス
真田広之“最近、すごく良かったのは、「ニューシネマ・パラダイス」ですね” 森卓也(映画評論家)“あんな間違いだらけの映画の何処がいいの?”この会話の場にいた私は次の言葉が出て来なかった。ディテイルはともかく、シチリアの小さな村そのものが父親だった。
10 マイ・レフトフット
冒頭、唯一、辛うじて自由が利く左足でレコードをかけるシーンで、この男の苦悩を瞬間的に描いてみせる。重度の脳性小児麻痺に冒されたアイルランド人画家が結婚相手に選んだ女性は、何処か優しい母親に似ていた。ダニエル・デイ・ルイスの代表作となった力作。