| 山 田 |
なるほどね。 |
| 岡 村 |
監督はいろんなインタビューでおっしゃっているんですが、“今、日本全体が景気もよくないし不安を抱いている。でも、そんなに
心配しなくても自分の実生活を生きていけばいいんじゃないか”と、そういう監督のお気持ちを感じました。 |
| 山 田 |
そうね。確かににそういう思いってあるのよね。だって、みんな心配してるじゃないの。不安でしようがないじゃないの。銀行も
つぶれちゃうしね、会社もつぶれちゃうしね。だけどまあ、そんな心配してもキリがないよ。何とかなって行くんじゃないか、
という楽観主義を持ちたいと言う気がしますよね。 「何とかなるぞ!」というね。
もちろんそのためにはいろんな努力をしなくてはいけないけれども、それで打ちひしがれてしまってさ、なんとか生き残ろうという
消極的な考え方してたってなんにも生れないと思うからね。
「大丈夫だ、なんとかやって行けるぞ。そんなに捨てたもんじゃない」っていうかなぁ。
この国っていうかなぁ、僕たち日本人がねぇ。まあそういう言い方は非常に漠然としているけどもね。
それと…あんまり欲をかかなきゃいいんじゃないかな。 |
| 岡 村 |
そうですね(笑)。 |
| 山 田 |
僕たちは長い年月、この3、40年ひたすら欲望を抱くことが、この国を発展させるという大きな錯覚の中に生きてきたと
いうかなぁ。その欲望を抱くことをやめてみようかとね。…この映画の主人公たちはそうでしょうけどね。欲望を抱くということが、
恥かしいことだと考えていた時代の物語だからね。
今、僕たちは欲望を抱くことがつまり正しいという風に、いつの間にかこの国はなってしまっているからね。そのことの間違いに
気が付いてみると、何とかやっていけるんじゃないかな。ということにもなるような気がする訳だけどね。 |
| 岡 村 |
高度成長が終ったピークが万博の年だと、’70年代だと言われてますね。その年に僕の大好きな「家族」という映画がありまして、
万博の会場でロケをされた。
昔はつつましく生きることがたぶん戦前のある時期まではあったような感じがするんですね。自分の親なんかと話してると…。 |
| 山 田 |
ああ、あった。つつましさの美徳っていうのがね。 |
| 岡 村 |
「うちはこれでいいんだよ」みたいな。それが、「行け行けドンドン」になって、バブルになって、「もっともっと!」って…
いつの間にか、何が正しくて何が悪い事か、境目もわからなくなって尚且つもっと悪いのは、いつも「損か得か」で考えてしまう
ようになった。 |
| 山 田 |
本当にそうだね。 「なんとかして、なんぼ」っていう言い方が最近あるじゃないの。嫌な言い方だよね。ぜんぶ金銭に置き換えて
しまうというかね。そういう価値観こそ今、僕たちは疑ってかからなきゃいけないのに…。
’70年に「家族」を作ったけども、’69年に寅さんの第一作ができているんですよ。高度成長のピークのときに寅さんという
貧しい男が誕生してみんな大喜びしたっていうことは、一体何だろうか? ということも考えますよね、時々ね。ああいう無欲で
貧しくて何の肩書きもない寅さんをみんなが何故、愛するようになったか?ということですね。 |
| 岡 村 |
もしも、渥美清さんが今もお元気で寅さんが作られていたら、きっとみんな今も寅さんを支持された
と思うんですね。それはきっと、その…何か安心するんですね。とても寅さんが好きで、寅さんが好きな自分も好きなんですね。
|
| 山 田 |
安心するって大事なことですね。でも、その言葉はよく悪口として使われたの。
「寅さん」ってのは安心して観られる映画だ。だから良くない、だからつまらない、だから大したことないっていう、
そういう批評を聞くと僕はいつも思ったねぇ。どうしていけないのかなぁってね。安心できるってことはとても大事なことで…。
日本人は昔は「幸福」という言葉を使わなかったわけで…。
「安心」という言葉は仏教の言葉だからね。古くから「たそがれ清兵衛」の時代からあった言葉なんですね。シナリオ
を書きながら、「幸せ」という言葉を使うとこの時代らしくない。ましてや「幸福」という言葉はなかったはずなの。「幸せ」
という概念をどういう言い方に置き換えればいいかっていうんで、とても苦しみましたけどもね。「安心」だったら、この時代にも
使えるんですね。
安心できる人、その人の側に行くと何かホッとするっていうのかな、だから安心して生きている人がいて、その人の側に行くと自分
も安心できる。これはねぇ、わかりやすくて良い言葉ですよね。安心できる映画っていうのね。僕だったらそんな映画を観たいなぁ
と、そういう悪口を聞くだびに思ったものですよ。 |
| 岡 村 |
安心させて頂けるというのは、大変なことですよね。 |
| 山 田 |
うんうん。 |
| 岡 村 |
他の映画の悪口を言う気はないんですけどね。邦画を観ていますと作品によっては
“もうちょっと考えて作れば良かったのに…”というのが結構多いんですよね。
でも、この「たそがれ清兵衛」を観ていると本当に高い技術を持った職人さんが俳優さんも含めて、本当に高度なものを
作った、つまりちゃんとした日本家屋の中に入れて頂いた感じがするんです。 |
| 山 田 |
ああ、そういう意味での安心ね。それだと、僕が言った意味とはちょっと違うな。 |
| 岡 村 |
いや、作品自体の安心もそうなんですけれど。 |
| 山 田 |
なるほどね…。いつか筑紫哲也さんもそんな事を言っていたな。“いまの日本映画は安心して観る
ことができる映画が少ない。どういう意味かというと、何か途中で突然お粗末なことになっちゃう”って。 |
| 岡 村 |
そう、そうなんです。 |
| 山 田 |
突然ボロが出ちゃうみたいなね。そりゃ、低予算でみんなギリギリでやっていますからそういうこと
が起きてくるんだけども。確かにハリウッドの映画と比べれば、本当に何十分の一の予算なんだけど、精一杯できる限りちゃんとし
た作り方はしたつもりですよね。 |
| 岡 村 |
伯父さんの丹波哲郎さんがやってきて文句を言いますよね。
「お前はなってない。嫁をもらえ。 嫁なんて、尻が大きければいい、丈夫だったらいい。何、顔なんかあればいいん
だ」っていうところで爆笑したんですけれども…。
そこで清兵衛は穏やかに反論しますよね。「せっかくの伯父さんの言葉ですが、私は今の暮らしをそんなに悪いとは思っていない」。 |
| 山 田 |
そうそう。 |
| 岡 村 |
「子どもが大きくなるのを見ているのは農作物が大きくなるのを見ているように幸せな事でがんす」
というというところが…いいですねぇ。 |
| 山 田 |
そうだね。なるほどね。「伯父様が思っているほど、この生活は惨めだと私は思いません」という
反論は、確かに大事な台詞かもしれませんね。貧しいということは、自分が貧しいと思っているから貧しいんで、貧しくないと
思ったら貧しくないんですよね。 |
| 岡 村 |
そうですね。清兵衛は思ってませんね。 |
| 山 田 |
思ってないんです。そりゃ、飢えるということはよくありませんよ。あるいは凍えてしまうという
のは明らかにに良くないけれども。何とか食べて行けます、何とか冬もしのげますと。それで俺は我慢できるんだ、っていうかなぁ。
貧しくないと思っているという…。
それが清兵衛という人間だし、もしかしたらあの時代にはみんなそういう思いを抱いて日本人は生きていたのかなぁと思ったりも
しますけど。 |
| 岡 村 |
誰に言われたのか、親とかおじいちゃん、おばあちゃんに言われたのかもしれませんが、
そういう矜持ってどこかにあったと思うんですね。 |
| 山 田 |
うん、それはみんな残ってるでしょうね。どっかにね。 |
| 岡 村 |
寅さんもそうなんですが、山田さんの作品を拝見した後、いつもね…ちゃんとしたところに戻った
感じがするんですよ。「くるまや」かどこかわからないけれども。だから、観終わった後とても気持ちいいんですね。 |
| 山 田 |
「戻れる」っていうのはいい批評だなぁ。それをみんな探してて、もう一回そこから歩き出したら
違う道があるんじゃないのかなぁ、とね、どうも道に迷ってるじゃないですか、この国はね…
もっと広く人類って言っていいかもしれないね。
今のアメリカのブッシュなんかの発言を聞いているとね、とんでもないところに行っちゃってるという感じがする。もう一回みんなで戻りませんか?って言いたいとこだねぇ。そして、そこからもう一度検討しながら、歩き直そうという気持ちが確かに僕にはありますね。 |
| 岡 村 |
こんな事を監督に言ったら怒られるかもしれませんが、寅さんを昔から観ていて子どもの頃、「ああ、ああいう人いたよ」と思ってたんですね。でも、最後の方の何作かになってくると、「これはSFだよ!」って思っていました。「ああいう人は今はもう、世界中の何処にもいないんだ」って。 |
| 山 田 |
ああ、なるほどね。 |
| 岡 村 |
でも、素晴らしい人を観に皆さん映画館に行ってるし、僕もそれを観に行ってたんですけどね。
今度「たそがれ清兵衛」を拝見して、山田さんの描いてらっしゃる…ん〜、ちょっと杓子定規な言い方ですけど、
“僕が好きな日本人”を描いていこうとされると、もしもその舞台がもう葛飾柴又でないとすれば…これは山田
さんが時代劇に行くのは必然じゃないかなと思いましたね。 |
| 山 田 |
あ〜そうか。う〜ん、なるほどね。
そういう日本人、美しい日本人とでも言うかな。美しかった日本人とでも言うのかな。
「寅さん」に長い間、笠智衆さんが出ていたでしょう? 御前様でね。笠さんが演じてきた小津作品の中での
キャラクターっていうのは、僕たちが世界に誇るに足る日本の男だったんじゃないかなぁ、と思うのね。
つまり、つつましくて、あまり大きな欲望を抱かないで、その自分の身の丈に合った生活を満足して送ることができる、
そして、勤勉で実直で嘘を付かずに、ほとんど愚直と言っていいくらい生真面目で…。
僕はそんな笠さんがとても好きだったなぁ。あの人はもう本人がそういう性格でしたから本物なのね、これはね。 |
| 岡 村 |
いつだったか、監督のインタビューで笠さんにある芝居をつけようとしたら、言う前にもう、それをしてらっしゃった
という…。 |
| 山 田 |
まぁなんて言うかな、芝居をつける必要もないって言うかな。 |
| 岡 村 |
ご自身が…。 |
| 山 田 |
いるだけで、もうなんか…素敵なのね。 |
| 岡 村 |
そうですね。 |
| 山 田 |
あんな俳優は、今はもう日本どころか世界にもいないかもしれませんよ。 |
| 岡 村 |
……この「たそがれ清兵衛」は時代劇ですけれども、実は今のサラリーマンがグッと来る映画じゃないかと思って
いるんですね。リストラ、それから今の日本の中でいうと、家庭内暴力みたいなことが出てきて、首を切られると
言うか、クビになっていく宮仕えの人間の切なさみたいなのが痛いくらい特に後半に出て来ますよね。 |
|
 |
「たそがれ清兵衛」完成披露記者会見
2002.9.12 |
|
| 山 田 |
まあ、いつもそういう感覚を失わないでいようと思っていましたね。僕たちのこの国の宮仕え、サラリーマンも
お役人もそうだけども、その感覚っていうのは、この時代にすでに作られてきたんじゃないかなぁ、と。ずっと
それを引きずっていて、今日(こんにち)の会社に対する忠誠ということが、この時代に置き換えれば藩に対する
忠誠だったんだろうなぁ、と。だから、宮仕えの辛さとか切なさみたいなものは今の日本人もよく分ることだし、
それがどっかでこの画面から匂ってなければいけないという風にはいつも思ってましたけどね。
(間)
だから、そういう事ってあるなぁ、と共感する、特に清兵衛の勤務の日々ね、お蔵役人としての上役との関係とかね、
夜、「おい、帰りに一杯やらないか?」と言う感覚。あれは今のサラリーマンに近い感覚として撮るように努力
したつもりなんですね。 |
| 岡 村 |
実に今の日本のことを描いた映画だなと思いますね。 |
| 山 田 |
それから、やっぱり社長あるいは、そういう立場の人間がクビを言い渡すとき、やっぱり相当にすごいんじゃない
のかなぁ。僕は具体的な話を聞いたことがあるけどね。それは本当に過酷って言うか、絶対に同情しちゃいけない、
みたいなセオリーがあるみたいね。 |
| 岡 村 |
ええ。 |
| 山 田 |
どんなに可哀相な事であってもね、その同情を自分で「殺せ」と「抑えろ」と。そして一方的に過酷に言い渡せと、
なんかそんな話を聞いたことがあるけどね。 |
| 岡 村 |
切るほうも辛いですよね。 |
| 山 田 |
だからその辛さを自分で消してしまえ、って言うかな、つまり人間であることを辞めろということだねぇ。 |
| 岡 村 |
う〜ん…。 |
| 山 田 |
そうじゃなきゃ、クビになんか出来ないぞというね。まあそんなこともいろいろ考えながら、上役に命令される
シーンなんかね、撮ったもんですよ。 |
| 岡 村 |
「余吾を討て!」と、清兵衛が夜中に呼ばれていくわけですが、「返事はどうだ?」と訊いてはいるるものの、
もう「YES」としか言えない状況ですよね。 |
| 山 田 |
まあそうだね。 |
| 岡 村 |
あそこにもよく出てましたね、会社ってこうなんだみたいな。 |
| 山 田 |
お前の部から5人首を切れと言われた時に、「いえ、お断りします」と言ったら彼も辞めなきゃいけなくなる。
だいたい、それが今の会社の形じゃないの? 「だったら、君も辞めてもらうぞ」という……大変ですよね、
勤め人はねぇ。 |
| 岡 村 |
そんなことを考えると、僕も深読みが好きな人間なんで、ずうっと昨日から考えていたんですが、もしかすると
清兵衛と余吾というのは、ある一人の人間のような気がしてきたんですね。 |
| 山 田 |
なぁるほど。 |
| 岡 村 |
清兵衛はある意味で運があった、藩の中で。余吾は「何も悪いことしてないのに、何で俺がこんな目に合うんだ!」
って事になる。それを二人の人間が演じたんじゃないかと思いましたね。 |
| 山 田 |
なるほどね。それは、だって寅とさくらだってひとりの人間と言えるんですよ。 |
| 岡 村 |
そうですね。 |
| 山 田 |
「真面目にいかなきゃいけないんだ、地道に。人生なんてそんな面白い事ばっかりあるもんじゃないし」って考える
部分が人間には誰にでもあるし、同時に「そんなのちっとも面白くないぞ!」と好き勝手にやって行きたいと思う
気持ちだって一人の人間の中にあるわけですからねぇ。その二人がしょっちゅう喧嘩してる、喧嘩しながら愛し
合っている、というのが一人の人間の心の中の状態でもあるんじゃないのかしら。 |
| 岡 村 |
役者さんの話をしたいんですけれどね。余吾の役をやられた田中泯さん。この方が実に素晴らしい。
このキャスティングというのがすごいと思いました。 |
| 山 田 |
僕もうまく当たったなぁ、と思ってますね。よかった、本当に。 |
| 岡 村 |
知らない方は「誰だろう?」と、顔もあまり写らないしね。 |
| 山 田 |
大部分の人がそう思うんじゃない? あの人、どういう人だろうなんてね。 |
| 岡 村 |
世界的な舞踏家でいらっしゃいますけれど。 |
| 山 田 |
舞踏って言うのは、あくまで舞台の上の芸術であって、顔をしげしげとみんな知ってる訳じゃないし。 |
| 岡 村 |
泯さんは、僕は最初、殺陣の専門家かな?と思ったんですよ。知らなくてね。 |
| 山 田 |
ああそうか。 |
| 岡 村 |
真田さんはもう殺陣が出来ることはよく知ってるんですけども。この映画は二つ殺陣のシーンがあるんですが、
これがちょっと今まで観た時代劇のいわゆる…。
僕は殺陣というのは踊りだなと思っているんですけどね。まあ、形なんですね。 |
| 山 田 |
まあそうだったね。 |
| 岡 村 |
ほとんどの映画がね。今回はそれと全然違っていて、映画、観ててよけましたね、刀を。
なんか恐かった! |
| 山 田 |
いや、すごい殺陣のシーンに挑戦しようと考えたんじゃなくて、今までの殺陣の中でほら、おかしいと思うところ
があるじゃないですか? |
| 岡 村 |
ええ。 |
| 山 田 |
何故そうなんだっていう、 そういうところをやめていくっていうかなぁ。
パッと斬って、ヤッと構えて、ひと間おいて次の型・次の太刀になるときに、ひと間おかないで何で行けないのだろうか
?とかね。そういう疑問を次々と提出しながらそれを殺陣師とか剣道の先生が、だったらこういうことがあるかと
か、ああいうことがあるかとかまあ、基本的にはそういうことですよね。 |
| 岡 村 |
この映画を作るにあたって、スタンリー・キューブリック監督の「バリーリンドン」をご覧になったと伺ったんです
が、どんなところが参考になりましたか? |
| 山 田 |
「バリーリンドン」も鉄砲の対決がクライマックスであってね。
全体の17・8分くらいなんだけど、彼がどれぐらいの長さで間合いをとって、それだけ長い決闘をどんなふうに演出
してるのかなあって、繰り返し観てみたわけ。なかなかみごとなシーンなんだけれども、ピストルっていうのは
一発でおしまいじゃない?
撃つまでを延々と持たせなきゃいけない。 |
| 岡 村 |
緊張感ですね。 |
| 山 田 |
緊張感をね。 だけど、刀の場合にそうじゃない。何度も何度も斬り合って斬り合ってお互い、あちこちから血が
出て血が出て、まだ続けられるという…。 |
| 岡 村 |
体力勝負ですよね。 |
| 山 田 |
だから、はるかにこっちの方が有利だなと、刀の方が演出的にはね。
「バリーリンドン」では最終的には一発で決まる。それを17分もまあみごとな演出で持たしているならば、僕は
もっと安心して演出していいんだろうと思ったのね。だから、この映画はどっちかって言えば、一番参考になった
のが「シェーン」だったねぇ。 |
| 岡 村 |
「シェーン」!? |
| 山 田 |
うん。 「シェーン」の最後の撃ち合いっていうのが、従来のあるパターンから外れてるもんであってねぇ。
「シェーン」が描こうとしたのは、決してそのピストルの撃ち合いじゃなくて、シェーンとあの家族・少年を中心
にした情愛だったのね。その辺りがあの映画が他の西部劇と全然違うところだったかな、と思っていたもんでね。
あれはどっちかと言うとあんな映画かな、と思ってましたね。 |
| 岡 村 |
あっ、「遥かなる山の呼び声」という作品もありましたね。 |
| 山 田 |
あれは、一種のオマージュみたいなものでしたね。 |
| 岡 村 |
さて、寅さんの話をしながら「たそがれ清兵衛」の話をさせて頂くと、「たそがれ清兵衛」の中には、もちろん
寅さんも御前様も出て来ないんですけれど、一人だけ出て来た人がいるんですよ。神戸(浩)ちゃん! |
| 山 田 |
ああ、神戸ねぇ。 |
| 岡 村 |
神戸ちゃんね、僕は名古屋出身なんで、良く知ってるんですよ、昔っから。 |
| 山 田 |
ああ、そう。 |
| 岡 村 |
それでね、「源公には会えたな」と思ってるんですよ(笑) 佐藤蛾次郎さんには。 |
| 山 田 |
ハッハッハッハッ… ああ、なるほどねぇ。 |
| 岡 村 |
うれしくって。 |
| 山 田 |
まあ、そんな事、考えてもいなかったけどもね。 |
| 岡 村 |
しかもね、ストーリー言ってあれですけれども、これからご覧になる方には…。
非常に緊張感のあるところで伝言をしに行くわけですね(笑)。 そこでちゃんと言えるかどうかが不安で、僕、一緒に
なって唱えてましたもん。 |
| 山 田 |
なるほどねぇ(笑)。 |
| 岡 村 |
とてもいい、うれしい存在でしたね。 |
| 山 田 |
そうね、神戸くんの存在って言うのはなかなか大事だったかもしれませんね。
ま、あそこでちょっと観客は少しホカホカした気持ちになれるところはあるわな、確かになぁ。 |
| 岡 村 |
それもまた、これから大変なことが起こるっていうところだから、よけいにね。いいですね。
さて、先ほど山田さんが時代劇に来たのは必然と申し上げたのですが、以前に何かの本で読んだんです。 三船敏郎さんで「その後の武蔵」を撮るっていう話がありましたね。 |
| 山 田 |
そうそうそうそう。 |
| 岡 村 |
それは実現しませんでしたけれども、この後、山田洋次さんの作品はどういう風な展開になって行くのでしょう? すごく興味があるんですけども。 |
| 山 田 |
なかなか、決まらなくてね。この映画撮っているときはね、もし僕がこの次撮るならタッチの違うものを撮ろうと
思っていましたけどね。今はね、タッチの違うものは何かっていうのもあるんですけれども、ある素材があってね、
もっと現実をそのまま捉えて行くという、とっちかというとセミドキュメンタリータッチの作品をね。
 |
「たそがれ清兵衛」撮影中の山田監督
(DVDボックスより) |
時代劇というのは全部作り上げていかなきゃいけないから、現実をジッと見つめてその中から何か発見するということが
まずあり得ないわけでしょう?
そういう意味でね、対極にあるようなタッチ、その手法の映画を作りたいというのがひとつあったんだけれども、
今考えてるのは。いつも両方、二つや三つ並行しながら最終的にある結論に達するんだけども…。
まあ、あなたもさっきからそうおっしゃってるけども、せっかく時代劇という鉱脈、あるいは藤沢周平という鉱脈
を掘り当てたってことが言えないかと。とすればね、それをみすみす放っておく手はないだろう。つまり具体的に
言えば、京都のスタッフと一緒に仕事してみんなもかなり今度は頑張って、今までやらなかったような事を沢山考
え出したり…とすれば、そこは一つの工場なわけでノウハウが財産として残っているわけですよねぇ。
それをそのままにするのはもったいないって気もする訳ね。あるいはそのまま結局、ある年月の中に消えて行っ
ちゃうのももったいないという気もするしね。僕もいろんなこと勉強したりしたことがあってね、そういう意味
じゃねぇ、もう一度時代劇をやってみるということもありかなぁと。 ハッハッハッハッ…。
|
| 岡 村 |
そうですか。いや〜もう是非。
実は今日ね、11月11日なんですけれども、淀川長治さんのご命日なんですね。 |
| 山 田 |
ああ、そうかそうか。 |
| 岡 村 |
淀川先生がもしご覧になったら「あんた、もう一本時代劇撮りなさいよ!」とおっしゃるんじゃないかなぁと勝手
に思ったりしてるんですけども(笑)。 |
| 山 田 |
言いますかねぇ? |
| 岡 村 |
と、思いますね。 もう一本観たいですね。
どういうのかなあ、ちょっと見終わって幸せになれる映画。最後に累々と屍が並んでいるような映画ではなくてね。 |
| 山 田 |
そう、最後に首斬られて死んじゃうような話じゃなくてね。まあ、「この人生は生きるに値するんだ」という風に
観客がなんとなく反芻しながらそういう思いを持ってね、小屋を出て行くっていうかねぇ。
ついこの間ね、一昨日か、徳島県に脇町って言う町があるんですね。僕は「虹をつかむ男」でそこの…。 |
| 岡 村 |
映画館のあったところですね。 |
| 山 田 |
あの映画を記念して、リニューアルしてもう一度全部新しくした。新しくしたといっても元の通りに復元して芝居
小屋を作って、花道があって全部桟敷で座布団置いて、そこでどうしても僕の「たそがれ清兵衛」をやりたいって。
ただね、僕たちには条件があると。それは、完璧な音・完璧なスクリーンじゃなきゃこの映画はやらないと。300
人入ったら、もう超満員になるような、二階も入れて600人以上入らない劇場。そこで完璧な映写をするためには
東京から5人のスタッフが行って機材をそこに運び込んで、スピーカーを7つも8つもスクリーンも全部持って行か
なきゃいけないでしょ。とても合わないんですよね。
それで町が町の行事として捉えようという事でかなり援助してくれたんじゃないのかなぁ。ひとつの大きなイベント
として、「たそがれ清兵衛」上映会。オデオン座って言うんですけどね(笑) やったのね。
それで、みんなびっくりしたみたい。映画ってこんなに綺麗で、こんなにすごい音がするのかと、その脇町の人達が。
一回、上映が終ってみんな表に出て来るでしょう?
そうするとね、映画館の前がちょっと広場になってるのね。そこにいっぱいの人がワイワイいてね。 「あ〜ら、あんた来てたの?」なんてね。その情景を見ててね、ああ、いいなぁと思ったねぇ。
つまり、映画を観るってそういうことなんだなぁと。観終わってそこでいろんな人と会ったりね。「どう、お蕎麦でも食べようか」とか「コーヒー飲もうか」とか…とっても、その情景がね僕…懐かしい景色を見たような気がしたなぁ。
大事件だな、脇町はな。シンフォニーのコンサートをやるような感じみたいだなぁ、あれはなぁ。
|
| 岡 村 |
きっとその時間は脇町の方には素晴らしい想い出になったんでしょうね。 |
| 山 田 |
そうだなぁ…そうですねぇ。 |
| 岡 村 |
私からのお願いですけれども、是非もう一本時代劇を松竹・京都で。 |
| 山 田 |
その時に…そうなんですよ、司会した人がいてね。
「みなさんもう一本、時代劇観たいと思いますか?山田監督の」って言ったら、みんなが「わぁー」って拍手してくれたのね。その脇町の人達、お年寄りも子ども達もいたけれども、とても嬉しかったですね。ああ、この人達またきっと観てくれるだろうと、今度やればね。うふふ…。 |
| 岡 村 |
少しずつ、時代劇のファンも増えて来るといいですね。 |
| 山 田 |
そうですね。 |
| 岡 村 |
今日は、映画「たそがれ清兵衛」の監督でいらっしゃいます山田洋次さんにいろいろと伺いました。
どうも本当にありがとうございました。 |
| 山 田 |
はい。いえ、いえ…。 |
| 岡 村 |
ありがとうがんす! |
| 山 田 |
ハッハッハッハッ…。 |
|
(了) |


![]()
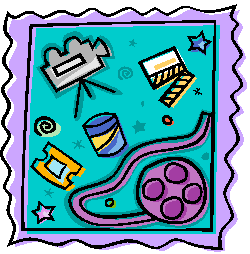
![]()