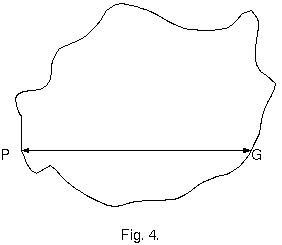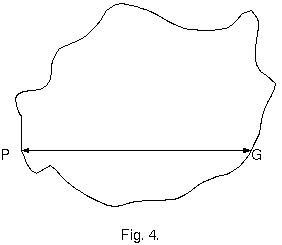≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
一般相対性の理論
全ての以前の考察は、全ての慣性系は物理現象の記述において等価であるが、それらは、異なる運動状態の参照空間からは、
自然法則の定式化において、選別されているという仮定に基づいていた。
我々は、確定的な運動状態を他から選別することには、我々の以前の考察に従えば、知覚し得る物体のなかにも、運動の概念
のなかにも、理由がないと考えることができる;反対に、それは、時空連続体の特性からは独立であるとみなさなければならない。
慣性の原理は、とくに物理的に客観的な特性を時空連続体に帰することを我々に強制するようにみえる。
それは、ちょうどニュートン的な立場からは、時間は絶対的である と、空間は絶対的である、というふたつの
言明を作ることが整合していたように、特殊相対論の立場からは、 時空の連続体は絶対である、と言わなければならない。
この後者の言明のなかで、絶対的とは、"物理的現実"であるということを意味するだけでなく、
"その物理特性のなかに独立であって、物理的に効果を与え、物理的状態からはそれ自身が影響を受けない"ことを意味する。
慣性の原理を物理の要石とみなす限り、この立場は、確かに正当化される唯一のものである。しかし、普通概念のふたつの深刻な批判が存在する。
第1番目には、それは、それ自身作用するが、作用されることのない、あること(時空連続体)を思考する科学の思想の様式に反している。
これが、E.マッハ(Mach) が力学のシステムにおいて、空間を作用の原因として除去しようと試みをすることを導いた理由である。
彼に従えば、物質粒子は、非加速的な運動を空間に相対してするのではなく、宇宙の他の全ての質量の中心に相対してする;
この方法で、ニュートンとガリレオの力学に対比して、力学的な現象の原因の系列は閉じられる。
媒体を通した作用の現代理論の制限のなかにおいて、この概念を開発するために、慣性を決定する時空連続体の特性が、電磁場に類似する
空間の場の特性と見なされなければならない。古典力学の概念は、これを表現する方法を与えない。この理由のため、その解として
E.マッハの試みは、現在の所、失敗している。我々は、後にこの観点に戻って来るだろう。
第 2 番目として、古典力学は、互いに非均一な運動をする参照空間への相対性の原理の拡張を直接に求める欠乏症を呈している。2物体の
質量比は、力学では互いに基本的に異なるふたつの方法によって定義された;最初には、それらの間に同じ動機の力が与えられるときの互い
の加速の比として(慣性質量)、次には、同じ重力場のなかでそれらに作用する力の比として(重力質量)。
全く異なって定義された、これらふたつの質量の等価性は、事実、非常に高い精度の実験によって確認された(エトベッシュ(Eötvös)実験)
が、古典力学は、この等価性に何も説明を提供しない。しかしながら、この数値的一致がこれらふたつの概念の現実の性質の等価性に
還元され割り振られた後にだけ、科学は正当性を完全にすることは明らかである。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
この目的が実際に相対性の原理の拡張によって達成され得ることは、次の考察から来る。少しの考察によって、慣性と重力質量の等価性は、
物体が重力場によって与えられた加速が物体の性質に依らないことと等価であることが示される。なぜなら、重力場のなかのニュートンの
運動方程式は、完全に書き下せば、次になる。
(慣性質量)・(加速)= (重力場の強さ)・(重力質量)
加速が物体の性質から独立であることは、慣性と重力質量の間に数値的一致があるときだけである。いま、$K$ を慣性系としよう、
互いにまた他の物体から十分遠い質量は、そのとき、$K$ に関して加速から解放されている。我々はまた、これらの質量を、$K$ に関して
均一に加速している座標系 $K'$ に参照させる。$K'$ に相対的には、全ての質量は等しく平行な加速をもつ; $K'$ に関しては、それらは、
あたかも、重力場が存在し、$K'$ が加速されていないかのように行動する。
いまのところ、そのような重力の "原因" についての問いを俯瞰すれば、それは後に我々を占有するだろうが、この重力場が現実のもの
であると我々が考えることを妨げるものはない。すなわち、$K'$ が "静止" していて、重力場が存在するという考えは、$K$ だけが "許される"
座標系であって重力場はないという考えと同等に考え得るものである。
座標系 $K$ と $K'$ の完全な物理的等価性の仮定を、我々は "等価性の原理" と呼ぶ。この原理は、明らかに、慣性と重力質量の同等性の法則
に深く結合していて、互いに非均一的運動をする座標系への相対性の原理の拡張を意味している。
事実、この概念を通して、我々は、慣性と重力の性質の統合に到着する。なぜなら、それを見る我々の方法に従えば、同じ質量が慣性だけ
の作用のもとにある($K$に関して)、又は慣性と重力の結合した作用のもとにある($K'$に関して)、のいずれとも表れることができるからである。
慣性と重力のそれらの性質の統合によって数値的な等価性を説明できる可能性は、私の信ずるところによれば、遭遇する全ての困難も、
この進歩と比較すれば小さいと考えなければならないような、そのような古典力学の概念に対する優越性を相対性の一般理論に与える。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
我々が、全ての他の座標系の上に慣性系に選別を付与するとき、経験によって非常に安全に確立されたようにみえる優先であることを
何が正当化するのだろうか? 慣性の原理の弱点は、それが循環論法を含むことにある:質量は加速なしに運動する、もし、それが他の物体
から十分に遠ければ;我々は、それが他の物体から十分に遠いことを、それが加速なしに運動する事実だけによって知る。
時空連続体の非常に拡がった部分、又は、実に、宇宙全体において、そもそも、何か慣性系が存在するのだろうか。
我々は、慣性の原理が近似の高い程度に、我々の惑星系の空間に確立しているとみなしてよい。もし我々が太陽と惑星による擾乱を無視
するならば。より正確にいえば、有限の領域があって、そこで適切に選ばれた参照空間に関して、物質粒子は加速なしに自由運動し、
そして、そのなかで上で開発された特殊相対論の法則が、注目すべき正確さをもって成立する。そのような領域を我々は "ガリレイ領域"
と呼ぶ。我々は、知られた特性の特別な場合として、そのような領域を考察することから進もう。
等価原理は、ガリレイ領域を扱うのに、我々が等しく非慣性系、すなわち、慣性系に相対して加速と回転から自由でないような座標系、
を使用してよいことを要求する。もし、我々が、さらに、ある座標系への選別に客観的な理由についてのいらいらする問いから完全に
離れようとするなら、そのときは、我々は、任意に運動する座標系の使用を許さなければならない。この試みを真面目にしようとする
とすぐに、我々は、特殊相対論によって我々がそこに導かれた時間と空間のあの物理的解釈との相克に出会うことになる。
なぜなら、$K'$ をその z'軸が $K$ の z 軸と一致して、後者の軸の周りに一定の角速度で回転している座標系としよう。$K'$に相対的に静止
する剛体の構成は、ユークリッド幾何学の法則に従うだろうか? 一方、$K'$は慣性系ではないので $K'$ に関する剛体の構成の法則を、また、
自然法則一般についても、我々は、直接には知らない。しかし、我々は、慣性系 $K$ に関して、これらの法則を知っている。そして我々は、
それゆえ、$K'$に関しての式を推定できる。 $K'$ の $x'y'$ 平面の原点の周りに円とこの円の直径を描くことを想像しよう。さらに、我々が
互いに等しい多数の剛体棒を与えられていると想像しよう。我々は、これらを $K'$ に相対的に静止している円の円周と直径にそって順次
直列に並べることを想定する。もし、$U$ を円周にそったこれらの棒の数、$D$ を直径にそった数とすると、そのとき、もし、$K'$ が $K$ に相対的に
回転していないなら、我々は次をもつ。
\[
{U \over D} = π
\]
しかし、もし、$K$' が回転するなら我々は違う結果を得る。$K$ の確定した時間 t において我々は全ての棒の端を決定することを考えよう。
$K$ に関して、円周上の全ての棒は、ローレンツ短縮を経験する。しかし、直径上の棒は、この短縮(それらの長さにそった!)を経験しない。
それゆえ、次式が出てくる。
\[
{U \over D} > π
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
それゆえ、$K'$に関する剛体の構成の法則は、ユークリッド幾何学に合致する剛体の構成法則とは一致しないことが分かる。もし、さらに、
我々がふたつの類似する時計($K'$と共に回転する)をひとつは円周に、他は円の中心に置くならば、そのとき、$K$ から判断して、円周上の時計は、
中心の時計よりもゆっくりと進行する。もし、同じことが $K'$ から判断しても実行されなければならないなら、我々が $K'$ に関して、全体
として不自然な方法で (すなわち、$K'$ に関して時間に明示的に依存する法則のような方法で)、時間を定義しなければならない(*訳注)。
それゆえ、$K'$ に関する空間と時間は、慣性系に関する特殊相対論のようには定義できない。しかし、等価性の原理に従って、$K'$は、それに
関して重力場 (遠心力とコリオリの力の場)がある静止系とみることができる。我々は、それゆえ、次の結果に到達する:重力場は、
時空連続体の計量の法則に影響し、それを決定しさえする。理想的剛体の構成の法則を幾何学的に表現するなら、重力場の存在があれば、
幾何学はユークリッド的でない。
我々が考察してきた場合は、表面の2次元的扱いで説明した場合と類似する。後者もまた、単純な計量的意味をもつ表面(例えば楕円体の表面)
の座標系を導入することは、不可能である。一方、平面上でデカルト座標、$x_1, x_2$ は、単位測定棒によって測られた長さを直接に意味する。
ガウスは、彼の表面の理論のなかで、この困難を乗り越えた。連続の条件を満たす以外は全く任意な曲線座標を導入し、そして、その後にだけ、
これらの座標値が表面の計量的特性に関係しているとすることによって。
類似の方法によって、我々は、一般相対論に任意の座標値、$x_1, x_2, x_3, x_4$ を導入する、時空点を一意に数値化し、隣接する事象が隣接
する座標値に関連する;それ以外、座標値の選択は任意である。もし我々が、そのようなどの4次元座標系にも有効である形式を法則に与える
なら、すなわち、法則を表現する方程式が任意の変換に関して共変であるなら、我々は、その最も広い意味において相対性の原理に忠実である。
(*訳注)この文を意訳。原英文: "もし、我々が $K'$ に関して、全体として不自然な方法で (すなわち、$K'$に関して時間に明示的に
依存する法則のような方法で)、時間を定義しなければ、同じことが $K'$ から判断しても実行されなければならない。"
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
ガウスの表面の理論と一般相対論との最も重要な接点は、両方の理論の概念が主に基礎とする計量の特性にある。表面の理論の場合、ガウス
の議論は次のようである。平面の幾何学は、無限に近傍する2点間の距離 $ds$ の概念に基くことができる。この距離の概念は、剛体の測定棒
の手段で直接に測定できるから物理的意味をもつ。デカルト座標の適切な選択によって、この距離は、式 $ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2$ によって
表現できる。我々は、その上にユークリッド平面幾何学を築く諸概念、測地線 ($δ∫ds= 0$) としての直線、間隔、円、そして角度をこの量に
基づくことができる。ひとつの幾何学を、もうひとつの連続的に曲がった表面の上に開発できる、もし、我々が観察して、表面の無限小の領域を、
平面と同様に、相対的に無限小の量とともにあるとみなすことができるなら。表面のそのような小領域の上にデカルト座標 $X_1, X_2$ があって、
測定棒で測定される2点間の距離が次によって与えられる。
\[
ds^2 = dX_1^2 + dX_2^2
\]
もし、我々が任意の曲線座標値 $x_1, x_2$ をその表面に導入するなら、そのとき、$dX_1, dX_2$ は $dx_1, dx_2$ によって線形に表現できる。
そのとき、表面のどこにおいても、我々は次の式をもつ。
\[
ds^2 = g_{11} dx_1^2 + 2 g_{12} dx_1 dx_2 + g_{22} dx_2^2
\]
ここで、$g_{11}, g_{12}, g_{22}$ は、表面の性質と座標の選択によって決定される; もし、これらの量を知るなら、そのとき、その表面上に
どのように剛体棒の網の目が敷かれ得るかをも知るのである。言葉を替えれば、表面の幾何は、$ds^2$ のこの表式に基づくことができ、
それは、平面幾何が対応する表式に基づくのと正確に同様である。
物理学の4次元時空連続体のなかに類似の関係がある。重力場のなかで自由落下する観測者の直近傍において、重力場は存在しない。
我々は、それゆえ、つねに、時空連続体の無限小の領域をガリレイ的とみることができる。そのような無限小領域には、それを参照すれば、
特殊相対論の法則が有効であると我々がみなすべき、慣性系(空間座標 $X_1, X_2, X_3$ と時間座標 $X_4$ をもつ)が存在する。
我々の単位測定棒と時計によって直接に測定可能な量、
\[
dX_1^2 + dX_2^2 + dX_3^2 - dX_4^2
\]
または、その負の、
\[
ds^2= - dX_1^2 - dX_2^2 - dX_3^2 + dX_4^2
\tag{54}
\]
は、それゆえ、ふたつの隣接する事象(4次元連続体のなかの点)に対する一意に決定される不変量である。持ち寄り重ねるとき互いに等しい
測定棒と、持ち寄るときその速度の等しい時計とを、我々が使用するならばである。このなかには、ふたつの測定棒の相対的な長さ、ふたつの
時計の相対的な速度は、それらの以前の履歴から原理的に独立である、という物理的な仮定が不可欠である。しかし、この仮定は、確かに経験
によって保証されている;もし、それが成立しなければ、鋭いスペクトル線はあり得ないだろう。なぜなら、同じ元素の単独原子は、確かに同
じ履歴を持たない。そしてなぜなら、ー単独原子の以前の履歴に依存する相対的可変性を仮定してーこれら原子の質量または固有の周波数が
かつてずっと互いに等しかったと想定することは理屈に合わない。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
有限の拡がりの時空領域は、一般にガリレイ的でなく、そのため、重力場は、有限の領域で座標系をどのように選択しても除去できない。
有限領域に、特殊相対論の計量的関係が成立するための、座標系の選択は、それゆえ、存在しない。しかし、連続体の近接2点(事象)には
不変量 $ds$ はつねに存在する。この不変量 $ds$ は、任意の座標系のなかで表現できる。もし、人が局所の $dX_ν$ が座標の微分 $dx_ν$ に
よって線形に表現できるとみるなら、 $ds^2$ は、次式に表現できる。
\[
ds^2 = g_{μν} dx_μ dx_ν
\tag{55}
\]
関数 $g_{μν}$ は、任意に選択された座標系に関して、時空連続体の計量関係、そしてまた重力場をも記述する。特殊相対論におけると同じく、
我々は、4次元連続体のなかで、時間性と空間性の線要素を区別しなければならない; 導入された符号の変化のために、時間性の線要素は実数の、
空間性の線要素は虚数の $ds$ をもつ。時間性の $ds$ は、適切に選ばれた時計によって直接に測定することができる。
以上述べたことに従って、一般相対論の定式化には、不変量の理論とテンソルの理論の一般化が必要であることが明らかである; 任意の点変換
に関して共変である方程式の形成についての問いが持ちあがる。テンソルの一般化された計算は、相対論よりもずっと以前に数学者達によって
開発された。リーマン (Riemann) は、ガウス (Gauss) の任意次元の連続体の一連の考察を最初に拡張した; 予言的視点をもって、ユークリッド
(Euclid) 幾何学の一般化の物理的な意味を見た。そして、とくにリッチ(Ricci) とレビ・チビタ(Levi-Civita) とによって、テンソルの計算の
形式での理論の開発が続いた。ここで、このテンソル計算の最も重要な数学的な概念と演算を短く提示する。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
我々は、任意の座標系に関する $x_ν$の関数として定義された 4つの量を、ひとつの反変ベクトルの成分 $A^ν$ と呼ぶ、
もしそれらが、座標値の変化において、座標微分 $dx_ν$ と同じく変換されるならば。我々は、それゆえ、次をもつ。
\[
A'^μ={∂x'_μ \over ∂x_ν} A^ν
\tag{56}
\]
これら反変ベクトル以外に、共変ベクトルも存在する。もし、$B_ν$ が共変ベクトルの成分なら、これらのベクトルは、
次の規則に従って変換される。
\[
B'_μ= {∂x_ν \over ∂x'_μ} B_ν
\tag{57}
\]
共変ベクトルの定義は、共変と反変ベクトルがともに、次の方式に従って、スカラーを形成することによる方法も選択できる。
\[
Φ= B_ν A^ν (νに渡って総和する).
\]
なぜなら、我々は次をもつから。
\[
B'_ν A'^ν = {∂x_α \over ∂x'_μ}{∂x'_μ \over ∂x_β} B_α A^β = B_α A^α
\]
とくに、スカラー$Φ$の微分 ${∂Φ \over ∂x_α}$ は、共変ベクトルの成分であり、座標微分とともに、スカラー ${∂Φ \over ∂x_α} dx_α$ を形成する;
この例から、我々は、共変ベクトルの定義がどれほど自然であるかを見る。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
ここにまた、任意の階数のテンソルがあり、共変または反変の性質を各添字に関してもつ; ベクトルと同様に、添字の位置によってその性質が記述される。
例えば、$A_μ^ν$ は、2階のテンソルを示し、添字$μ$について共変、添字$ν$について反変である。テンソルの性質は、変換の式が次であることを示す。
\[
A_μ^{ν'}= {∂x_α \over ∂x'_μ} {∂x'_ν \over ∂x_β} A_α^β
\tag{58}
\]
テンソルは、線形直交変換の不変量理論と同様に、同じ階数の同種の性質のテンソルの加算と減算によって形成できる。例えば、
\[
A_μ^ν + B_μ^ν = C_μ^ν
\tag{59}
\]
$C_μ^ν$ のテンソルの性質は、(58)によって証明される。
テンソルは、線形直交変換の不変量理論と同様に、添字の性質を保存して、乗算によっても形成できる。例えば、
\[
A_μ^ν B_{στ} = C^ν_{μστ}
\tag{60}
\]
証明は、変換の規則から直接に出てくる。
テンソルは、異なる性質のふたつの添字に関する縮約によって形成できる。例えば、
\[
A^μ_{μστ}= B_{στ}
\tag{61}
\]
$A^μ_{μστ}$のテンソル性質は、$B_{στ}$ のテンソル特性を決定する。証明ー
\[
A^{μ'}_{μστ}
= {∂x_α \over ∂x'_μ}{∂x'_μ \over ∂x_β}{∂x_δ \over ∂x'_σ} {∂x_t \over ∂x'_τ} A^β_{αδt}
= {∂ x_δ \over ∂x'_σ} {∂x_t \over ∂x'_τ} A^α_{αδt}
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
同種の性質のふたつの添字に関するテンソルの対称と反対称の特性は、特殊相対論においてと同じ意味をもつ。
これによって、テンソルの代数的な特性に対する全ての本質的なことは、言い終えた。
基本テンソル $dx_ν$ の任意選択における $ds^2$ の不変性から、(55)に整合する対称性の条件と関連して、 $g_{μν}$ が
対称共変テンソル(基本テンソル)の成分であることが出る。様々な $g_{μν}$に対応して $g_{μν}$ の行列式 $g$ を作り、そしてまた、
余因子を $g$ で割ろう。これら余因子を $g$ で割ったものは、$g^{μν}$ で記述し、そして、その共変の性質は、まだ知られていない。
そのとき、我々は、次をもつ。
\[
g_{μα} g^{μβ}= δ_α^β= 1 (if α=β), 0 (if α≠β)
\tag{62}
\]
もし、我々が無限小の量(共変ベクトル)を形成するなら、
\[
dξ_μ= g_{μα} dx_α
\tag{63}
\]
$g^{μβ}$を掛け、$μ$に渡り総和して、(62)を使って、次を得る。
\[
dx_β= g^{βμ} dξ_μ
\tag{64}
\]
$dξ_μ$の比は任意であるから、そして、$dx_β$ も $dξ_μ$ と同様にベクトルの成分であるから、$g^{μν}$ は、反変テンソルの成分(*)
(反変基本テンソル)であることが出てくる。δ_α^β (混合基本テンソル)のテンソル性質は、それゆえ、(62)によって続いてくる。
我々は、基本テンソルによって、共変添字の性質のテンソルの代わりに、反変添字性質のテンソルを導入したり、その逆もできる。例えば、
\[
A^μ= g^{μα} A_α \\
A_μ= g_{μα} A^α \\
T^σ_μ= g^{σν} T_{μν}
\]
(*) もし、我々が (64)に$∂x'_α \over ∂x_β$を掛け、$β$に渡り総和し、$dξ_μ$をアクセント付きの系に変換することによって置き換えるなら、次を得る。
\[
dx'_α= {∂x'_σ \over ∂x_μ} {∂x'_α \over ∂x_β} g^{μβ} dξ'_σ
\]
上でなされた言明は、これから出る。なぜなら、(64)によって、我々はまた $dx'_α= g^{σα'} dξ'_σ$ を持たねばならず、両式は、
どの $dξ'_σ$ の選択にも成立しなければならないからである。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
体積不変量 体積要素、
\[
∫dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 = dx
\]
は、不変量ではない。なぜなら、ヤコビ(Jacobi)の定理によって、
\[
dx'= |{dx'_μ \over dx_ν}| dx
\tag{65}
\]
しかし、我々は、$dx$ を補正して不変量にすることができる。もし、我々がその量の行列式を形成するなら、
\[
g'_{μν}= {∂x_α \over ∂x'_μ} {∂x_β \over ∂x'_ν} g_{αβ}
\]
我々は、行列式の乗算の定理を2回適用して、次を得る。
\[
g'= |g'_{μν}| = |{∂x_ν \over ∂x'_μ}|^2 . |g_{μν}| = |{∂x'_μ \over x_ν}|^{-2} g
\]
我々は、それゆえ、次の不変量を得る。
\[
\sqrt{g'} dx' = \sqrt{g} dx
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
微分によるテンソル形成 テンソルの形成の代数的演算は、線形直交変換に関する不変量の特別な場合に単純であることが証明
されているにも関わらず、一般の場合、不変量の微分演算は、不幸にも、かなりより複雑である。この理由を次に示す。
もし、$A^μ$ が反変ベクトルであり、その変換係数、${∂x'_μ \over ∂x_ν}$ は、変換が線形であるときにだけ、場所によらない。そのときは、
ベクトル成分 $A^μ + {∂A^μ \over ∂x_α} dx_α$ は、近傍点で $A^μ$ と同様の方法で変換する。そこから、ベクトル微分のベクトルの性質と、
${∂A^μ \over ∂x_α}$のテンソルの性質が出てくる。しかし、もし、${∂x'_μ \over ∂x_ν}$ が変数ならば、これはもはや真でない。
それにも関わらず、一般の場合のテンソルの不変量の微分演算は、最も満足に認識される、次の方法でレビ・チビタ(Levi-Civita)とワイル(Weyl)
によって導入された。($A^μ$) を反変ベクトルとし、その成分が、$x_ν$ の座標系に関して与えられているとしよう。$P_1$ と $P_2$ を、
連続体のふたつの無限近傍点とする。点 $P_1$ を囲む無限小領域にとって、質量を考慮する我々の方法に従って、それに関して連続体が
ユークリッド的な $X_ν$ の座標系 (虚数の $X_4$ 座標をもつ) が存在する。$A^μ_{(1)}$ を点 $P_1$ でのそのベクトルの座標値としよう。点 $P_2$ に
ベクトルを引き、$X_ν$ の局所系を使って、同じ座標値をもつ ($P_2$を通る平行なベクトル) ことを想像せよ。そのとき、この平行ベクトル
は、$P_1$ にあるベクトルと移動とによって、一意に決定される。我々は、この操作を、その一意性は後に示すが、ベクトル ($A^μ$) の
無限近傍点 $P_2$ への平行移動と呼ぶ。もし、我々が $P_2$ 点でのベクトル ($A^μ$)と $P_1$ から $P_2$ への平行移動によって得るベクトルと
のベクトルの差を作れば、我々は、ベクトル ($A^μ$) の与えられた変位 ($dx_ν$) に対する微分と見なすことのできるベクトルを得る。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
このベクトルの移動は、$x_ν$ の座標系に関しても、また自然に考えられる。$A^μ$ をそのベクトルの $P_1$ での座標値とし、$A^μ + δA^μ$ を
間隔 ($dx_ν$) に沿って $P_2$ に移動したベクトルの座標値とするなら、$δA^μ$ は、この場合、消えない。我々は、これらの量がベクトルの性質
を持たず、線形一様に $dx_ν$ と $A^μ$ に依存しなければならないことを知っている。我々は、それゆえ、次を置く。
\[
δA^ν= -Γ^ν_{αβ} A^α dx_β
\tag{67}
\]
我々は、さらに、$Γ^ν_{αβ}$ が、添字$α$と$β$に関して対称でなければならないことを言うことができる。なぜなら、我々は、局所座標の
ユークリッド系の助けによる表現から、要素 $d^{(1)} x_ν$ の2番目の要素 $d^{(2)} x_ν$ に沿う移動と $d^{(2)} x_ν $の $d^{(1)} x_ν $に沿う移動と
によって同じ平行四辺形が描かれると仮定できるからである。我々は、それゆえ、次を持たねばならない。
\[
d^{(2)} x_ν + {(d^{(1)} x_ν - Γ^ν_{αβ} d^{(1)} x_α d^{(2)} x_β)}\\
= d^{(1)} x_ν + {(d^{(2)} x_ν - Γ^ν_{αβ} d^{(2)} x_α d^{(1)} x_β)}
\]
上述のことは、この式から右辺の総和の添字$α$と$β$を交換して出る。
量 $g_{μν}$ は、連続体の全ての計量特性を決定するから、$Γ^ν_{αβ}$ をも決定しなければならない。
もし、ベクトル $A^μ$ の不変量を考えるなら、すなわち、その大きさの2乗、
\[
g_{μν} A^μ A^ν
\]
が不変量であり、これは、平行移動によって変化しえない。我々は、それゆえ、次をもつ。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
\[
0= δ(g_{μν} A^μ A^ν) = {∂g_{μν} \over ∂x_α} A^μ A^ν dx_α + g_{μν} A^μ δA^ν + g_{μν} A^ν δA^μ
\]
または、(67) によって、
\[
({∂g_{μν} \over ∂x_α} - g_{μβ} Γ^β_{να} - g_{νβ} Γ^β_{μα}) A^ν A^μ dx_α = 0
\]
括弧内の式の添字$μ$と$ν$に関する対称性のため、この式が ($A^μ$) と $d_ν$ の任意選択にも有効であることは、括弧内の式が添字のどの組合せ
にも消滅するときだけ可能である。添字$μ,ν,α$の周期的交換により、このように全部で 3 つの方程式を得て、そこから、$Γ^α_{μν}$の対称の
特性を考慮に入れて、次を得る。
\[
[μν, α]= g_{αβ} Γ^β_{μν}
\tag{68}
\]
ここでクリストッフェルに従って、次の省略記号を用いた。
\[
[μν, α]= {1 \over 2} ({∂g_{μα} \over ∂x_ν} + {∂g_{να} \over ∂x_μ} - {∂g_{μν} \over ∂x_α})
\tag{69}
\]
もし、(68)に $g^{ασ}$ を掛け、$α$に渡って総和すれば、次を得る。
\[
Γ^σ_{μν}= {1 \over 2} g^{σα} ({∂g_{μα} \over ∂x_ν }+ { ∂g_να \over ∂x_μ} -{∂g_μν \over ∂x_α}) = \{μν, σ\}
\tag{70}
\]
ここで $\{μν, σ\}$ は、第 2 種クリストッフェル記号である。このように、$Γ$ の量は、$g_{μν}$から導かれる。
式 (67), (70) は、これからの議論の基礎となる。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
テンソルの共変微分 もし、($A^μ + δA^μ$) が $P_1$ から $P_2$ への無限小平行移動の結果、得られるベクトル、($A^μ + dA^μ$)
が点 $P_2$ でのベクトル $A^μ$ なら、そのとき、これらふたつの差、
\[
dA^μ - δA^μ= ({∂A^μ \over ∂x_σ} + Γ^μ_{σα} A^α) dx_σ
\]
も、またベクトルである。これは、$dx_σ$の任意選択の場合であるから、次式、
\[
A^μ_;σ= {∂A^μ \over ∂x_σ} + Γ^μ_{σα} A^α
\tag{71}
\]
がテンソルであることが出る。我々は、これを1階のテンソル(ベクトル) の共変微分と呼ぶ。
このテンソルを縮約して反変テンソル $A^μ$の発散を得る。このなかに我々は、(70) に従って、次をみなければならない。
\[
Γ^σ_{μσ}= {1 \over 2} g^{σα} {∂g_{σα} \over ∂x_μ} = {1 \over \sqrt{g}} {∂ \sqrt{g} \over ∂x_μ}
\tag{72}
\]
もし、我々がさらに、次を置くなら、
\[
A^μ \sqrt{g} = A^μ
\tag{73}
\]
これはワイルが1階の反変テンソル密度(*)と呼ぶ量である。そこから、
\[
A= {∂A^μ \over ∂x_μ}
\tag{74}
\]
は、スカラー密度であることが出る。
(*) この表式は、$A^μ \sqrt{g} dx= A^μ dx $ がテンソルの特性をもつことのなかで正当化される。どのテンソルも$\sqrt{g}$ で乗算されるとき、
テンソル密度に変わる。我々は、テンソル密度には大文字のゴシック文字を使う。(訳注:全角文字を使用した。)
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
我々が、共変ベクトル $B_μ$ の平行移動の法則を得るのに、ある規則を作ることによる。それは、平行移動がスカラー、
\[
Φ= A^μ B_μ
\]
を不変に残すような方法で影響すべきこと、そして、それゆえ、
\[
A^μ δB_μ + B_μ δA^μ
\]
が、どんな値を ($A^μ$) に割り当てても消滅するという規則である。我々はそれゆえ、次を得る。
\[
δB_μ= Γ^α_{μσ} B_α dx_σ
\tag{75}
\]
これから、我々は、(71)を導いたと同様な過程によって、共変ベクトルの共変微分に到達する。
\[
B_{μ;σ}= {∂B_μ \over ∂x_σ} - Γ^α_{μσ} B_α
\tag{76}
\]
添字$μ$と$σ$の交換、そして引算によって、我々は、次の反対称テンソルを得る。
\[
Φ_{μσ}= {∂B_μ \over ∂x_σ} - {∂B_σ \over ∂x_μ}
\tag{77}
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
2階以上の階数のテンソルの共変微分については、我々は、(75)を導いた過程を使うことができる。
例えば、($A_{στ}$) を2階の共変テンソルとしよう。そのとき、$A_{στ} E^σ F^τ$ は、スカラーである、もし、$E$ と $F$ がベクトルであるなら。
この表式は、δ-移動によって変化してはならない;これを式で表し、我々は、(67)を使って$δA_{στ}$ を得、そこから次の目的の共変微分を得る。
\[
A_{στ\hspace{1mm};ρ}= {∂A_{στ} \over ∂x_ρ} - Γ^α_{σρ} A_{ατ} - Γ^α_{τρ} A_{σα}
\tag{78}
\]
テンソルの共変微分の一般的な法則を明確に見るため、類似の方法で導かれるふたつの共変微分を書き下す。
\[
A^τ_{σ;ρ} = {∂A^τ_σ \over ∂x_ρ} - Γ^α_{σρ} A^τ_α + Γ^τ_{αρ} A^α_σ
\tag{79}
\]
\[
A^{στ}_{;ρ}= {∂A^{στ} \over ∂x_ρ} + Γ^σ_{αρ} A^{ατ} + Γ^τ_{αρ} A^{σα}
\tag{80}
\]
形成の一般法則は、いま、明らかになる。これらの式から、理論の物理的応用において興味のある他のいくつかを導こう。
もし、$A_{στ}$が反対称であるなら、我々は次のテンソルを、
\[
A_{στρ}= {∂A_{στ} \over ∂x_ρ} + {∂A_{τρ} \over ∂x_σ} + {∂A_{ρσ} \over ∂x_τ}
\tag{81}
\]
それは、全ての添字の対に反対称であるが、周期的交換と加算によって得る。
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
もし、(78)のなかで、我々が $A_{στ}$ を基本テンソル $g_{στ}$ に置き換えるなら、そのとき、右辺は恒等的に消滅する; 類似の言明は、(80)
について、$g^{στ}$ に関して成立する; すなわち、基本テンソルの共変微分は、消滅する。これがそうでなくてならないことは、我々が直接に
局所座標系のなかで見ることである。
$A^{στ}$ が反対称の場合、我々は (80) から、$τ$と$ρ$に関する縮約によって、次を得る。
\[
A^σ= {∂A^{στ} \over ∂x_τ}
\tag{82}
\]
一般の場合、(79) と (80) から、$τ$と$ρ$に関する縮約によって、我々は、次の式を得る。
\[
A_σ= {∂A^α_σ \over ∂x_α} - Γ^α_{σβ} A^β_α
\tag{83}
\]
\[
A^σ= {∂A^{σα} \over ∂x_α} + Γ^σ_{αβ} A^{αβ}.
\tag{84}
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
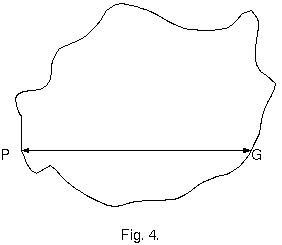
リーマンテンソル もし、我々が連続体の点 P から点 G に伸びる曲線が与えられたなら、そのとき、P に与えられたベクトル $A^μ$
は、平行移動によって G までその曲線に沿って動かすことができる。もし、連続体がユークリッド的 (より一般的に、座標の適切な選択に
よって $g_{μν}$ が一定である) ならば、そのとき、その移動の結果として G に得られるベクトルは、P と G を結ぶ曲線の選択に依存しない。
しかし、そうでないとき、結果は移動の経路に依存する。この場合は、それゆえ、ベクトルは、もし、それを点 P から閉じた曲線に沿って運び、
再び P に達するならば、$ΔA^μ$ (その方向に、その大きさでなく) の変化を被る。我々は、いま、このベクトルの変化を計算する。
\[
ΔA^μ= §δA^μ
\]
閉曲線の周りのベクトルの線積分へのストークスの定理のように、この問題は、無限小の線の大きさをもつ閉曲線の周りの積分に還元できる;
我々は、この場合に限定しよう。
我々は、最初に、(67) によって、
\[
ΔA^μ= -§ Γ^μ_{αβ} A^α dx_β
\]
このなかで $Γ^μ_{αβ}$ は、積分経路上の可変点 G にあるこの量の値である。もし、我々が次のように置き、
\[
ξ^μ= (x_μ)_G - (x_μ)_P
\]
P における $Γ^μ_{αβ}$ の値
を $\overline{Γ^μ_{αβ}}$ で表すと、そのとき、我々は、十分な精度をもって、次をもつ。
\[
Γ^μ_{αβ} = \overline{Γ^μ_{αβ} }+ {∂\overline{Γ^μ_{αβ}} \over ∂x_ν }dξ_ν
\]
さらに、$A^α$を
$\overline{A^α} $から P から G への曲線に沿った平行移動によって得られた値としよう。いま、(67)によって、容易に証明できるのは、
$A^μ -\overline{A^μ}$ が1次の無限小であり、一方、曲線が1次の無限小の大きさをもつから、$ΔA^μ$ は、2次の無限小であることである。それゆえ、
もし、我々が次のように置いても、2次のオーダーの誤差しかない。
\[
A^α = \overline{A^α} - \overline{Γ^α_{στ}} \ \overline{A^σ} \ \overline{ξ^τ}
\]
もし、我々がこれらの値、$Γ^μ_{αβ}$ と $A^α$ を積分に導入して、我々は、2次より高次の全ての量を無視して、次式を得る。
\[
ΔA^μ= -({∂Γ^μ_{σβ} \over ∂x_α} - Γ^μ_{ρβ}Γ^ρ_{σα}) A^σ §ξ^α dξ^β.
\tag{85}
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
積分記号の下から除かれた量は、点 P に関するものである。被積分から ${1 \over 2} d(ξ^αξ^β)$ を引いて、我々は次を得る。
\[
{1 \over 2} §(ξ^α dξ^β - ξ^β dξ^α)
\]
この 2 階の反対称テンソル $f^{αβ}$ は、その曲線で区切られた表面要素を、大きさと位置で特徴づける。もし、(85) の括弧内の式が添字$α$
と$β$に関して反対称なら、我々は、そのテンソル特性を (85) から結論できるだろう。我々は、 (85) の総和の添字$α$と$β$とを交換して、
結果の式を (85) に加算することによって、これを達成できる。我々は、次を得る。
\[
2ΔA^μ= - R^μ_{σαβ} A^σ f^αβ
\tag{86}
\]
ここで、
\[
R^μ_{σαβ}= -{∂Γ^μ_{σα} \over ∂x_β} + {∂Γ^μ_{σβ} \over ∂x_α} + Γ^μ_{ρα}Γ^ρ_{σβ} - Γ^μ_{ρβ}Γ^ρ_{σα}.
\tag{87}
\]
$R^μ_{σαβ}$ のテンソル特性は、(86)から出る; これは、4階のリーマン曲率テンソルであり、その対称性の特性についてさらには踏み込む
必要がない。その消滅は(選ばれた座標系の現実性に関わらず)、連続体がユークリッド的であることの十分条件である。添字$μ$と$β$に関して
リーマンテンソルを縮約すれば、我々は、次の2階の対称テンソルを得る。
\[
R_{μν}= - {∂Γ^α_{μν} \over ∂x_α} + Γ^α_{μβ}Γ^β_{να}+ {∂Γ^α_{μα} \over ∂x_ν} - Γ^α_{μν}Γ^β_{αβ}
\tag{88}
\]
最後の2項は、もし、座標系が $g=$ 一定であるように選ばれれば消滅する。$R_{μν}$ から、我々は、次のスカラーを形成できる。
\[
R= g^{μν} R_{μν}
\tag{89}
\]
≪=BACK TOP∧ NEXT=≫
最も真直な(測地)線 その継続する要素が、互いに平行移動から来るような方法で構成することができる線。これは、ユークリッド
幾何学の直線の自然な拡張である。そのような線には、我々は次をもつ。
\[
δ({dx_μ \over ds}) = - Γ^μ_{αβ} {dx_α \over ds} dx_β
\]
左辺は、${d^2x_μ \over ds^2}$ によって置き換えされ(*)、我々は、次を得る。
\[
{d^2x_μ \over ds^2} + Γ^μ_{αβ} {dx_α \over ds} {dx_β \over ds} = 0
\tag{90}
\]
もし、我々がふたつの点の間の、次の積分の停留値を与える線 (測地線) を見出すならば、我々は、同じ線を得る。
\[
∫ds 又は、 ∫\sqrt{g_{μν} dx_μ dx_ν}
\]
(*) 曲線上の隣接点の方向ベクトルは、考慮中の各点の方向ベクトルから、線要素 ($dx_β$) に沿った平行移動によってもたらされる。